けいざい四季報① 世界経済 量的緩和縮小で市場動揺
【ポイント】
①米国が量的金融緩和策を縮小。FRB議長は来春にも利上げの可能性を示唆
②米量的緩和縮小で新興国から資金流出。通貨防衛と物価抑制で利上げ相次ぐ
③欧州は3期連続のプラス成長で、今年もプラス予想。高失業や債務が足かせ
米連邦準備制度理事会(FRB)が量的金融緩和策を縮小していることに加え、イエレンFRB議長が来春にも政策金利を引き上げる可能性を示したことが、世界の金融市場に余波を広げています。
利上げを示唆
FRBは18、19両日の連邦公開市場委員会(FOMC)で、量的緩和の資産購入規模を100億ドル縮小し、月550億ドル(約5兆6000億円)にすると決定しました。
縮小決定は、昨年12月と今年1月に続いて100億ドルずつ3回目。
同時に、今後の指針では、インフレ率が2%を下回る限り、量的緩和終了後も実質ゼロ金利政策来は、失業率が6・5%を下回るという数値基準も付いていましたが、それを削除しました。
しかし、直近の2月の失業率は前月比0・1ポイント増の6・7%と、なお高水準です。
一方、イエレン議長は19日の会見で、量的緩和終了後もゼロ金利を続ける期間について「6カ月程度」と発言。量的緩和終了は今秋とみられており、来春にも利上げがあり得ることになります。
一般予測より早い利上げの可能性に、19日の市場は動揺し、株価下落や長期金利上昇に見舞われ、アジア市場にも余波が広がりました。
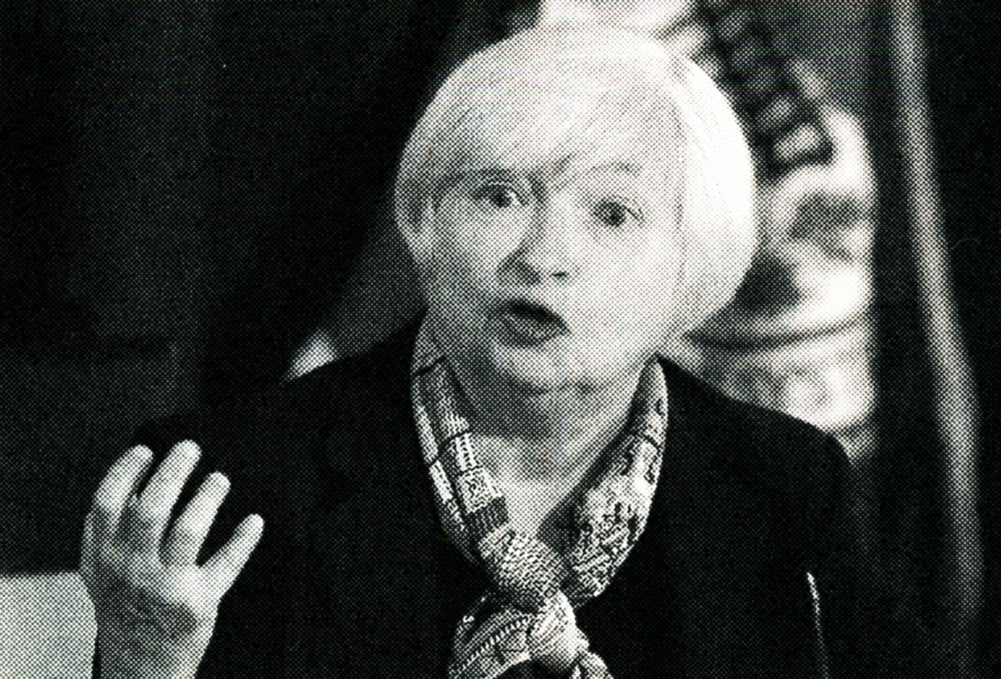
FOMC後、記者会見するイエレンFRB議長=19日、ワシントン(ロイター)
通貨安に対処
米国の量的緩和の縮小は、新興諸国へ流入していた「緩和マネー」の逆流を起こしました。そのため、これら諸国は、自国通貨の下落による物価上昇や経常収支悪化への対処に追われ、利上げが相次ぎました。
インドは1月28日、貸出金利を0・25%上げ、8%としました。5カ月間で3度目。10年ぶりの低成長にもかかわらず、景気対策よりも、通貨下落による物価上昇への対処を優先しました。
トルコも同日、貸出金利を4・25%上げ、12%としました。ほぼ2年ぶり高水準。やはり、急激な資金流出をくいとめ、通貨下落に伴う物価上昇を抑える必要に迫られました。
南アフリカは1月29日、政策金利を5・0%から5・5%へ引き上げました。08年6月以来。ブラジルも2月26日、政策金利を10・50%から10・75%へ引き上げました。政策会合7回連続です。
なお高失業率
欧州連合(EU)統計局が2月14日発表したユーロ圏(17力国)の2013年10~12月期の国内総生産(GDP)は、前期比0・3%増、年率換算で1・1%増と、3四半期連続のプラス成長でした。
EU欧州委員会は2月25日、ユーロ圏(18力国)の14年の成長率見通しを1・2%と発表し、昨年11月時点の1・1%の予想を上方修正しました。ひところの政府債務危機が沈静化し、景況感は上向いています。しかし、失業率や債務の対GDP比が高止まりしており、景気回復の足かせになっています。
EU統計局が2月28日発表したユーロ圏(18力国)の1月の失業率は、前月と同じ12・0%でした。昨年10月以来、横ばいが続いています。特に、15~24歳の若年層の失業率は、前月比0・1ポイント低下したものの、なお24%の高水準です。
世界経済の主な出来事(1~3月)
1/10 13年中国貿易総額が初の4兆ドル突破と発表
1/28~29 米FRBが量的緩和策を月100億ドル縮小。12月以来2回目
1/28 インドが利上げ
1/28 トルコが利上げ
1/29 南アフリカが利上げ
2/15 米国の「債務上限暫定延長法」が成立。15年3月15日まで
2/22~23 G20が「5年間で成長率2%以上引き上げ」の共同声明
2/25 14年のユー口圏諸国GDPが前年比1.2%増との見通しを発表
2/26 ブラジルが利上げ
2/28 1月のユー口圏失業率が12%と発表。4カ月連続で横ばい
3/17 中国が人民元の許容変動幅を基準値の上下1%から2%へ拡大
3/19 米FRBが量的緩和策を月100億ドル縮小。議長は利上げを示唆
(つづく)(5回連載の予定です)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2014年3月25日付掲載
【ポイント】
①米国が量的金融緩和策を縮小。FRB議長は来春にも利上げの可能性を示唆
②米量的緩和縮小で新興国から資金流出。通貨防衛と物価抑制で利上げ相次ぐ
③欧州は3期連続のプラス成長で、今年もプラス予想。高失業や債務が足かせ
米連邦準備制度理事会(FRB)が量的金融緩和策を縮小していることに加え、イエレンFRB議長が来春にも政策金利を引き上げる可能性を示したことが、世界の金融市場に余波を広げています。
利上げを示唆
FRBは18、19両日の連邦公開市場委員会(FOMC)で、量的緩和の資産購入規模を100億ドル縮小し、月550億ドル(約5兆6000億円)にすると決定しました。
縮小決定は、昨年12月と今年1月に続いて100億ドルずつ3回目。
同時に、今後の指針では、インフレ率が2%を下回る限り、量的緩和終了後も実質ゼロ金利政策来は、失業率が6・5%を下回るという数値基準も付いていましたが、それを削除しました。
しかし、直近の2月の失業率は前月比0・1ポイント増の6・7%と、なお高水準です。
一方、イエレン議長は19日の会見で、量的緩和終了後もゼロ金利を続ける期間について「6カ月程度」と発言。量的緩和終了は今秋とみられており、来春にも利上げがあり得ることになります。
一般予測より早い利上げの可能性に、19日の市場は動揺し、株価下落や長期金利上昇に見舞われ、アジア市場にも余波が広がりました。
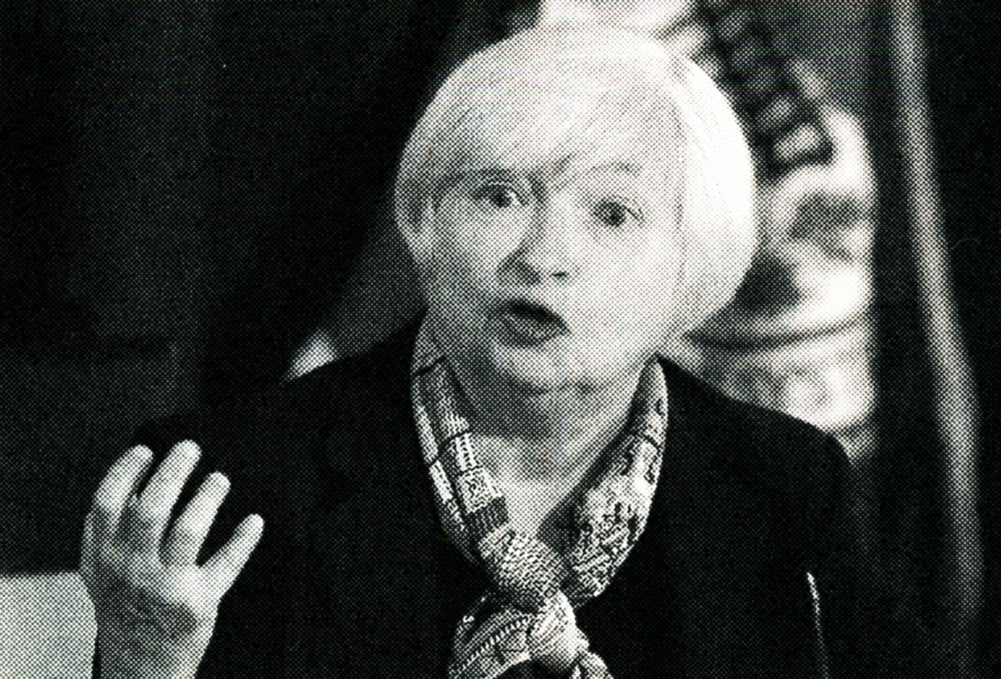
FOMC後、記者会見するイエレンFRB議長=19日、ワシントン(ロイター)
通貨安に対処
米国の量的緩和の縮小は、新興諸国へ流入していた「緩和マネー」の逆流を起こしました。そのため、これら諸国は、自国通貨の下落による物価上昇や経常収支悪化への対処に追われ、利上げが相次ぎました。
インドは1月28日、貸出金利を0・25%上げ、8%としました。5カ月間で3度目。10年ぶりの低成長にもかかわらず、景気対策よりも、通貨下落による物価上昇への対処を優先しました。
トルコも同日、貸出金利を4・25%上げ、12%としました。ほぼ2年ぶり高水準。やはり、急激な資金流出をくいとめ、通貨下落に伴う物価上昇を抑える必要に迫られました。
南アフリカは1月29日、政策金利を5・0%から5・5%へ引き上げました。08年6月以来。ブラジルも2月26日、政策金利を10・50%から10・75%へ引き上げました。政策会合7回連続です。
なお高失業率
欧州連合(EU)統計局が2月14日発表したユーロ圏(17力国)の2013年10~12月期の国内総生産(GDP)は、前期比0・3%増、年率換算で1・1%増と、3四半期連続のプラス成長でした。
EU欧州委員会は2月25日、ユーロ圏(18力国)の14年の成長率見通しを1・2%と発表し、昨年11月時点の1・1%の予想を上方修正しました。ひところの政府債務危機が沈静化し、景況感は上向いています。しかし、失業率や債務の対GDP比が高止まりしており、景気回復の足かせになっています。
EU統計局が2月28日発表したユーロ圏(18力国)の1月の失業率は、前月と同じ12・0%でした。昨年10月以来、横ばいが続いています。特に、15~24歳の若年層の失業率は、前月比0・1ポイント低下したものの、なお24%の高水準です。
世界経済の主な出来事(1~3月)
1/10 13年中国貿易総額が初の4兆ドル突破と発表
1/28~29 米FRBが量的緩和策を月100億ドル縮小。12月以来2回目
1/28 インドが利上げ
1/28 トルコが利上げ
1/29 南アフリカが利上げ
2/15 米国の「債務上限暫定延長法」が成立。15年3月15日まで
2/22~23 G20が「5年間で成長率2%以上引き上げ」の共同声明
2/25 14年のユー口圏諸国GDPが前年比1.2%増との見通しを発表
2/26 ブラジルが利上げ
2/28 1月のユー口圏失業率が12%と発表。4カ月連続で横ばい
3/17 中国が人民元の許容変動幅を基準値の上下1%から2%へ拡大
3/19 米FRBが量的緩和策を月100億ドル縮小。議長は利上げを示唆
(つづく)(5回連載の予定です)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2014年3月25日付掲載











