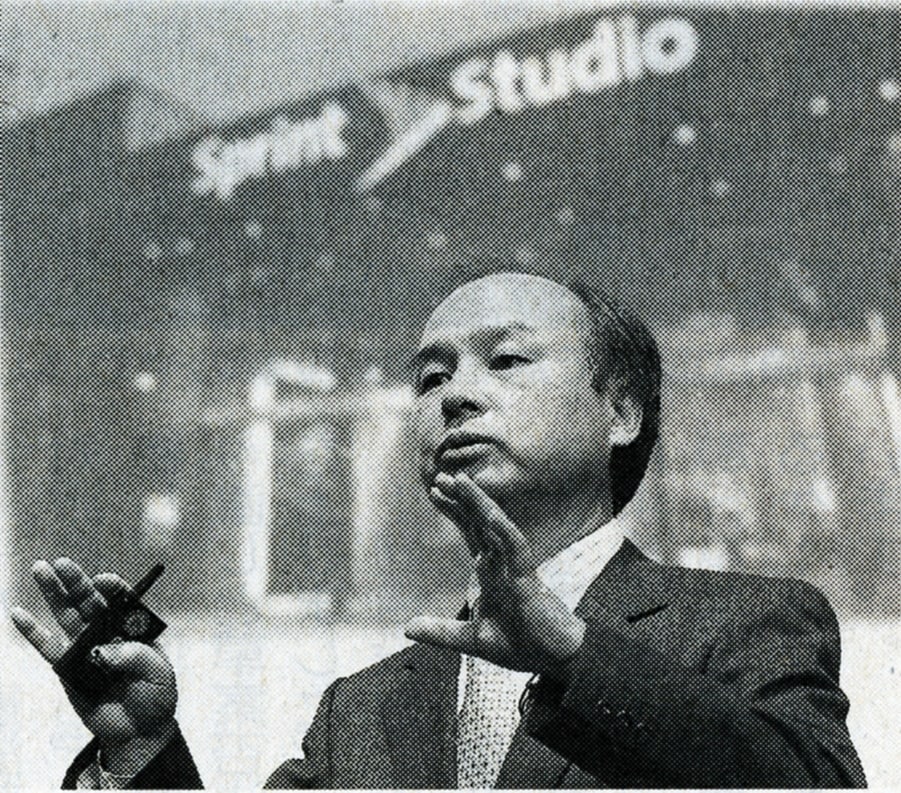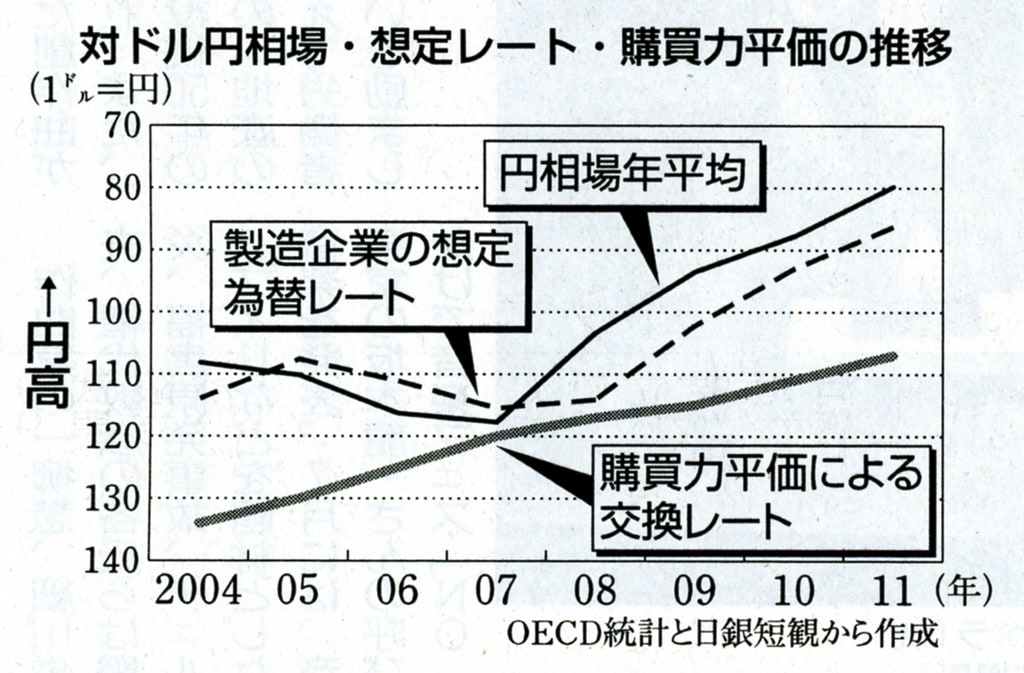検証 超円高④ 対米従属から抜け出て
国民の利益を守る立場から、自国の通貨を為替の投機的変動から守ることは、各国の主権に属する問題です。
日本同様、自国通貨高に悩むスイスでは2011年9月、中央銀行がスイス・フラン防衛のため無制限の為替介入を行うことを決定。1ユーロ=1・20スイス・フランを超えるスイス・フラン高は許容しないことを宣言しました。自国の利益のために通貨を断固として守る姿勢は日本と違います。
しかし、日本政府は日米安保体制のもとで、米国との関係を何よりも優先させ、ドル基軸通貨体制を支えてきました。その一方、日本国民の経済的利益を守るために必要な手立てをとってきませんでした。日米安保条約を廃棄し、従属関係から抜け出せば、日本経済を立て直す展望が生まれます。

東京都内の工場(ロイター)
■内需主導に
日本が円高危機を繰り返し、そのつど労働者や中小企業が犠牲にされてきた原因は、輸出依存の経済構造でした。それを改めるには、国民の生活を中心にした内需主導の経済に転換することが不可欠です。そのためにも安保条約の廃棄が必要です。
日本は1960年代、米国の技術をもとに対米輸出を拡大し、高度成長を遂げました。これが輸出依存の経済構造をつくり上げました。
安保条約第2条は、「国際経済政策におけるくい違いを除くことに努める」と定めています。
米国大企業はこれを根拠として、常に自国の経済ルールを日本に押し付けてきました。派遣労働の自由化や労働時間の規制緩和は、日本の財界の要求であるとともに、米国大企業の要求でした。
その結果、非正規雇用が増え、長時間・過密労働が深刻化。大企業が労働者を犠牲にしてコストを削減することがまかり通ってきました。これが円高をさらに加速させてきました。この悪循環を断つためにも、経済主権の回復が不可欠です。
■投機規制を
「超円高」を引き起こしているのは、米国を基盤とする投機筋です。巨額の投機が異常な円高を引き起こすことを防ぐには国際的に金融投機を規制する必要があります。
欧州連合(EU)は通貨取引税を創設して、金融投機を規制する道に踏み出しています。日本政府も通貨取引税を含め、国際的な為替投機の規制に向けて踏み出す必要があります。しかし、米国は国際的な投機規制に消極的です。経団連など日本の財界は、金融取引税の導入に反対。米国と財界言いなりの日本政府は導入にきわめて消極的です。
日本が米国への従属を断ち切ることは、自主的な投機規制を行う上でも欠かせません。
中央大学の今宮謙二名誉教授は、「自主的な政策を行うことによって円高対策も可能になる」といいます。
「円高対策の基本は日本が内需主導で安定した経済成長をすることです。そうすれば、投機筋の動きも活発化せず、為替相場も本来の水準になっていく可能性があります。日米安保条約を廃棄し、対等平等の日米友好条約を結んで、日本の経済主権を確立すべきです」と強調します。
(おわり)(この連載は山田俊英が担当しました)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2012年12月21日付掲載
「儲かりさえすればどこで生産してもいい」って事じゃなく、やはり国内での生産と消費をメインに経済政策を転換していかないといけないですね。
地域の業者さんはもちろんですが、大企業にも巡り巡って良い方向になるんですがねえ。
そして大企業の260兆円もの内部留保のごく一部を労働者の所得や下請け単価に還元することにより経済が好転するとともに、投機マネーの規模自体を縮小させることにもなります。
上下(うえした)両方でいい方向にいくんですがねえ…
国民の利益を守る立場から、自国の通貨を為替の投機的変動から守ることは、各国の主権に属する問題です。
日本同様、自国通貨高に悩むスイスでは2011年9月、中央銀行がスイス・フラン防衛のため無制限の為替介入を行うことを決定。1ユーロ=1・20スイス・フランを超えるスイス・フラン高は許容しないことを宣言しました。自国の利益のために通貨を断固として守る姿勢は日本と違います。
しかし、日本政府は日米安保体制のもとで、米国との関係を何よりも優先させ、ドル基軸通貨体制を支えてきました。その一方、日本国民の経済的利益を守るために必要な手立てをとってきませんでした。日米安保条約を廃棄し、従属関係から抜け出せば、日本経済を立て直す展望が生まれます。

東京都内の工場(ロイター)
■内需主導に
日本が円高危機を繰り返し、そのつど労働者や中小企業が犠牲にされてきた原因は、輸出依存の経済構造でした。それを改めるには、国民の生活を中心にした内需主導の経済に転換することが不可欠です。そのためにも安保条約の廃棄が必要です。
日本は1960年代、米国の技術をもとに対米輸出を拡大し、高度成長を遂げました。これが輸出依存の経済構造をつくり上げました。
安保条約第2条は、「国際経済政策におけるくい違いを除くことに努める」と定めています。
米国大企業はこれを根拠として、常に自国の経済ルールを日本に押し付けてきました。派遣労働の自由化や労働時間の規制緩和は、日本の財界の要求であるとともに、米国大企業の要求でした。
その結果、非正規雇用が増え、長時間・過密労働が深刻化。大企業が労働者を犠牲にしてコストを削減することがまかり通ってきました。これが円高をさらに加速させてきました。この悪循環を断つためにも、経済主権の回復が不可欠です。
■投機規制を
「超円高」を引き起こしているのは、米国を基盤とする投機筋です。巨額の投機が異常な円高を引き起こすことを防ぐには国際的に金融投機を規制する必要があります。
欧州連合(EU)は通貨取引税を創設して、金融投機を規制する道に踏み出しています。日本政府も通貨取引税を含め、国際的な為替投機の規制に向けて踏み出す必要があります。しかし、米国は国際的な投機規制に消極的です。経団連など日本の財界は、金融取引税の導入に反対。米国と財界言いなりの日本政府は導入にきわめて消極的です。
日本が米国への従属を断ち切ることは、自主的な投機規制を行う上でも欠かせません。
中央大学の今宮謙二名誉教授は、「自主的な政策を行うことによって円高対策も可能になる」といいます。
「円高対策の基本は日本が内需主導で安定した経済成長をすることです。そうすれば、投機筋の動きも活発化せず、為替相場も本来の水準になっていく可能性があります。日米安保条約を廃棄し、対等平等の日米友好条約を結んで、日本の経済主権を確立すべきです」と強調します。
(おわり)(この連載は山田俊英が担当しました)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2012年12月21日付掲載
「儲かりさえすればどこで生産してもいい」って事じゃなく、やはり国内での生産と消費をメインに経済政策を転換していかないといけないですね。
地域の業者さんはもちろんですが、大企業にも巡り巡って良い方向になるんですがねえ。
そして大企業の260兆円もの内部留保のごく一部を労働者の所得や下請け単価に還元することにより経済が好転するとともに、投機マネーの規模自体を縮小させることにもなります。
上下(うえした)両方でいい方向にいくんですがねえ…