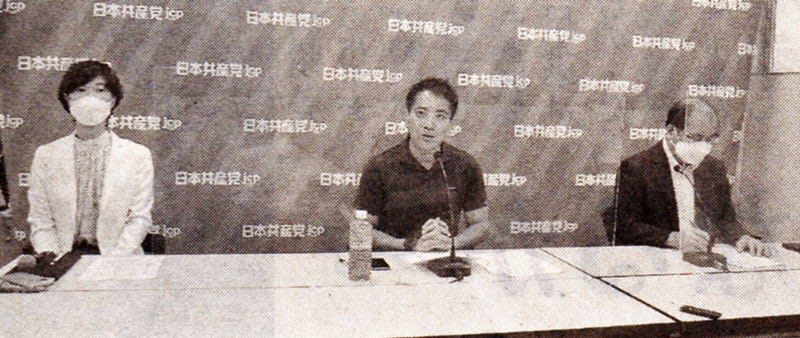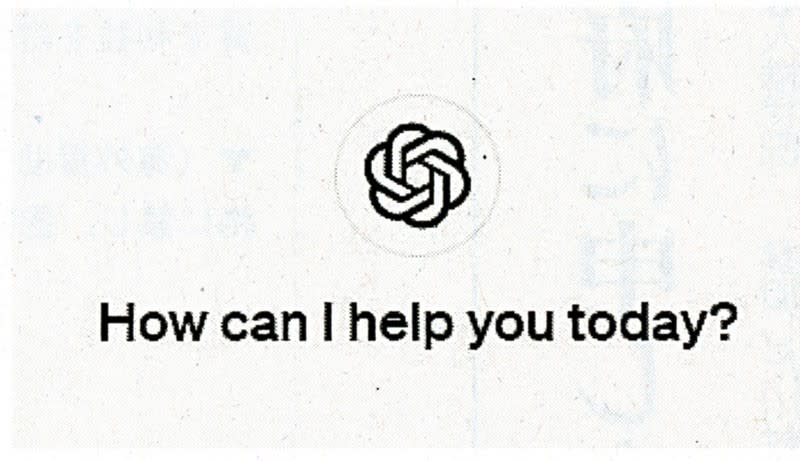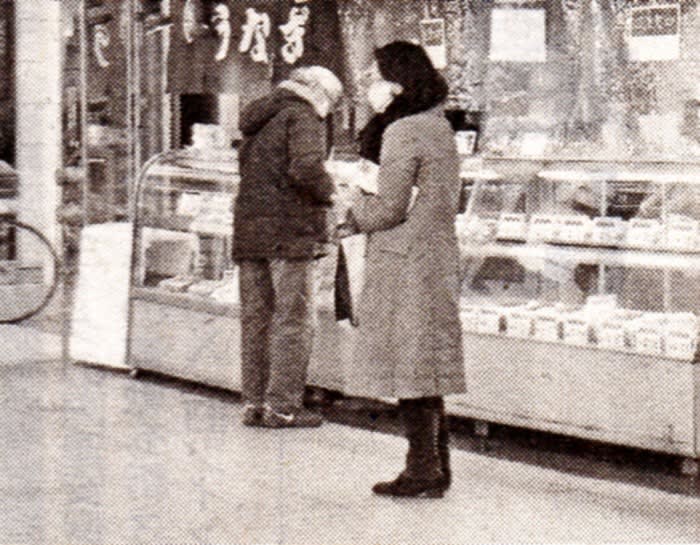維新万博を問う② 「身を切る改革」どこへ
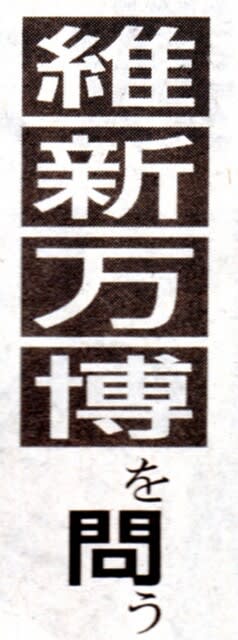
「昭和の3大バカ査定」(戦艦大和、伊勢湾干拓、青函トンネル)ならぬ、「令和の3大バカ査定」とは何か。「大阪万博、リニア新幹線、防衛費増強か」1昨年10月25日付「日刊スポーツ」のコラム「政界地獄耳」は、こう描きました。
膨張続ける建設費
「バカ査定」とは言い得て妙です。当初「1250億円」とした万博会場建設費が、2020年末には「1850億円」。「これで増加の話は最後」と吉村洋文大阪府知事が語った言葉はどこへやら。昨年10月には「2350億円」と約2倍に。その直後に今度は政府が「日本館建設」「警備費等」で新たに850億円が出されました。
上振れは「会場建設費」にとどまりません。政府が先月19日公表した万博「インフラ整備費」は8390億円。シャトルバスルートとして整備を急ぎ2・5倍に膨らんだ淀川左岸線2期工事も含まれます。さらに、万博開催に乗じた広域的なインフラ整備費が9・7兆円とされています。ここには、四国や山陰地方の自動車道の整備費まで含まれています。まさに「底なし沼」状態です。

「世界一高価な日よけ」とも批判されている「大屋根」(木造リング)の建設=大阪市此花区・夢洲の万博会場
木造リング350億円
会場建設費のなかでは、ワイド・ショーでもあいついでとりあげられた「350億円の木造リング」が批判の的です。「なぜ必要なのか」と問われた自見英子万博担当相が「日よけのため」と語ったことでも話題になりました。
「半年で解体するのに、なぜ350億円も!」。先月12月9日のMBS「報道特集」では、キャスターが「世界最大級の木造建築物を、環境負荷をかけて建てたのにすぐに撤去するということが、果たしてSDGs(持続可能な開発目標)の観点からどうなのか」と語りました。
あわてて「移設案」「保存案」が浮上しているものの、専門家は「保存なら補強工事、防水・防腐処理で150億円必要。維持費も年5億円!」と指摘しています。(昨年11月30日のテレ朝系「羽鳥モーニングショー」)
昨年の「朝日」10月1日付社説は「万博の経費増国民にツケを回すのか」と掲げ、こう指摘しました。「万博は維新が掲げる『身を切る改革』の例外なのか、厳しく闇われよう」(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2024年1月13日付掲載
「昭和の3大バカ査定」(戦艦大和、伊勢湾干拓、青函トンネル)ならぬ、「令和の3大バカ査定」とは何か。
「バカ査定」とは言い得て妙です。当初「1250億円」とした万博会場建設費が、2020年末には「1850億円」。「これで増加の話は最後」と吉村洋文大阪府知事が語った言葉はどこへやら。昨年10月には「2350億円」と約2倍に。その直後に今度は政府が「日本館建設」「警備費等」で新たに850億円が。
会場建設費のなかでは、ワイド・ショーでもあいついでとりあげられた「350億円の木造リング」が批判の的。
先月12月9日のMBS「報道特集」では、キャスターが「世界最大級の木造建築物を、環境負荷をかけて建てたのにすぐに撤去するということが、果たしてSDGs(持続可能な開発目標)の観点からどうなのか」
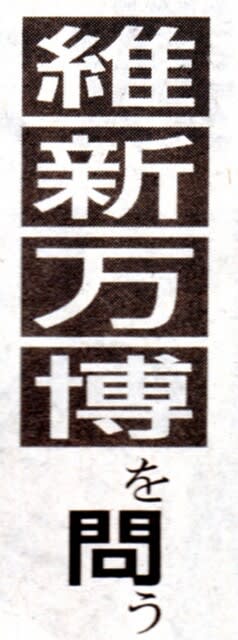
「昭和の3大バカ査定」(戦艦大和、伊勢湾干拓、青函トンネル)ならぬ、「令和の3大バカ査定」とは何か。「大阪万博、リニア新幹線、防衛費増強か」1昨年10月25日付「日刊スポーツ」のコラム「政界地獄耳」は、こう描きました。
膨張続ける建設費
「バカ査定」とは言い得て妙です。当初「1250億円」とした万博会場建設費が、2020年末には「1850億円」。「これで増加の話は最後」と吉村洋文大阪府知事が語った言葉はどこへやら。昨年10月には「2350億円」と約2倍に。その直後に今度は政府が「日本館建設」「警備費等」で新たに850億円が出されました。
上振れは「会場建設費」にとどまりません。政府が先月19日公表した万博「インフラ整備費」は8390億円。シャトルバスルートとして整備を急ぎ2・5倍に膨らんだ淀川左岸線2期工事も含まれます。さらに、万博開催に乗じた広域的なインフラ整備費が9・7兆円とされています。ここには、四国や山陰地方の自動車道の整備費まで含まれています。まさに「底なし沼」状態です。

「世界一高価な日よけ」とも批判されている「大屋根」(木造リング)の建設=大阪市此花区・夢洲の万博会場
木造リング350億円
会場建設費のなかでは、ワイド・ショーでもあいついでとりあげられた「350億円の木造リング」が批判の的です。「なぜ必要なのか」と問われた自見英子万博担当相が「日よけのため」と語ったことでも話題になりました。
「半年で解体するのに、なぜ350億円も!」。先月12月9日のMBS「報道特集」では、キャスターが「世界最大級の木造建築物を、環境負荷をかけて建てたのにすぐに撤去するということが、果たしてSDGs(持続可能な開発目標)の観点からどうなのか」と語りました。
あわてて「移設案」「保存案」が浮上しているものの、専門家は「保存なら補強工事、防水・防腐処理で150億円必要。維持費も年5億円!」と指摘しています。(昨年11月30日のテレ朝系「羽鳥モーニングショー」)
昨年の「朝日」10月1日付社説は「万博の経費増国民にツケを回すのか」と掲げ、こう指摘しました。「万博は維新が掲げる『身を切る改革』の例外なのか、厳しく闇われよう」(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2024年1月13日付掲載
「昭和の3大バカ査定」(戦艦大和、伊勢湾干拓、青函トンネル)ならぬ、「令和の3大バカ査定」とは何か。
「バカ査定」とは言い得て妙です。当初「1250億円」とした万博会場建設費が、2020年末には「1850億円」。「これで増加の話は最後」と吉村洋文大阪府知事が語った言葉はどこへやら。昨年10月には「2350億円」と約2倍に。その直後に今度は政府が「日本館建設」「警備費等」で新たに850億円が。
会場建設費のなかでは、ワイド・ショーでもあいついでとりあげられた「350億円の木造リング」が批判の的。
先月12月9日のMBS「報道特集」では、キャスターが「世界最大級の木造建築物を、環境負荷をかけて建てたのにすぐに撤去するということが、果たしてSDGs(持続可能な開発目標)の観点からどうなのか」