PHDガイディングを導入して半年が経っても相変わらず”星は流れていた”。
2011/11/26撮影 「北アメリカ星雲&ペリカン星雲」
NFD300mm EM-200USD赤道儀 GS-60Sガイドスコープ PHD ガイディング


( これまでの「星の流れ」は )
・・
・・・・
・・・・・・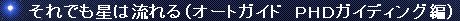
問題はPHDガイディングの制御グラフでは±1ピクセル程度で収まっているのに、画像の特に赤経(Ra)が進み過ぎる事。

上記の11/26の「北アメリカ星雲&ペリカン星雲」の追尾グラフでは
△Ra=39.4 ピクセル/H (進み)
ふしぎな事に、ノータッチガイドの頃から赤経(Ra)が進むという傾向は変わらない。
この時点でのわたしの推測は以下のようなものだった。
(1)EM-200赤道儀のモーター回転数は日周運動(恒星時)より少し早い。(精度不足)
(2)PHDガイディングのアルゴリズムで、ガイド星が検出枠を外れようとすると、枠自体をスライドさせる事でガイド星を見失わないようにしている。
この2つの要因が合わさって、毎回赤経(Ra)が進む現象を起こしていると思い込んでいた。
このため、ガイド星が枠から外れにくくするために、ガイドスコープの焦点距離を短くしたり、PHDガイディングのパラメータを変更したりしたが”星の流れ”は改善しなかった。
そこで、ほんとにそうか?の検証を12月に入ってやっと実施した。
検証は以下のような簡単な方法でおこなった。
「PHDガイディング動作中に赤道儀への制御用コードを抜いてみる。」

当然、赤道儀には制御信号が届かないのでガイド星は次第にズレてゆき、検出枠をはみだそうとする。
このときに、検出枠がガイド星を追うようにスライドするかどうか?
結果は 『ガイド星が枠を越えて更に外れていったのに、おかまいなしに枠はそのままだった!』
もっと早くこの検証をすれば良かった!・・・思い込みが強すぎた。(反省)
と、なれば
『PHDガイディングは正常に星を追尾している』・・・と考えられる。
ここでふたたび、Orion SSAGについてきたマニュアルを読み直してみた。
『グラフがおだやかなのに、星が流れるのはトータルな光学系の強度の問題』 とある。
思い込みを捨てて冷静に考えてみると、わたしの場合東側が家屋の影になるため、
(1)もっぱら天頂付近から次第に西に傾いていく対象を撮影している。
(2)撮影する鏡筒は撮り始めは真上方向を向いているが、次第に西側に”おじぎ”をするように傾きを増す。
ここでガイドスコープに比べて、重量のある撮影鏡筒のバランスが悪く、且つ取り付け部が弱いとしたら・・・・
ちょうど
「物干し竿の先に重たいものをぶら下げて、はじめは竿をまっすぐに、次第に竿を傾けていったら・・・」
だんだん持っているのがつらくなるのでは。
追尾結果のグラフを良く見ると、時間とともに進みが大きくなっている。
これは西側に傾くにつれて、「星の動きを追うモータ回転」+「”おじき”によるたわみの増加」 で発生していると考えられる。
となれば、その対策は
●物干し竿の先の重りを減らすための バランス調整
●多少の重り(バランスくずれ)なら耐えられる 支持部の強化
次回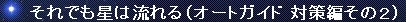 では、
では、
実際に実施した対策の内容について掲載します。
========================================================
冬季間にもかかわらず、つい先日も撮影することができました。
最新の追尾データもこれから調べて、対策と効果を検証してみます。
雲上(くもがみ)
ブログランキング参加しています。
 ← ポチッとお願いします。
← ポチッとお願いします。
にほんブログ村
========================================================
2011/11/26撮影 「北アメリカ星雲&ペリカン星雲」
NFD300mm EM-200USD赤道儀 GS-60Sガイドスコープ PHD ガイディング


( これまでの「星の流れ」は )
・・
・・・・
・・・・・・
問題はPHDガイディングの制御グラフでは±1ピクセル程度で収まっているのに、画像の特に赤経(Ra)が進み過ぎる事。

上記の11/26の「北アメリカ星雲&ペリカン星雲」の追尾グラフでは
△Ra=39.4 ピクセル/H (進み)
ふしぎな事に、ノータッチガイドの頃から赤経(Ra)が進むという傾向は変わらない。
この時点でのわたしの推測は以下のようなものだった。
(1)EM-200赤道儀のモーター回転数は日周運動(恒星時)より少し早い。(精度不足)
(2)PHDガイディングのアルゴリズムで、ガイド星が検出枠を外れようとすると、枠自体をスライドさせる事でガイド星を見失わないようにしている。
この2つの要因が合わさって、毎回赤経(Ra)が進む現象を起こしていると思い込んでいた。
このため、ガイド星が枠から外れにくくするために、ガイドスコープの焦点距離を短くしたり、PHDガイディングのパラメータを変更したりしたが”星の流れ”は改善しなかった。
そこで、ほんとにそうか?の検証を12月に入ってやっと実施した。
検証は以下のような簡単な方法でおこなった。
「PHDガイディング動作中に赤道儀への制御用コードを抜いてみる。」

当然、赤道儀には制御信号が届かないのでガイド星は次第にズレてゆき、検出枠をはみだそうとする。
このときに、検出枠がガイド星を追うようにスライドするかどうか?
結果は 『ガイド星が枠を越えて更に外れていったのに、おかまいなしに枠はそのままだった!』
もっと早くこの検証をすれば良かった!・・・思い込みが強すぎた。(反省)
と、なれば
『PHDガイディングは正常に星を追尾している』・・・と考えられる。
ここでふたたび、Orion SSAGについてきたマニュアルを読み直してみた。
『グラフがおだやかなのに、星が流れるのはトータルな光学系の強度の問題』 とある。
思い込みを捨てて冷静に考えてみると、わたしの場合東側が家屋の影になるため、
(1)もっぱら天頂付近から次第に西に傾いていく対象を撮影している。
(2)撮影する鏡筒は撮り始めは真上方向を向いているが、次第に西側に”おじぎ”をするように傾きを増す。
ここでガイドスコープに比べて、重量のある撮影鏡筒のバランスが悪く、且つ取り付け部が弱いとしたら・・・・
ちょうど
「物干し竿の先に重たいものをぶら下げて、はじめは竿をまっすぐに、次第に竿を傾けていったら・・・」
だんだん持っているのがつらくなるのでは。
追尾結果のグラフを良く見ると、時間とともに進みが大きくなっている。
これは西側に傾くにつれて、「星の動きを追うモータ回転」+「”おじき”によるたわみの増加」 で発生していると考えられる。
となれば、その対策は
●物干し竿の先の重りを減らすための バランス調整
●多少の重り(バランスくずれ)なら耐えられる 支持部の強化
次回
実際に実施した対策の内容について掲載します。
========================================================
冬季間にもかかわらず、つい先日も撮影することができました。
最新の追尾データもこれから調べて、対策と効果を検証してみます。
雲上(くもがみ)
ブログランキング参加しています。
にほんブログ村
========================================================
















