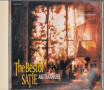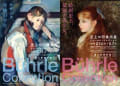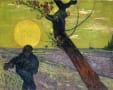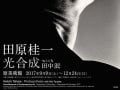8月が終わり幾分暑さも和らいだら、もっと書きたくなってきたけど、「定番CD」の話をもう少し。僕が若い時からよく聴いているのは、なんといってもモーツァルト。ビートルズやコルトレーンはCDを買い直さなかったけど、モーツァルトはレコードで持ってた名盤もかなりCDで買い直した。レコードも聴けるマルチプレーヤーも持ってるが、やっぱりレコードは面倒くさい。

ゴダールの「勝手にしやがれ」に、ジャン=ピエール・ベルモンドが部屋でモーツァルトの「クラリネット協奏曲」を聴く場面がある。なんていう美しい音楽だろうと思った。学生時代に山口昌男をよく読んでたが、どこかに「勝手にしやがれ」で「ピアノ協奏曲」が流れると書かれていた。あれ、間違ってると思った記憶があるから、学生時代にモーツァルトを聴いてたのである。
モーツァルトの音楽をよく「天国的」と評するけど、僕も全くそんな気分だった。若い時分に見たり聴いたり読んだりして、これは人類史上の天才だと思ったのはモーツァルトだけだ。お金の問題で買えるレコードは限られるけど、それでもずいぶん持ってた。割と何でも聴く方だけど、一番好きなのは間違いなくモーツァルトだった。年をとってもずっと聴くもんだと思っていた。まさかあの天国的な澄み渡った明るさより、バッハの方がいいと思う時期が来るとは思わなかった。
いろいろ聞いた中で、好きなのはコンチェルト(協奏曲)が多い。交響曲が嫌いなわけじゃないけど、長くて聴く方も力がいるからあまり聴かない。オペラも素晴らしいし、新国立劇場に見に行ったこともあるけど、モーツァルトに限らず一枚もCDを持ってない。(レコードやDVDも。)これも長くて高いから。ということで、聴くのはほとんど協奏曲。素晴らしいのはいくつもあるが、中でもクラリネット協奏曲とクラリネット五重奏曲が圧倒的に素晴らしいと思っている。
それもレオポルド・ウラッハ(1902~1956)のもの。オーストリアのクラリネット奏者で、ウィーン国立歌劇場とウィーンフィルの首席奏者を務めた。54歳で亡くなっているが、モノラルで残されたウラッハの音色の素晴らしさは一頭抜けていると思う。全部聴いたわけじゃないけど、ウラッハ盤を聴いたらもうそれでいいという気分になる。クラリネット協奏曲は1791年に書かれたもので、モーツァルト最後の協奏曲。クラリネット五重奏曲は1789年に書かれた。
甲乙つけがたい名曲だが、若いころは圧倒的にクラリネット協奏曲の方が大好きだった。とにかく美しくて、心が晴れ晴れとする。その開放感が素晴らしい。しかし、だんだんもう少し憂愁の趣が欲しいと思うようになった。五重奏曲の方がいいぞと思うようになった。今じゃ、聴くのはクラリネット五重奏曲ばかりである。年とると変わるのである。クラリネットという楽器はモーツァルト時代には、ようやくオーケストラに入るようになった新しい楽器だった。どっちも友人のアントン・シュタードラーのために作曲されたもので、クラリネットの魅力を見事に引き出している。
クラリネット以外では、フルート協奏曲、フルートとハープのための協奏曲、ヴァイオリン協奏曲、ファゴット協奏曲、ホルン協奏曲など多くの協奏曲を書いている。もちろん、27番まであるピアノ協奏曲を忘れてはいけない。ピアノ協奏曲は明るいもの、暗いものが分かれているから、どれが好きかで心が揺れる。しかし、次第に最後の27番がいいなと思うようになった。モーツァルトには伝説的な話がいっぱいあるが、僕はあまり関心がなく曲だけあれば十分だ。また「レクイエム」も素晴らしい。モーツァルトは僕などがいくら書いても仕方ないのでもう止める。

ゴダールの「勝手にしやがれ」に、ジャン=ピエール・ベルモンドが部屋でモーツァルトの「クラリネット協奏曲」を聴く場面がある。なんていう美しい音楽だろうと思った。学生時代に山口昌男をよく読んでたが、どこかに「勝手にしやがれ」で「ピアノ協奏曲」が流れると書かれていた。あれ、間違ってると思った記憶があるから、学生時代にモーツァルトを聴いてたのである。
モーツァルトの音楽をよく「天国的」と評するけど、僕も全くそんな気分だった。若い時分に見たり聴いたり読んだりして、これは人類史上の天才だと思ったのはモーツァルトだけだ。お金の問題で買えるレコードは限られるけど、それでもずいぶん持ってた。割と何でも聴く方だけど、一番好きなのは間違いなくモーツァルトだった。年をとってもずっと聴くもんだと思っていた。まさかあの天国的な澄み渡った明るさより、バッハの方がいいと思う時期が来るとは思わなかった。
いろいろ聞いた中で、好きなのはコンチェルト(協奏曲)が多い。交響曲が嫌いなわけじゃないけど、長くて聴く方も力がいるからあまり聴かない。オペラも素晴らしいし、新国立劇場に見に行ったこともあるけど、モーツァルトに限らず一枚もCDを持ってない。(レコードやDVDも。)これも長くて高いから。ということで、聴くのはほとんど協奏曲。素晴らしいのはいくつもあるが、中でもクラリネット協奏曲とクラリネット五重奏曲が圧倒的に素晴らしいと思っている。
それもレオポルド・ウラッハ(1902~1956)のもの。オーストリアのクラリネット奏者で、ウィーン国立歌劇場とウィーンフィルの首席奏者を務めた。54歳で亡くなっているが、モノラルで残されたウラッハの音色の素晴らしさは一頭抜けていると思う。全部聴いたわけじゃないけど、ウラッハ盤を聴いたらもうそれでいいという気分になる。クラリネット協奏曲は1791年に書かれたもので、モーツァルト最後の協奏曲。クラリネット五重奏曲は1789年に書かれた。
甲乙つけがたい名曲だが、若いころは圧倒的にクラリネット協奏曲の方が大好きだった。とにかく美しくて、心が晴れ晴れとする。その開放感が素晴らしい。しかし、だんだんもう少し憂愁の趣が欲しいと思うようになった。五重奏曲の方がいいぞと思うようになった。今じゃ、聴くのはクラリネット五重奏曲ばかりである。年とると変わるのである。クラリネットという楽器はモーツァルト時代には、ようやくオーケストラに入るようになった新しい楽器だった。どっちも友人のアントン・シュタードラーのために作曲されたもので、クラリネットの魅力を見事に引き出している。
クラリネット以外では、フルート協奏曲、フルートとハープのための協奏曲、ヴァイオリン協奏曲、ファゴット協奏曲、ホルン協奏曲など多くの協奏曲を書いている。もちろん、27番まであるピアノ協奏曲を忘れてはいけない。ピアノ協奏曲は明るいもの、暗いものが分かれているから、どれが好きかで心が揺れる。しかし、次第に最後の27番がいいなと思うようになった。モーツァルトには伝説的な話がいっぱいあるが、僕はあまり関心がなく曲だけあれば十分だ。また「レクイエム」も素晴らしい。モーツァルトは僕などがいくら書いても仕方ないのでもう止める。