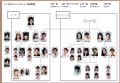ちょうど一週間前に天地真理を見に行ったばかりだが、今日は竹下景子の舞台を見てきた。竹下景子(1953~)も70年代に大人気だった人で、当時「お嫁さんにしたい女優№1」と呼ばれていた。自分の結婚相手ではなく、自分の息子の結婚相手に望むという、ホントの「嫁」である。今ではセクハラだろう。舞台女優のイメージは薄いかもしれないが、昔から商業演劇ばかりでなく小劇場にもずいぶん出て来た。黒木和雄監督『祭りの準備』(1975)の影響で、僕の中では70年代の想い出が残っている。

何も竹下景子だから見たのではなく、作者の鴻上尚志(こうかみ・しょうじ)にも関心があるが、それよりもシニア料金があったから見たのである。映画館、美術館にはシニア設定があるのに、演劇にはほとんどない(ユース割りはあるのに)。マチネ(昼)で席が空いてるなら、演劇にもシニア割りが欲しいと思っていたら、この公演にはあったのである。サードステージ『アカシアの雨が降る時』である。(新国立劇場小劇場。)題名にも心引かれた。僕は関口宏の司会ぶりが批判されると、「アカシアの雨がやむとき」が脳内に鳴り響くのである。(何でという人向けの説明は書かない。)
 (左から鈴木福、竹下景子、松村武)
(左から鈴木福、竹下景子、松村武)
舞台には3人しか出て来ない。(声だけ出る人はいるけど。)孫(鈴木福)が祖母(桜庭香寿美=竹下景子)の家を訪ねると、玄関に倒れていた。あわてて救急車を呼ぶと、医者から一時的な失神だと言われる。孫の両親は離婚していて、母とも息子とも疎遠だった父親とは数年ぶりに病院で会う。そして意識が目覚めると、祖母は自分は20歳の学生だと言い張り、孫は自分の恋人で、まだ子どもがいるはずはなく父親は知らない人だと言う。医者からは妄想を否定してはいけないと言われ、二人は「香寿美ちゃん」と呼ぶことになる。この祖母が自分は「村雨橋」に行かなくちゃと言い出したのである。
「村雨橋」(むらさめばし)は横浜市神奈川区にある橋で、1972年8月5日、相模原市の米軍施設から横浜港に向かう戦車を市民が取り囲んで止めた現場である。ベトナム戦争に加担してはならないと考える「ただの市民」が集まって座り込んだ。当時の飛鳥田横浜市長が、車両制限令で橋を通行できる重量が決められており、戦車を積載したトレーラーは重量が超過するとして通行を認めなかったのである。香寿美はノンポリ学生だったけど、心の底で何かしなければと思っていた。今こそ行かなくちゃと二人を誘う。エッと驚くと、あなたはベトナム戦争をどう思っているの?と問い詰めてくる。
これは同じ鴻上尚志が原案・脚本を担当した2007年の『僕たちの好きだった革命』の姉妹編というか、逆ヴァージョンである。あの舞台は中村雅俊が主演した抱腹絶倒の傑作コメディだった。高校闘争のさなかに石に打たれて意識を失ったまま30年、1999年になって突如意識が戻り、かつての革命意識を持ちながら47歳で目覚めた男が高校に戻ってきた…。男と現役高校生のギャップが面白かったのだが、その舞台から早くも10数年。相模原戦車闘争からすでに半世紀である。あの時代に20歳だった学生が意識不明で今蘇っても古稀を越えている。今さら高校や大学に復学するという設定が成り立たないほど時間が経ってしまった。
ということで、祖母の意識が昔に戻るという設定にせざるを得ない。だが、そうなると孫世代はすでに戦車闘争どころか、ベトナム戦争も知らない。香寿美は高野悦子の『二十歳の原点』を読みたいと言い出す。岩波ホール支配人じゃなく、立命館大学学生だった人である。むろん孫は知らない。実際に鈴木福君はこの舞台に立つまで、戦車闘争も『二十歳の原点』も知らなかったんじゃないかと思う。今はスマホがあるから、舞台上でも孫はあわててベトナム戦争って何だっけと検索している。それだけじゃ観客に見えないから、舞台上にはスクリーンがあって『二十歳の原点』が流れるし、当時や今の村雨橋の映像が映し出される。
 (出演者と鴻上尚志)
(出演者と鴻上尚志)
そこがどうしても説明的になってしまい、演劇的感興を削ぐのである。設定上、今じゃ観客も判らないことが多く、セリフだけでは伝えきれない。やむを得ないけれど、残念な点である。話はそこから、祖母が秘密のミッションに乗り出し、それは脱走米兵を受け入れるということで(知ってる人なら予想が出来る)、だけどすぐに頼める若いアメリカ人などいないから、父親が金髪のカツラを被って脱走兵に扮する。これは予想外で爆笑。祖母(20歳の香寿美)は歌が好きで時々歌うシーンがある。最初は「遠い世界に」で孫は何て曲と聞く。次は元気が出る曲として香寿美が選んだ「友よ」で、竹下景子と鈴木福が舞台で歌ってる。
そこに親子や夫婦の葛藤、施設に入れるべきかなどの問題が出て来る。そのうち祖母は脳梗塞を起こし、やがて肺炎を起こして亡くなる。実際の竹下景子の年齢を考えると、これは若すぎる。確かにそういう人もいるけれど、日本人女性の平均寿命を考えると、今や85歳超じゃないとおかしい。母を亡くすというのは、最近自分の身に起こったばかりで、その意味では身につまされる劇だが、自分の場合は95歳だから想い出は戦争前後である。だけど、まあ竹下景子が「遠い世界に」や「友よ」を歌うのを聞けたんだから、それでいいじゃないかと思った。
この芝居は本来、2021年に上演されるものだった。その時は竹下景子ではなく、久野綾希子が演じていたが、コロナ禍で中断せざるを得なかった。その間に久野が2022年8月に亡くなってしまい、今回キャストを変えて再演となったという。父親役の松村武(1970~)は「劇団カムカムミニキーナ」を主宰する作家兼役者で、この劇では鬱陶しい父親であり、かつ仕事でトラブっているという難役を見事に演じている。スマホが鳴るたびに、それは仕事のトラブル関係がほとんどなので、見ているこちらもビクッとしてしまう。鈴木福は小劇場系の舞台出演は少なく、こういう場で出ずっぱりの体験は大切だろう。この後何公演か地方を回るけど、東京は今日が最後。

何も竹下景子だから見たのではなく、作者の鴻上尚志(こうかみ・しょうじ)にも関心があるが、それよりもシニア料金があったから見たのである。映画館、美術館にはシニア設定があるのに、演劇にはほとんどない(ユース割りはあるのに)。マチネ(昼)で席が空いてるなら、演劇にもシニア割りが欲しいと思っていたら、この公演にはあったのである。サードステージ『アカシアの雨が降る時』である。(新国立劇場小劇場。)題名にも心引かれた。僕は関口宏の司会ぶりが批判されると、「アカシアの雨がやむとき」が脳内に鳴り響くのである。(何でという人向けの説明は書かない。)
 (左から鈴木福、竹下景子、松村武)
(左から鈴木福、竹下景子、松村武)舞台には3人しか出て来ない。(声だけ出る人はいるけど。)孫(鈴木福)が祖母(桜庭香寿美=竹下景子)の家を訪ねると、玄関に倒れていた。あわてて救急車を呼ぶと、医者から一時的な失神だと言われる。孫の両親は離婚していて、母とも息子とも疎遠だった父親とは数年ぶりに病院で会う。そして意識が目覚めると、祖母は自分は20歳の学生だと言い張り、孫は自分の恋人で、まだ子どもがいるはずはなく父親は知らない人だと言う。医者からは妄想を否定してはいけないと言われ、二人は「香寿美ちゃん」と呼ぶことになる。この祖母が自分は「村雨橋」に行かなくちゃと言い出したのである。
「村雨橋」(むらさめばし)は横浜市神奈川区にある橋で、1972年8月5日、相模原市の米軍施設から横浜港に向かう戦車を市民が取り囲んで止めた現場である。ベトナム戦争に加担してはならないと考える「ただの市民」が集まって座り込んだ。当時の飛鳥田横浜市長が、車両制限令で橋を通行できる重量が決められており、戦車を積載したトレーラーは重量が超過するとして通行を認めなかったのである。香寿美はノンポリ学生だったけど、心の底で何かしなければと思っていた。今こそ行かなくちゃと二人を誘う。エッと驚くと、あなたはベトナム戦争をどう思っているの?と問い詰めてくる。
これは同じ鴻上尚志が原案・脚本を担当した2007年の『僕たちの好きだった革命』の姉妹編というか、逆ヴァージョンである。あの舞台は中村雅俊が主演した抱腹絶倒の傑作コメディだった。高校闘争のさなかに石に打たれて意識を失ったまま30年、1999年になって突如意識が戻り、かつての革命意識を持ちながら47歳で目覚めた男が高校に戻ってきた…。男と現役高校生のギャップが面白かったのだが、その舞台から早くも10数年。相模原戦車闘争からすでに半世紀である。あの時代に20歳だった学生が意識不明で今蘇っても古稀を越えている。今さら高校や大学に復学するという設定が成り立たないほど時間が経ってしまった。
ということで、祖母の意識が昔に戻るという設定にせざるを得ない。だが、そうなると孫世代はすでに戦車闘争どころか、ベトナム戦争も知らない。香寿美は高野悦子の『二十歳の原点』を読みたいと言い出す。岩波ホール支配人じゃなく、立命館大学学生だった人である。むろん孫は知らない。実際に鈴木福君はこの舞台に立つまで、戦車闘争も『二十歳の原点』も知らなかったんじゃないかと思う。今はスマホがあるから、舞台上でも孫はあわててベトナム戦争って何だっけと検索している。それだけじゃ観客に見えないから、舞台上にはスクリーンがあって『二十歳の原点』が流れるし、当時や今の村雨橋の映像が映し出される。
 (出演者と鴻上尚志)
(出演者と鴻上尚志)そこがどうしても説明的になってしまい、演劇的感興を削ぐのである。設定上、今じゃ観客も判らないことが多く、セリフだけでは伝えきれない。やむを得ないけれど、残念な点である。話はそこから、祖母が秘密のミッションに乗り出し、それは脱走米兵を受け入れるということで(知ってる人なら予想が出来る)、だけどすぐに頼める若いアメリカ人などいないから、父親が金髪のカツラを被って脱走兵に扮する。これは予想外で爆笑。祖母(20歳の香寿美)は歌が好きで時々歌うシーンがある。最初は「遠い世界に」で孫は何て曲と聞く。次は元気が出る曲として香寿美が選んだ「友よ」で、竹下景子と鈴木福が舞台で歌ってる。
そこに親子や夫婦の葛藤、施設に入れるべきかなどの問題が出て来る。そのうち祖母は脳梗塞を起こし、やがて肺炎を起こして亡くなる。実際の竹下景子の年齢を考えると、これは若すぎる。確かにそういう人もいるけれど、日本人女性の平均寿命を考えると、今や85歳超じゃないとおかしい。母を亡くすというのは、最近自分の身に起こったばかりで、その意味では身につまされる劇だが、自分の場合は95歳だから想い出は戦争前後である。だけど、まあ竹下景子が「遠い世界に」や「友よ」を歌うのを聞けたんだから、それでいいじゃないかと思った。
この芝居は本来、2021年に上演されるものだった。その時は竹下景子ではなく、久野綾希子が演じていたが、コロナ禍で中断せざるを得なかった。その間に久野が2022年8月に亡くなってしまい、今回キャストを変えて再演となったという。父親役の松村武(1970~)は「劇団カムカムミニキーナ」を主宰する作家兼役者で、この劇では鬱陶しい父親であり、かつ仕事でトラブっているという難役を見事に演じている。スマホが鳴るたびに、それは仕事のトラブル関係がほとんどなので、見ているこちらもビクッとしてしまう。鈴木福は小劇場系の舞台出演は少なく、こういう場で出ずっぱりの体験は大切だろう。この後何公演か地方を回るけど、東京は今日が最後。