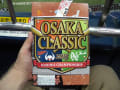今年のゴールデンウィークも終了。オリックス・バファローズはイーグルス、ホークス、ライオンズと対戦して結局3勝6敗。ホークス戦ではあと一歩のところで逆転負けを食らったかと思えば、ライオンズ戦は3戦とも力の差を見せつけられた敗戦で、借金も再び二けたに膨れ上がった。もう、どうなることやら・・・。
西国巡りをする中で「諸願成就」ということを行っているのだが、ここに「オリックス・バファローズの勝利」というのを加えてお参りするとするかな・・・。

 さて、粉河からJR和歌山線で和歌山まで出て、きのくに線(紀勢線)の御坊行きに乗り継ぐ。二つ目が紀三井寺駅である。ここも、西国巡りの2回目の訪問である。目指す紀三井寺は駅から歩いて5分ほどのところにある。桜の名所としては名高いところだが、連休中とはいえそれほどの混雑はない。同じ和歌山でも行くとすればもっと南へ向かう人が多いのだろう。
さて、粉河からJR和歌山線で和歌山まで出て、きのくに線(紀勢線)の御坊行きに乗り継ぐ。二つ目が紀三井寺駅である。ここも、西国巡りの2回目の訪問である。目指す紀三井寺は駅から歩いて5分ほどのところにある。桜の名所としては名高いところだが、連休中とはいえそれほどの混雑はない。同じ和歌山でも行くとすればもっと南へ向かう人が多いのだろう。

 楼門から231段の石段がある。ここまであちらこちらの札所を巡る中で歩いたのに比べれば、231段の石段くらいはさほどのものではない。ただこの「結縁坂」・・・その昔、紀伊国屋文左衛門の結婚と出世のきっかけとなった、縁結びのエピソードが残る石段であるが、私も昨年上ったがその後何かそいう話があったわけではない。まあ、1回上ったくらいでそのようなご利益が受けられるはずもなく、いろんな意味での信心を持たなければならないところであるが・・・。
楼門から231段の石段がある。ここまであちらこちらの札所を巡る中で歩いたのに比べれば、231段の石段くらいはさほどのものではない。ただこの「結縁坂」・・・その昔、紀伊国屋文左衛門の結婚と出世のきっかけとなった、縁結びのエピソードが残る石段であるが、私も昨年上ったがその後何かそいう話があったわけではない。まあ、1回上ったくらいでそのようなご利益が受けられるはずもなく、いろんな意味での信心を持たなければならないところであるが・・・。

 本堂に出る。ここ紀三井寺は「救世観音宗(ぐぜかんのんしゅう)」という、独立した宗派の総本山としての一面も持つ。元々は真言宗の山階派というのに属していたが、1948年に先代の住職が救世観音宗を開創した。そういうことはあるが、宗派を問わず古くから多くの人の心の拠りどころであったことには違いない。西国の札所は真言宗、天台宗、さまざまな宗派に属してはいるが、だからと言って寺の造りにそれほどの違いがあるものでなく、同じ宗派でもご本尊が違う、逆に別の宗派でも同じご本尊を祀るというところもある。巡礼する人も果たしてどのくらい意識しているのかなと思う。
本堂に出る。ここ紀三井寺は「救世観音宗(ぐぜかんのんしゅう)」という、独立した宗派の総本山としての一面も持つ。元々は真言宗の山階派というのに属していたが、1948年に先代の住職が救世観音宗を開創した。そういうことはあるが、宗派を問わず古くから多くの人の心の拠りどころであったことには違いない。西国の札所は真言宗、天台宗、さまざまな宗派に属してはいるが、だからと言って寺の造りにそれほどの違いがあるものでなく、同じ宗派でもご本尊が違う、逆に別の宗派でも同じご本尊を祀るというところもある。巡礼する人も果たしてどのくらい意識しているのかなと思う。
外陣にてこの日二回目のお勤めを行う。

 そして朱印を受ける。朱印帳のほうは重ね印ということで、納経軸の最上段にもいただく。これで最上段の4ヶ所全てに朱印と菊の御紋が入った。和歌山の3ヶ所には2回来ることにはなったが、これで華厳寺のある岐阜県以外の近畿2府4県のうち、最初にコンプリートした県となった。西国巡りも折り返しに来て、少しずつ形になってくるのを感じる。
そして朱印を受ける。朱印帳のほうは重ね印ということで、納経軸の最上段にもいただく。これで最上段の4ヶ所全てに朱印と菊の御紋が入った。和歌山の3ヶ所には2回来ることにはなったが、これで華厳寺のある岐阜県以外の近畿2府4県のうち、最初にコンプリートした県となった。西国巡りも折り返しに来て、少しずつ形になってくるのを感じる。
 本堂の後は、高さが25mある大千手十一面観音像が安置される仏殿に向かう。2008年に落慶した新しい像だが、今ではこちらが紀三井寺のシンボルになっているかのようである。本尊の十一面観音が秘仏となっていることもあるだろう。「フラッシュなしなら写真を撮っていただいて結構ですよ」という案内の僧侶の言葉に、スマホやタブレットを向ける人も多い。
本堂の後は、高さが25mある大千手十一面観音像が安置される仏殿に向かう。2008年に落慶した新しい像だが、今ではこちらが紀三井寺のシンボルになっているかのようである。本尊の十一面観音が秘仏となっていることもあるだろう。「フラッシュなしなら写真を撮っていただいて結構ですよ」という案内の僧侶の言葉に、スマホやタブレットを向ける人も多い。

 100円を納めればこの仏殿の3階の展望台に上がることができる。ちょうど観音像の顔の高さにあり、ご対面である。観音像の視線のちょうど先に本堂がある。
100円を納めればこの仏殿の3階の展望台に上がることができる。ちょうど観音像の顔の高さにあり、ご対面である。観音像の視線のちょうど先に本堂がある。


 天気もよく、風も心地よく吹いている。和歌山市街から和歌の浦、マリーナシティはもちろん、その先の景色もくっきり見える。海の色が明るい。春を通り越して初夏の気分である。
天気もよく、風も心地よく吹いている。和歌山市街から和歌の浦、マリーナシティはもちろん、その先の景色もくっきり見える。海の色が明るい。春を通り越して初夏の気分である。
さて、この景色を眺めながら、次の行き先を決めるくじ引きとサイコロである。華厳寺は最後に行くとして、札所をエリアごとに分けたグループも残り9つ。
1.近江(長命寺、観音正寺)
2.飛鳥(岡寺)
3.阪急京都線(善峯寺、総持寺)
4.姫路(圓教寺)
5.宇治(三室戸寺)
6.京都東山(今熊野観音寺、清水寺、六波羅蜜寺)
ちなみに残りのエリアは、山科醍醐(元慶寺、上醍醐)、箕面宝塚(勝尾寺、中山寺)、丹後(成相寺、松尾寺)である。和歌山はこれで完了したが、まだ姫路、丹後、近江と、端のエリアは残っている。ここらで姫路、近江といった遠いところも押さえておきたい。
そして出た目は・・・「3」。うーん、選択肢の中ではもっとも地味で、寺としてもマイナーなイメージのところである(あくまで、私の主観として・・・)。総持寺は阪急の駅名にもなっているから名前は知っているにしても、善峯寺は、西国巡りの中で初めて知った名前である。いずれももちろん訪れるのは初めてだが、普段なかなか行くことのない西京から茨木というコースも、道中何か面白いものがあるかもしれない。
ちょうど昼近くなったところでこの日の巡拝は終了。さて、和歌山に来た午後の時間をどう過ごすか・・・・。
西国巡りをする中で「諸願成就」ということを行っているのだが、ここに「オリックス・バファローズの勝利」というのを加えてお参りするとするかな・・・。

 さて、粉河からJR和歌山線で和歌山まで出て、きのくに線(紀勢線)の御坊行きに乗り継ぐ。二つ目が紀三井寺駅である。ここも、西国巡りの2回目の訪問である。目指す紀三井寺は駅から歩いて5分ほどのところにある。桜の名所としては名高いところだが、連休中とはいえそれほどの混雑はない。同じ和歌山でも行くとすればもっと南へ向かう人が多いのだろう。
さて、粉河からJR和歌山線で和歌山まで出て、きのくに線(紀勢線)の御坊行きに乗り継ぐ。二つ目が紀三井寺駅である。ここも、西国巡りの2回目の訪問である。目指す紀三井寺は駅から歩いて5分ほどのところにある。桜の名所としては名高いところだが、連休中とはいえそれほどの混雑はない。同じ和歌山でも行くとすればもっと南へ向かう人が多いのだろう。
 楼門から231段の石段がある。ここまであちらこちらの札所を巡る中で歩いたのに比べれば、231段の石段くらいはさほどのものではない。ただこの「結縁坂」・・・その昔、紀伊国屋文左衛門の結婚と出世のきっかけとなった、縁結びのエピソードが残る石段であるが、私も昨年上ったがその後何かそいう話があったわけではない。まあ、1回上ったくらいでそのようなご利益が受けられるはずもなく、いろんな意味での信心を持たなければならないところであるが・・・。
楼門から231段の石段がある。ここまであちらこちらの札所を巡る中で歩いたのに比べれば、231段の石段くらいはさほどのものではない。ただこの「結縁坂」・・・その昔、紀伊国屋文左衛門の結婚と出世のきっかけとなった、縁結びのエピソードが残る石段であるが、私も昨年上ったがその後何かそいう話があったわけではない。まあ、1回上ったくらいでそのようなご利益が受けられるはずもなく、いろんな意味での信心を持たなければならないところであるが・・・。
 本堂に出る。ここ紀三井寺は「救世観音宗(ぐぜかんのんしゅう)」という、独立した宗派の総本山としての一面も持つ。元々は真言宗の山階派というのに属していたが、1948年に先代の住職が救世観音宗を開創した。そういうことはあるが、宗派を問わず古くから多くの人の心の拠りどころであったことには違いない。西国の札所は真言宗、天台宗、さまざまな宗派に属してはいるが、だからと言って寺の造りにそれほどの違いがあるものでなく、同じ宗派でもご本尊が違う、逆に別の宗派でも同じご本尊を祀るというところもある。巡礼する人も果たしてどのくらい意識しているのかなと思う。
本堂に出る。ここ紀三井寺は「救世観音宗(ぐぜかんのんしゅう)」という、独立した宗派の総本山としての一面も持つ。元々は真言宗の山階派というのに属していたが、1948年に先代の住職が救世観音宗を開創した。そういうことはあるが、宗派を問わず古くから多くの人の心の拠りどころであったことには違いない。西国の札所は真言宗、天台宗、さまざまな宗派に属してはいるが、だからと言って寺の造りにそれほどの違いがあるものでなく、同じ宗派でもご本尊が違う、逆に別の宗派でも同じご本尊を祀るというところもある。巡礼する人も果たしてどのくらい意識しているのかなと思う。外陣にてこの日二回目のお勤めを行う。

 そして朱印を受ける。朱印帳のほうは重ね印ということで、納経軸の最上段にもいただく。これで最上段の4ヶ所全てに朱印と菊の御紋が入った。和歌山の3ヶ所には2回来ることにはなったが、これで華厳寺のある岐阜県以外の近畿2府4県のうち、最初にコンプリートした県となった。西国巡りも折り返しに来て、少しずつ形になってくるのを感じる。
そして朱印を受ける。朱印帳のほうは重ね印ということで、納経軸の最上段にもいただく。これで最上段の4ヶ所全てに朱印と菊の御紋が入った。和歌山の3ヶ所には2回来ることにはなったが、これで華厳寺のある岐阜県以外の近畿2府4県のうち、最初にコンプリートした県となった。西国巡りも折り返しに来て、少しずつ形になってくるのを感じる。 本堂の後は、高さが25mある大千手十一面観音像が安置される仏殿に向かう。2008年に落慶した新しい像だが、今ではこちらが紀三井寺のシンボルになっているかのようである。本尊の十一面観音が秘仏となっていることもあるだろう。「フラッシュなしなら写真を撮っていただいて結構ですよ」という案内の僧侶の言葉に、スマホやタブレットを向ける人も多い。
本堂の後は、高さが25mある大千手十一面観音像が安置される仏殿に向かう。2008年に落慶した新しい像だが、今ではこちらが紀三井寺のシンボルになっているかのようである。本尊の十一面観音が秘仏となっていることもあるだろう。「フラッシュなしなら写真を撮っていただいて結構ですよ」という案内の僧侶の言葉に、スマホやタブレットを向ける人も多い。
 100円を納めればこの仏殿の3階の展望台に上がることができる。ちょうど観音像の顔の高さにあり、ご対面である。観音像の視線のちょうど先に本堂がある。
100円を納めればこの仏殿の3階の展望台に上がることができる。ちょうど観音像の顔の高さにあり、ご対面である。観音像の視線のちょうど先に本堂がある。

 天気もよく、風も心地よく吹いている。和歌山市街から和歌の浦、マリーナシティはもちろん、その先の景色もくっきり見える。海の色が明るい。春を通り越して初夏の気分である。
天気もよく、風も心地よく吹いている。和歌山市街から和歌の浦、マリーナシティはもちろん、その先の景色もくっきり見える。海の色が明るい。春を通り越して初夏の気分である。さて、この景色を眺めながら、次の行き先を決めるくじ引きとサイコロである。華厳寺は最後に行くとして、札所をエリアごとに分けたグループも残り9つ。
1.近江(長命寺、観音正寺)
2.飛鳥(岡寺)
3.阪急京都線(善峯寺、総持寺)
4.姫路(圓教寺)
5.宇治(三室戸寺)
6.京都東山(今熊野観音寺、清水寺、六波羅蜜寺)
ちなみに残りのエリアは、山科醍醐(元慶寺、上醍醐)、箕面宝塚(勝尾寺、中山寺)、丹後(成相寺、松尾寺)である。和歌山はこれで完了したが、まだ姫路、丹後、近江と、端のエリアは残っている。ここらで姫路、近江といった遠いところも押さえておきたい。
そして出た目は・・・「3」。うーん、選択肢の中ではもっとも地味で、寺としてもマイナーなイメージのところである(あくまで、私の主観として・・・)。総持寺は阪急の駅名にもなっているから名前は知っているにしても、善峯寺は、西国巡りの中で初めて知った名前である。いずれももちろん訪れるのは初めてだが、普段なかなか行くことのない西京から茨木というコースも、道中何か面白いものがあるかもしれない。
ちょうど昼近くなったところでこの日の巡拝は終了。さて、和歌山に来た午後の時間をどう過ごすか・・・・。