室伏きみ子さん編著「科学と社会が出会う場所 サイエンスカフェにようこそ④」を読みました。
サイエンスカフェは、神田神保町にある喫茶室「サロンド富山房フォリオ」で毎月第三金曜日の午後6時半から、コーディネーターの室伏きみ子さんが、最先端の研究に携わっている科学者を招いて、お茶を飲みながら気軽に科学についておしゃべりするという集いです。
この本は、2008年6月〜2010年2月に開催された内容を収録したものです。
「科学と社会が出会う場所」という副題にあるように、幅広いテーマについて話されています。
私が興味を惹かれたのは、五島綾子さんが話されたテーマ「ブレークスルーの科学は予測できない」ですね。
ナノテクノロジーを例に、日米のナノテク戦略を比較していますが、興味深いですね。
米国では、科学者とSF作家が市民を巻き込んでいき、真実とサイエンス・フィクションの間で揺れ動くブームになっていくのですが、日本では、実利をすぐさま求め、ナノ商品という目先の経済効果を期待するブームに変質していきました。
この辺の違いが実に面白い。
米国は、何十年という長期にわたって予算計画を立て、基礎研究を重視した予算、人材育成にも予算を多く配分しています。
これに対して日本は、省庁縦割りの弊害で、単年度予算で、人材育成も不十分です。
新しい材料が出来たときは、当然リスクがあるので(ナノテクの場合は、環境、健康への影響)、そのリスクへの配慮が必要です。
米国では、ナノテクが市民に受け入れられるように、リスクに対しても大きく予算を投入して社会受容を図っていますが、日本では、リスクマネージメントは企業のボランティア頼りというお粗末な状況です。
米国では、新技術に対する負の議論も活発に行われていますが、日本では、ほとんど行われていません。
「顔を見せて、責任をもって市民に説明する科学者が少ない」というのが日本の科学者の問題ですね。
このテーマ以外にも興味のあるテーマが多く収録されています。
知的好奇心を満足させてくれる本です。
ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。
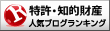 特許・知的財産 ブログランキングへ
特許・知的財産 ブログランキングへ
 弁理士 ブログランキングへ
弁理士 ブログランキングへ
サイエンスカフェは、神田神保町にある喫茶室「サロンド富山房フォリオ」で毎月第三金曜日の午後6時半から、コーディネーターの室伏きみ子さんが、最先端の研究に携わっている科学者を招いて、お茶を飲みながら気軽に科学についておしゃべりするという集いです。
この本は、2008年6月〜2010年2月に開催された内容を収録したものです。
「科学と社会が出会う場所」という副題にあるように、幅広いテーマについて話されています。
私が興味を惹かれたのは、五島綾子さんが話されたテーマ「ブレークスルーの科学は予測できない」ですね。
ナノテクノロジーを例に、日米のナノテク戦略を比較していますが、興味深いですね。
米国では、科学者とSF作家が市民を巻き込んでいき、真実とサイエンス・フィクションの間で揺れ動くブームになっていくのですが、日本では、実利をすぐさま求め、ナノ商品という目先の経済効果を期待するブームに変質していきました。
この辺の違いが実に面白い。
米国は、何十年という長期にわたって予算計画を立て、基礎研究を重視した予算、人材育成にも予算を多く配分しています。
これに対して日本は、省庁縦割りの弊害で、単年度予算で、人材育成も不十分です。
新しい材料が出来たときは、当然リスクがあるので(ナノテクの場合は、環境、健康への影響)、そのリスクへの配慮が必要です。
米国では、ナノテクが市民に受け入れられるように、リスクに対しても大きく予算を投入して社会受容を図っていますが、日本では、リスクマネージメントは企業のボランティア頼りというお粗末な状況です。
米国では、新技術に対する負の議論も活発に行われていますが、日本では、ほとんど行われていません。
「顔を見せて、責任をもって市民に説明する科学者が少ない」というのが日本の科学者の問題ですね。
このテーマ以外にも興味のあるテーマが多く収録されています。
知的好奇心を満足させてくれる本です。
ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。















