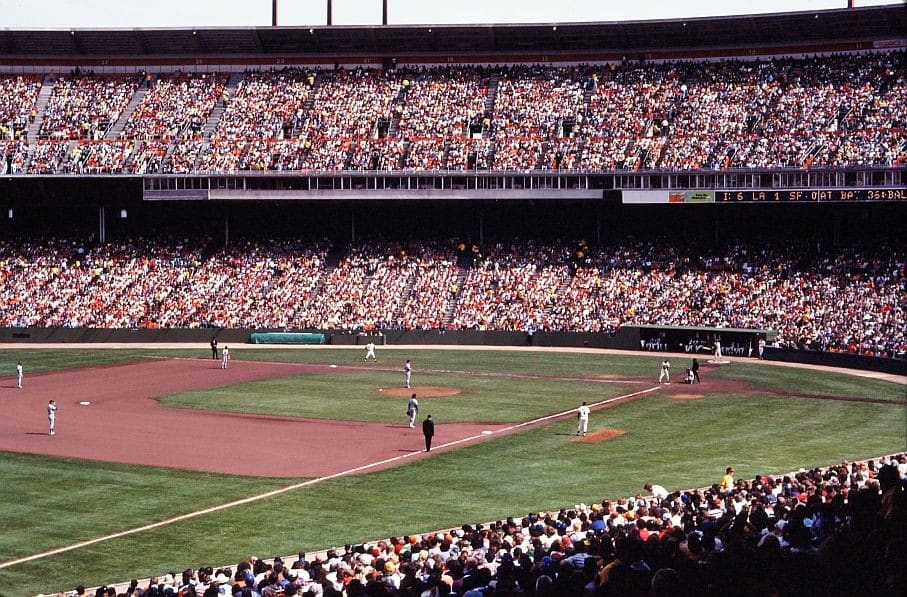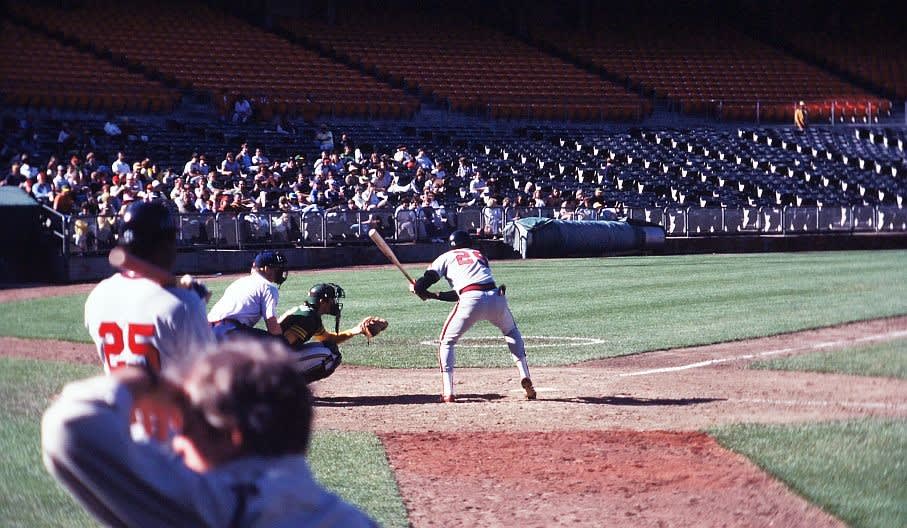今年10月で新幹線開業から60年となります。
開業時の新幹線車両といえば0系、丸っこい鼻のかわいらしい顔をしている車両でした。その0系は歴代の新幹線車両の中では一番の長寿の車両です。1964年に運行を開始し、最後は山陽新幹線として2008年11月まで定期運行していました。(※)
活躍の最後年である2008年の夏に、最後の雄姿を記録しようと思って出かけました。たしか新大阪に顔を出すのは2往復だったような記憶があります。効率よく走行写真を撮りたくて、西明石駅に出かけました。
開業時の新幹線車両といえば0系、丸っこい鼻のかわいらしい顔をしている車両でした。その0系は歴代の新幹線車両の中では一番の長寿の車両です。1964年に運行を開始し、最後は山陽新幹線として2008年11月まで定期運行していました。(※)
活躍の最後年である2008年の夏に、最後の雄姿を記録しようと思って出かけました。たしか新大阪に顔を出すのは2往復だったような記憶があります。効率よく走行写真を撮りたくて、西明石駅に出かけました。

朝7時25分頃の上りと8時20分頃の下りが0系での運用でした。


現在の山陽新幹線は、N700系(N700AやN700S含む)主体で、500系と700系がわずかに残るだけですが、2008年にはさまざまな新幹線車両が走っていました。
まずは100系。ちょっと尖った顔がお洒落にみえました。すでに4両及び6両の短編成だけが残っていました。色はグレーの車体に緑色の帯でした。

そして初代のぞみと言えば300系、鉄仮面のような顔でした。

次は新幹線車両の中では一番スマート、一番格好良いと大人気の500系。

そして、カモノハシのような顔の700系。この当時はノーマルの16両編成とレールスター用の8両編成が走っていました。


現在の主流のN700系、2007年7月から定期運用が開始された、当時としては新車両でした。

αSweet Digital+Minolta AF 75-300mmF4.5-5.6D
今では考えられないほどの車両バリエーションが豊富な時期でした。
参考文献
※:「特集:新幹線60年」『鉄道ファン 2024年10月号』交友社、2024年10月1日発行、pp.9-61
参考文献
※:「特集:新幹線60年」『鉄道ファン 2024年10月号』交友社、2024年10月1日発行、pp.9-61