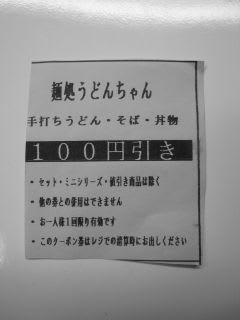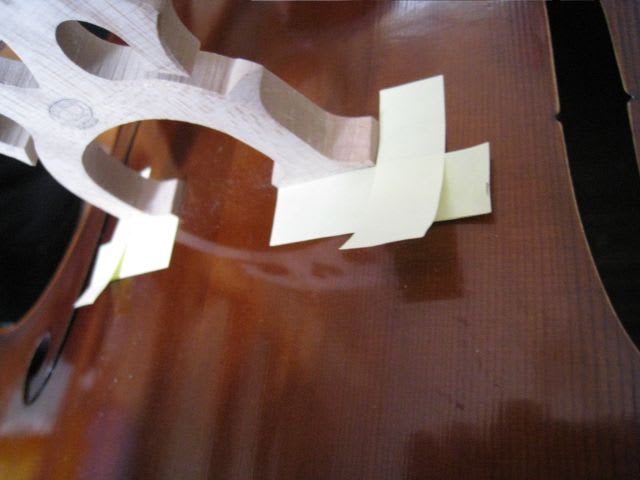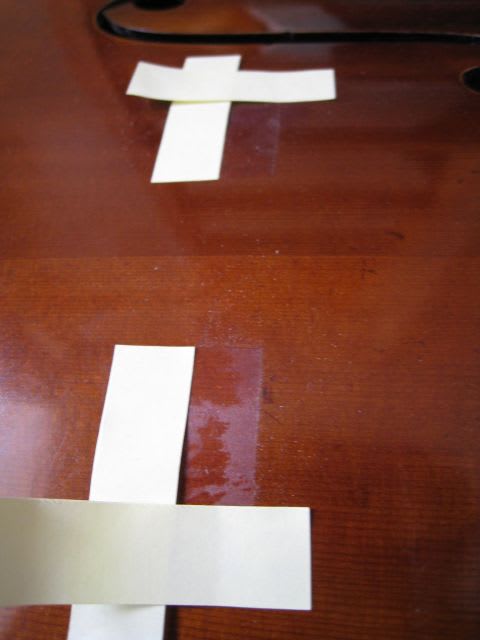モダンガール論, 斎藤美奈子, 文春文庫 さ-36-2, 2003年
・『女性の人権問題』にはこれっぽちも興味は無く、興味があったのは著者の綴る文章です。きっかけは、前出『働くことがイヤな人のための本』(中島義道)のあとがきでした。そのズバッ! と相手に切り込んで行く様は爽快です。
・テーマは日本の明治から現代までの女性史。「歴史は繰り返す」という主張を軸に論を展開する。
・思ったよりもおとなしい、というのが読んだ第一印象です。しかし、自分にとっては何の興味も無いテーマについて、面白く読ませてしまうのはすごいことだと思います。お気に入り著者に追加。今後に期待。
・「そうなのだ。女の子には出世の道が二つある。立派な職業人になることと、立派な家庭人になること。職業的な達成(労働市場で自分を高く売ること)と家庭的な幸福(結婚市場で自分を高く売ること)は、女性の場合、どっちも「出世」なのである。 したがって、女の子はいつも「二つの出世の道」の間で揺れてきた。」p.10
・「さて、それから今日までの100年間、女の子たちが二つの出世の道の間でどんなふうに右往左往してきたか。べつにいうと、自身の出世願望を充たすために、彼女たちがどれほど微笑ましくも涙ぐましい奮闘努力をしてきたか。その足跡をたどってみようというのが本書の主旨だ。」p.12
・「この本は、じつはあんまり正義の味方じゃない。この際、名前をつけておこう。欲望史観。うん、これがいい。」p.12
・「20世紀の望ましい女性像とは何だったか。行をかえて強調しちゃおう。 良妻賢母!」p.26
・「ここは断言してしまおう。日本の男子の近代は「立身出世」思想からはじまった。そして、男子に遅れること30年、女子の近代は「良妻賢母」思想とともにはじまったのだと。」p.29
・「主婦はいまとなっては「平凡」の代名詞である。しかし、かつては平凡どころかオシャレな生き方の最前線。やる気満々の女の子たちをして「主婦になりたい!」と夢みさせるに十分な、キラキラした女性像だったのだ。」p.60
・「市民レベルの生活が近代化、合理化、洋風化するのは20世紀以降、おもに大正時代だ。「文化」「家庭」「生活」「衛生」「健康」といった熟語も、みんなこのころ流行し、普及したことばである。」p.65
・「さあ、どうでしょう。新しい設備に新しい方法論。街には主婦を支援する情報やグッズがいっぱい。こんな時代に主婦をやっていたら、ワクワクしたと思いませんか。」p.70
・「頭脳労働中心の「職業婦人」と区別する意味で、女工のような肉体労働者は「労働婦人」とも呼ばれていた。」p.87
・「女工や女中は差別の対象だったのだ。職業に貴賎はある。女工や女中はまさに「賎」の代表選手。人々が彼女達を見る目は、ひどいものだった。ブスでバカで貧乏で行儀が悪くて身持ちが悪い。」p.101
・「農村婦人には産休もない。分娩の直前まで働いて、出産後も横になっていられるのは、たった一日、せいぜい二四時間であり、一週間以内には、七割の人が「通常どおりの労働」に復帰している。」p.146
・「・貞婦になるより恋に生きたい 私の家庭はこの通り、けれど夫婦の関係というものはこれでも無事に済んでゆくのです。私も貞婦の一人なのです。けれど私自身はそんな言葉はいただきたくない。それよりも、人間なら人間らしく真面目な恋に確(しつか)り抱かれていたい。たとえそれが恐ろしい罪悪の名の下に支配される行為でも……ふるえて偽りの日を送るよりも、形式はどうあろうとも心と心をふれ合うことのできる生活に這入りたい。(荒木郁「手紙」/『青鞜』明治45年4月号)」p.182
・「余談だが、戦前戦後の女性論客の中でも山川菊栄はとびぬけて頭がいい人、という印象がある。売春論争でコテンパンにされた伊藤野枝も気の毒だったが、晶子もらいてうも彼女の参戦を内心「いやだなあ」と思ったのではなかろうか。年下の才女が突然出てきて「あなたのは女性論です」「あなたのは母権論ね」なんて論評されたら、どう? いやな感じでしょう?」p.188
・「というか、職場の待遇差別から主婦の自立論まで、現代の私たちが直面しているような問題は、戦前に、ほとんどすべて先取りされていたのである。」p.189
・「戦争は変化を求めていた人々の気持ちをパッと明るくした。保守的で頑迷な昔風の女性ではなく、前向きで活発で近代的なセンスをもった女性ほど、戦争にはハマりやすいのですよ、みなさん。」p.197
・「けれども、女性の職場進出は、かえって促進されたのである。平時との大きなちがいは、徴兵によって激減した男子労働者の穴を埋めるために、それまでは「女にはふさわしくない」という理由で男が独占していた職域にまで、女性の職場が拡大したことである。」p.203
・「戦争には「階級差別」と「性差別」という平時における二つの差別を忘れさせる効用がある。国民皆働のかけ声と物資不足からくる耐久生活は「国民みな平等」の錯覚をおこさせる。さらに「男は戦争/女は労働」の戦時政策は、「女性の社会進出→婦人解放」の幻想をいだかせる。 戦争=銃後の暮らしは女性に「出世」を疑似体験させるのだ。」p.216
・「が、重要なのは、戦争がどんなに悲惨な結末を迎えたじゃなく、人々がどんな気分で戦争をスタートさせたか、だ。戦争責任とはそういうことじゃないんだろうか。」p.217
・「もう一度いおう。モダンガールは後ろ向きな姿勢や保守的な態度を嫌う。だからこそ、戦争に向かって進んでいく時代には、軍国婦人になりやすいのである。」p.218
・「高度成長期のかくれた変化のひとつに「恋愛結婚の増加」がある。明治大正の女の子たちもロマンチックな恋愛を夢みていたが、じっさいには九割がたがお見合いで結婚した。」p.244
・「アンノンのファッション革命によって、かつて「家事」や「花嫁修業」の領域にあったものは、ことごとくカジュアルな趣味・消費の対象にかわった。」p.268
・「アグネス論争、なつかしいですね。いちおう復習しておくと、「アグネス論争」とは、1987年から翌年にかけてつづけられた「育児と職業」をめぐる論争である。 それがいままでのどの論争ともちがっていたのは、有名無名、識者非識者、男女の別を問わず、ものすごーく多くの人が参戦したことである。」p.287
・「ここで私たちが思い出すのは、大正中期の母性保護論争である。アグネス・チャンの「子連れ出勤肯定論」は平塚らいてうの「母性保護は女の権利だ論」を、林真理子の「子連れ出勤は女の甘えだ論」は与謝野晶子の「母性保護は女の甘えだ論」を思わせる。」p.290
・「20世紀末、1990年代の女の子たちは白けていた。女子高生も女子大生もOLも白けていた。彼女たちはなんだってもっていた。流行の洋服も、山のような化粧品も、ブランドもののハンドバッグも、携帯電話も、ボーイフレンドもだ。家の中には立派な個室があり、家の外には時間をつぶせる遊び場がいくらでもあった。けれども、彼女たちは白けていた。 彼女たちが失ってしまったもの、それはおそらく「夢」である。」p.294
・「この100年を、大まかにまとめると、前半の50年は「出世のモデルケース」がショーウィンドウに飾られた時期、後半の50年はショーウィンドウのなかのモデルケースをみんながこぞって買い求めた時期、といえるのではないかと思う。戦後の50年は、戦前の50年の拡大版だったといってもいい。」p.296
・以下あとがきより。
・「自分でいうのもなんですが、この本を書く過程は、興奮と発見の連続でした。 当初、私が考えていたのは、ごく単純なことでした。 専業主婦と働く女性という二つの行き方は、どこでどう分岐したのだろう。」p.310
・「少なくとも、高校、大学に進学し、そこそこの企業に就職しさえすれば一生食いっぱぐれずにすむ「一億総中流の時代」は過去のものになった、と考えるべきでしょう。 さて、ではこんな時代の「ポストモダンガール」はなにを目指せばいいのでしょう。『モダンガール論』の結末は、読者にそこはかとなく不評でした。「先輩たちのことはわかったが、じゃあ私たちはどうすりゃいいの?」ってことですね。 正直にいうと、2000年の時点で、私にも明快なビジョンは見えていませんでした。」p.315
・「思えば、出世とは「見てくれ」にこだわる生き方です。考えようによっては「出世から下りる」ことで、かえって新しい展望が開けるかもしれない。」p.319
・「さしあたって私にできるアドバイスは、女性も男性も、一生続けられる仕事をぜひ見つけてください(それが見つかっている人は、ぜひいまの仕事を大切にしてください)、ということです。」p.320
・以下、解説(浅井良夫)より。因みにこの人物は、著者の大学(ゼミ)の恩師だそうです。
・「現存作家の文庫本の解説は、何のためにあるのでしょうか? そんなことは、今まで考えたこともなかったのですが、いくつかの文庫本の解説を開いてみて、要するに「お口直し」、たとえば、焼肉をたべたあとの、ペパーミント・ガムのようなものだと納得しました。「お口直し」ですから、作者と解説者の「取り合わせの妙」ないし「取り合わせの奇妙」がキー・ポイントです。」p.322
・「「進歩史観」、「抑圧史観」を排し、「この本はあまり正義の味方ではない」とうそぶく斎藤美奈子は、まさに、マンデヴィルの末裔です。」p.324
・「また、郁さんは、「ルーズソックスのコギャルは元気で明るい。(中略)この本の作者の斎藤美奈子さんも元気な女性の一人である。自分の考えを思ったとおりにまとめて、本を出版しているのだから」と、斎藤さんとコギャルの生き方の共通点をズバリ指摘しました。」p.328
・『女性の人権問題』にはこれっぽちも興味は無く、興味があったのは著者の綴る文章です。きっかけは、前出『働くことがイヤな人のための本』(中島義道)のあとがきでした。そのズバッ! と相手に切り込んで行く様は爽快です。
・テーマは日本の明治から現代までの女性史。「歴史は繰り返す」という主張を軸に論を展開する。
・思ったよりもおとなしい、というのが読んだ第一印象です。しかし、自分にとっては何の興味も無いテーマについて、面白く読ませてしまうのはすごいことだと思います。お気に入り著者に追加。今後に期待。
・「そうなのだ。女の子には出世の道が二つある。立派な職業人になることと、立派な家庭人になること。職業的な達成(労働市場で自分を高く売ること)と家庭的な幸福(結婚市場で自分を高く売ること)は、女性の場合、どっちも「出世」なのである。 したがって、女の子はいつも「二つの出世の道」の間で揺れてきた。」p.10
・「さて、それから今日までの100年間、女の子たちが二つの出世の道の間でどんなふうに右往左往してきたか。べつにいうと、自身の出世願望を充たすために、彼女たちがどれほど微笑ましくも涙ぐましい奮闘努力をしてきたか。その足跡をたどってみようというのが本書の主旨だ。」p.12
・「この本は、じつはあんまり正義の味方じゃない。この際、名前をつけておこう。欲望史観。うん、これがいい。」p.12
・「20世紀の望ましい女性像とは何だったか。行をかえて強調しちゃおう。 良妻賢母!」p.26
・「ここは断言してしまおう。日本の男子の近代は「立身出世」思想からはじまった。そして、男子に遅れること30年、女子の近代は「良妻賢母」思想とともにはじまったのだと。」p.29
・「主婦はいまとなっては「平凡」の代名詞である。しかし、かつては平凡どころかオシャレな生き方の最前線。やる気満々の女の子たちをして「主婦になりたい!」と夢みさせるに十分な、キラキラした女性像だったのだ。」p.60
・「市民レベルの生活が近代化、合理化、洋風化するのは20世紀以降、おもに大正時代だ。「文化」「家庭」「生活」「衛生」「健康」といった熟語も、みんなこのころ流行し、普及したことばである。」p.65
・「さあ、どうでしょう。新しい設備に新しい方法論。街には主婦を支援する情報やグッズがいっぱい。こんな時代に主婦をやっていたら、ワクワクしたと思いませんか。」p.70
・「頭脳労働中心の「職業婦人」と区別する意味で、女工のような肉体労働者は「労働婦人」とも呼ばれていた。」p.87
・「女工や女中は差別の対象だったのだ。職業に貴賎はある。女工や女中はまさに「賎」の代表選手。人々が彼女達を見る目は、ひどいものだった。ブスでバカで貧乏で行儀が悪くて身持ちが悪い。」p.101
・「農村婦人には産休もない。分娩の直前まで働いて、出産後も横になっていられるのは、たった一日、せいぜい二四時間であり、一週間以内には、七割の人が「通常どおりの労働」に復帰している。」p.146
・「・貞婦になるより恋に生きたい 私の家庭はこの通り、けれど夫婦の関係というものはこれでも無事に済んでゆくのです。私も貞婦の一人なのです。けれど私自身はそんな言葉はいただきたくない。それよりも、人間なら人間らしく真面目な恋に確(しつか)り抱かれていたい。たとえそれが恐ろしい罪悪の名の下に支配される行為でも……ふるえて偽りの日を送るよりも、形式はどうあろうとも心と心をふれ合うことのできる生活に這入りたい。(荒木郁「手紙」/『青鞜』明治45年4月号)」p.182
・「余談だが、戦前戦後の女性論客の中でも山川菊栄はとびぬけて頭がいい人、という印象がある。売春論争でコテンパンにされた伊藤野枝も気の毒だったが、晶子もらいてうも彼女の参戦を内心「いやだなあ」と思ったのではなかろうか。年下の才女が突然出てきて「あなたのは女性論です」「あなたのは母権論ね」なんて論評されたら、どう? いやな感じでしょう?」p.188
・「というか、職場の待遇差別から主婦の自立論まで、現代の私たちが直面しているような問題は、戦前に、ほとんどすべて先取りされていたのである。」p.189
・「戦争は変化を求めていた人々の気持ちをパッと明るくした。保守的で頑迷な昔風の女性ではなく、前向きで活発で近代的なセンスをもった女性ほど、戦争にはハマりやすいのですよ、みなさん。」p.197
・「けれども、女性の職場進出は、かえって促進されたのである。平時との大きなちがいは、徴兵によって激減した男子労働者の穴を埋めるために、それまでは「女にはふさわしくない」という理由で男が独占していた職域にまで、女性の職場が拡大したことである。」p.203
・「戦争には「階級差別」と「性差別」という平時における二つの差別を忘れさせる効用がある。国民皆働のかけ声と物資不足からくる耐久生活は「国民みな平等」の錯覚をおこさせる。さらに「男は戦争/女は労働」の戦時政策は、「女性の社会進出→婦人解放」の幻想をいだかせる。 戦争=銃後の暮らしは女性に「出世」を疑似体験させるのだ。」p.216
・「が、重要なのは、戦争がどんなに悲惨な結末を迎えたじゃなく、人々がどんな気分で戦争をスタートさせたか、だ。戦争責任とはそういうことじゃないんだろうか。」p.217
・「もう一度いおう。モダンガールは後ろ向きな姿勢や保守的な態度を嫌う。だからこそ、戦争に向かって進んでいく時代には、軍国婦人になりやすいのである。」p.218
・「高度成長期のかくれた変化のひとつに「恋愛結婚の増加」がある。明治大正の女の子たちもロマンチックな恋愛を夢みていたが、じっさいには九割がたがお見合いで結婚した。」p.244
・「アンノンのファッション革命によって、かつて「家事」や「花嫁修業」の領域にあったものは、ことごとくカジュアルな趣味・消費の対象にかわった。」p.268
・「アグネス論争、なつかしいですね。いちおう復習しておくと、「アグネス論争」とは、1987年から翌年にかけてつづけられた「育児と職業」をめぐる論争である。 それがいままでのどの論争ともちがっていたのは、有名無名、識者非識者、男女の別を問わず、ものすごーく多くの人が参戦したことである。」p.287
・「ここで私たちが思い出すのは、大正中期の母性保護論争である。アグネス・チャンの「子連れ出勤肯定論」は平塚らいてうの「母性保護は女の権利だ論」を、林真理子の「子連れ出勤は女の甘えだ論」は与謝野晶子の「母性保護は女の甘えだ論」を思わせる。」p.290
・「20世紀末、1990年代の女の子たちは白けていた。女子高生も女子大生もOLも白けていた。彼女たちはなんだってもっていた。流行の洋服も、山のような化粧品も、ブランドもののハンドバッグも、携帯電話も、ボーイフレンドもだ。家の中には立派な個室があり、家の外には時間をつぶせる遊び場がいくらでもあった。けれども、彼女たちは白けていた。 彼女たちが失ってしまったもの、それはおそらく「夢」である。」p.294
・「この100年を、大まかにまとめると、前半の50年は「出世のモデルケース」がショーウィンドウに飾られた時期、後半の50年はショーウィンドウのなかのモデルケースをみんながこぞって買い求めた時期、といえるのではないかと思う。戦後の50年は、戦前の50年の拡大版だったといってもいい。」p.296
・以下あとがきより。
・「自分でいうのもなんですが、この本を書く過程は、興奮と発見の連続でした。 当初、私が考えていたのは、ごく単純なことでした。 専業主婦と働く女性という二つの行き方は、どこでどう分岐したのだろう。」p.310
・「少なくとも、高校、大学に進学し、そこそこの企業に就職しさえすれば一生食いっぱぐれずにすむ「一億総中流の時代」は過去のものになった、と考えるべきでしょう。 さて、ではこんな時代の「ポストモダンガール」はなにを目指せばいいのでしょう。『モダンガール論』の結末は、読者にそこはかとなく不評でした。「先輩たちのことはわかったが、じゃあ私たちはどうすりゃいいの?」ってことですね。 正直にいうと、2000年の時点で、私にも明快なビジョンは見えていませんでした。」p.315
・「思えば、出世とは「見てくれ」にこだわる生き方です。考えようによっては「出世から下りる」ことで、かえって新しい展望が開けるかもしれない。」p.319
・「さしあたって私にできるアドバイスは、女性も男性も、一生続けられる仕事をぜひ見つけてください(それが見つかっている人は、ぜひいまの仕事を大切にしてください)、ということです。」p.320
・以下、解説(浅井良夫)より。因みにこの人物は、著者の大学(ゼミ)の恩師だそうです。
・「現存作家の文庫本の解説は、何のためにあるのでしょうか? そんなことは、今まで考えたこともなかったのですが、いくつかの文庫本の解説を開いてみて、要するに「お口直し」、たとえば、焼肉をたべたあとの、ペパーミント・ガムのようなものだと納得しました。「お口直し」ですから、作者と解説者の「取り合わせの妙」ないし「取り合わせの奇妙」がキー・ポイントです。」p.322
・「「進歩史観」、「抑圧史観」を排し、「この本はあまり正義の味方ではない」とうそぶく斎藤美奈子は、まさに、マンデヴィルの末裔です。」p.324
・「また、郁さんは、「ルーズソックスのコギャルは元気で明るい。(中略)この本の作者の斎藤美奈子さんも元気な女性の一人である。自分の考えを思ったとおりにまとめて、本を出版しているのだから」と、斎藤さんとコギャルの生き方の共通点をズバリ指摘しました。」p.328