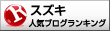白川通り花園橋を大原方面に右折。
蓮華寺を通り過ぎてすぐのところに入り口が見える。
バイクか自転車ならば数台置けるスペースがある。

崇道神社。
参道はうっそうとしており、昼間でも薄暗い。
奈良末期~平安初期の皇族、早良親王を祀る。
早良親王は、光仁天皇・高野新笠の子で、桓武天皇の実弟である。
延暦4年(785)、長岡京の造営長官だった藤原種継(ふじわらたねつぐ)が
暗殺された事件に連座したとして乙訓寺(長岡京市)に幽閉されたが、親王
は無実を訴え飲食を拒み淡路島へ流される途中憤死。
その後、桓武天皇の近親者に死が続いたこと、また都に悪疫が流行しはじめ
ると、貴族や庶民の間で親王の崇りとの噂され、その怨霊を鎮めるため延暦19年
”崇道天皇”と追号を贈り、高野村のこの地へ親王の御霊を祀る神社を創建。

参道は涼しい。
途中に朽ちかけたベンチがあり、座ってみると心地いい。

手水舎の水はこんこんと流れている。


狛犬。
苔が生え、勇ましさが増している。


本殿。
昼間でも電灯で照らされている。

伊多太神社。
御祭神:伊多太大神
崇道神社本殿への階段西側にある。

小野神社。
御祭神 小野妹子・小野毛人
小野毛人は最初の遣隋使小野妹子の子で天武6年(677)に没したとされる。
慶長18年、崇道神社境内の上高野一帯を見渡す山腹から鋳銅製の墓誌が
発見され、この墓が小野毛人を埋葬したものであることが明らかになった。
大正3年墓誌は国宝に指定され現在京都国立博物館に保管されている。

打たせ滝。

てっぺんが徳利?の形をした灯篭が多くあった。
・・・・・
大原へ行くときに、いつも通り過ぎていた神社。
訪ねてみると遣隋使の時代のものが発見されていたりで、深ーい歴史の
ある山だと関心する。
深呼吸すると、その時代の空気を吸っているような感覚になる場所である。
蓮華寺を通り過ぎてすぐのところに入り口が見える。
バイクか自転車ならば数台置けるスペースがある。

崇道神社。
参道はうっそうとしており、昼間でも薄暗い。
奈良末期~平安初期の皇族、早良親王を祀る。
早良親王は、光仁天皇・高野新笠の子で、桓武天皇の実弟である。
延暦4年(785)、長岡京の造営長官だった藤原種継(ふじわらたねつぐ)が
暗殺された事件に連座したとして乙訓寺(長岡京市)に幽閉されたが、親王
は無実を訴え飲食を拒み淡路島へ流される途中憤死。
その後、桓武天皇の近親者に死が続いたこと、また都に悪疫が流行しはじめ
ると、貴族や庶民の間で親王の崇りとの噂され、その怨霊を鎮めるため延暦19年
”崇道天皇”と追号を贈り、高野村のこの地へ親王の御霊を祀る神社を創建。

参道は涼しい。
途中に朽ちかけたベンチがあり、座ってみると心地いい。

手水舎の水はこんこんと流れている。


狛犬。
苔が生え、勇ましさが増している。


本殿。
昼間でも電灯で照らされている。

伊多太神社。
御祭神:伊多太大神
崇道神社本殿への階段西側にある。

小野神社。
御祭神 小野妹子・小野毛人
小野毛人は最初の遣隋使小野妹子の子で天武6年(677)に没したとされる。
慶長18年、崇道神社境内の上高野一帯を見渡す山腹から鋳銅製の墓誌が
発見され、この墓が小野毛人を埋葬したものであることが明らかになった。
大正3年墓誌は国宝に指定され現在京都国立博物館に保管されている。

打たせ滝。

てっぺんが徳利?の形をした灯篭が多くあった。
・・・・・
大原へ行くときに、いつも通り過ぎていた神社。
訪ねてみると遣隋使の時代のものが発見されていたりで、深ーい歴史の
ある山だと関心する。
深呼吸すると、その時代の空気を吸っているような感覚になる場所である。