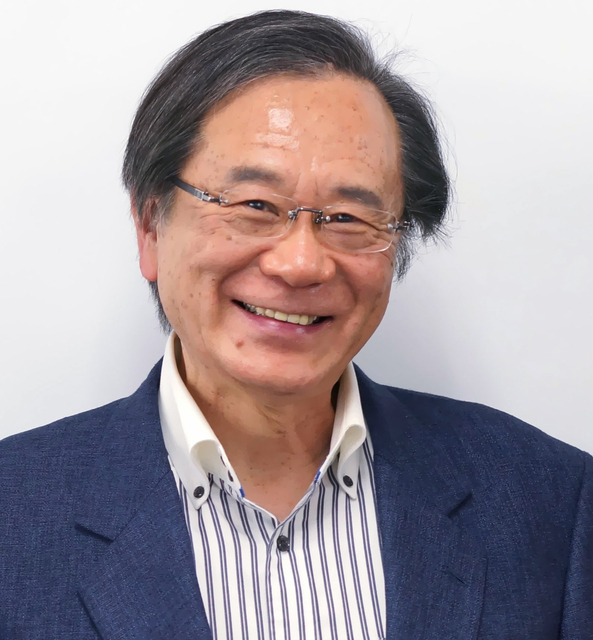1860~70年代(幕末から明治)に日本が西洋から取り入れた思想の体系は、西周によって「哲学」と訳され、今日に至っていますが、この固く厳しい響きを持つ言葉は、近代ドイツ観念論にはピタリと合う訳語でしょう。ドイツの文化と学問を学びとる「逸学協会学校」の初代校長・西周にふさわしい術語だと言えます。
しかし、今日必要とされているのは、もっとおおきくかつ明晰な思想です。生活世界の具体的体験につき、それを原理に戻して考えてみる営み=疑い・考え・試し・確かめる思索と実践です。活字や情報によってのみ判断するのではなく、心身の全体で深く知る=会得する知だと言えるでしょう。制度化され権威化された知とは無縁な「生きた納得の知」を生み出すことです。キリスト教という強い一神教(いっしんきょう)が誕生する前に古代ギリシャでつくられたプィロソプィア(philosohia)を素直に訳した「恋知」が必要、そう考えています。
私は、堅苦しく特殊な「知」を連想させてしまう「哲学」を「恋知」へ変えることを提案していますが、それは名称だけの問題ではありません。対象を限定した個別学問や技術的な知も、すべては人間の生きる意味と価値の問題をその根底には持っているのですから、なぜ?どうして?何のため?という意味論(恋知)は、あらゆる知を貫いて存在していなければなりません。どこかで一神教(いっしんきょう)の信仰との整合性を探ろうとする無理な営みを隠し持った「哲学」では、主観性を豊かにすることで、真に普遍的な了解を生み出そうとする「恋知」にはなりにくいのです。
おおもとに戻して考えるという営みは(フッサールの言葉では「純粋自我」、サルトルの言葉では「非・反省的自己意識」)、考えるという働き=主観性それ自体を豊かにすることであり、経験的な意味での自我意識(「おれは太郎だ!」)とは全く異なります。
強い疎外感が生み出した一神教の下で生じた反動形式としての「自我」ではなく、思考する作用=「意識」のことです。
そもそも歴史的には、ギリシャの恋知(哲学)とは、インドの仏教(無神論)と近親性をもつ言葉=概念であり、一神教のキリスト教とは対極にある思想です。ほんらい日本には「恋知」を花咲かす土壌があるはずなのですが、欧米の脅威から身を守ろうとして明治政府(下級武士の山県有朋ら)がつくった「天皇制」というイデオロギー(擬似一神教)が、自由に思考する土壌を奪ってしまったのです。予めの真理や権威を設け、タブーをつくる社会では、「恋知」は死んでしまいます。自由に、大胆に、伸び伸びと思い・考える「恋知」を広げ実践することが、自分の生を豊かにし、人間と社会の問題を現実的に解決するための基本条件だと思います。
自分の内側から、内在的に、主観性を豊かにしつつ生きる=「善美に憧れる」生き方を基本にもつことが「恋知」の基盤であり目的です。「超越的な真理」という発想とは無縁なのです。強い一神教や特定の主義が作る思想ではなく、無理なく自分の内側に納得がやってくるような思想を育てつつ生きることです。
来年4月より『民知の会』を始めますが、今日は、民知とは?を説明する前に、その前提で核となる「恋知」のことを書きました。
武田康弘