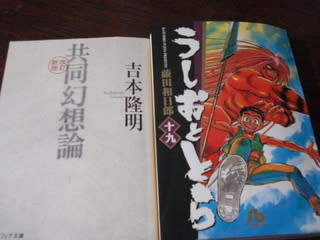昨日だったか、一昨日だったか忘れたが、原発推進学者が16人、「国民に深く陳謝する」とか謝ったそうである。「謝るだけまし、謝りもしない政治家は死ね」、「今更おそい」、「老い先短いやつが何言ってもしょうがない」、「謝る暇があったら現場に行ってこい」、「チェリノブイリ級になったときの言い訳かよ」、「東電からの賄賂を全額返せ、話はそれからだ」、「この16人以外に一番ひどいやつがいるに違いない」、「国民だけに謝るんですか、他国民はどうでもいいんですか」などなど、さまざま声があるであろう。
日本では、謝罪というもののほとんどは、本当は謝っていないときに行われるものであるので、当然であろう。むしろ、上のような侃々諤々を誘発してガス抜きをするための儀式である。とはいえ、この謝罪は下手すると歴史的な転換にもなりかねんので、あまりオオゲサに報道されている訳でもないようだ。テレビを見てないから分からない。
わたくしが、研究者の端くれとして思うのは、こういうことである。……たまたま原発推進学者は、金に釣られてか、鉄腕アトムばりの平和利用を本気でやろうとしてたか、本当は原発で世の中滅ぼすのが目的だったのか、東電に親戚や恋人がいたからか、指導教官に脅されてか、学内の資金獲得競争に勝ちたかったのか、原子力と聞くと頭が回転し始める才能であったのか、人文的に馬鹿だったのか……なんなのかは知らないが、それぞれ理由があって、こんなことになってしまった訳である。しかし、おそらく、こんなことは、原子力村でなくても研究者の世界ではそこここで起こっている。
例えば私は、教育学部内の若手研究者のためのなんとか寄金に「近代文学の宗教的なんとか」というテーマで応募したところ、速やかに落選したので、次年度「近代文学の〈子ども像〉の変遷」に変えたところ、速やかに通過した。私は〈子ども像〉にあんまり興味はないが、大学院や免許更新講習の授業で一応講義してみた。そして改めて、こんなテーマは、まだアリエスを読んで感動してしまうおっちょこちょいにしか通用しないテーマだったなあと思ったわけであるが、私もこれから、はずみで講義の成果を発表していい気になってしまう可能性がある。無論、自分なりの発見がなかったわけではなかったから……。もっと金の使い道にうるさい寄金なら、確実にきちんとした研究成果を求めてくるはずだ。その場合、私は自分の本来の研究を棄てて、〈子ども像〉を騙る研究者になっていたかも知れない。この程度のことは起こる。これが上の16人の場合原子力推進であったかもしれない。
大学院のときには、ある教員のために研究費申請の原案をつくった。そのときのテーマは、私ですらとうてい思いつかぬような愚劣なものだと思ったが、なんとなく学会の流行の一部を形成しそうだったのか、協力研究者のメンツがよかったのか、私の魂を売った作文が素晴らしかったのか、めでたく研究費を獲得した。ただでも、その教員とは必ずしも仲がよいとはいえなかったが、この仕事を断っていたら何をされるのか分からないと思ったものである。私の被害妄想の可能性はかなりあるが、そんな雰囲気が漂うのが大学である。
現在、研究費獲得のために手段を選ばず、などという発想は、別に研究者にとっては良心の呵責どころの話じゃなくなっている。「社会に貢献」とか「書類のわかりやすさ」から「審査委員の気に入るように」、「学会懇親会での立ち回り」に至るまでいろいろレベルはあるが、この程度の妥協はお茶の子さいさいである。最近は、どこからか批判やクレームが付きそうな文章は、「わかりやすくしろ」という脅しが心の中に聞こえてきて、自主的に内容を変えている。「わかりやすさ」への要求は、しばしば、通念や空気への従属の要求として行われているからこそ脅しに感じる。……というか、そういう心の声に応えようとなんだか燃えてくるタイプこそが最近は研究者になる、そういう可能性だってあるのである。かかる研究者にとっては、脅しはもはや他者に対する使命として昇華され、必要不可欠なものになる。こうなってくると、下手をすれば、一見ラディカルで、かつ寄らば大樹の陰的な研究者ができあがる可能性が出てくる。……大学の中にいると、研究者にはかかる心の仕組みがある程度必要であるかに思われてくるから不思議だ。そう思わなければ同調圧力で確実に気が狂う。最近は、クレームが付きそうだったり自分の知らない言葉があるだけで文章の内容を変えさせたいと思う人もいるが、端から見てると、気が弱いのか、本気なのかわからないところが不気味である。私もいつそうなるか分からない。
以上のような感想を持つので、私は「社会のため」を研究目的にするのには反対だ。科研費に関するもろもろの議論を聞いていると、本気かどうか分からないが「社会的な意味のないものは存在する意味がない」と口走ったりする研究者がいるが、とんでもない話である。なぜなら「社会のため」などという言葉の内実は、時代の空気に、あるいは誰かの意図や利益に沿ったかたちに、いかようにも変化し得るし、実際変化しているからである。実のところそれを知ってて、申請書類に手心を加えてしまったりするのに、社会も何もあったものではない。「人間のため」の方がまだましかも知れない。ましだというだけであるが。
研究者の世界というのは、こんな中で、なんとか独創性をぎりぎり追究するしかないような、すさまじい世界である。のみならず、自分の好きなことをやっているうちに、どかんと建家が爆発してしまうこともあるから大変である。