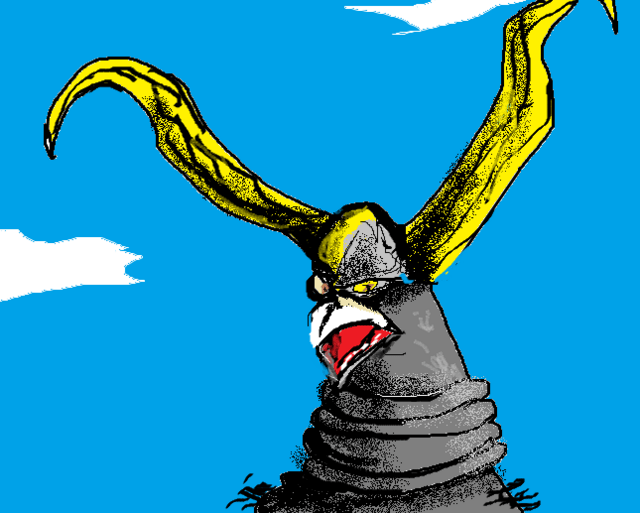
わたしはすごく眠くなる直前にむかって時間をかけて集中力があがっていく人間で、なにもやってないと大体前半はモウダメダみたいな感覚との戦いになるので、絵を描くとか飜訳するとか漢文読むところからはじめて文献名を入力するみたいな作業の果てにやっと本題に入る。しかしこれが不眠とかで体力が落ちてくると、この器械的な助走が失われてやばい感覚のまま本題に入らざるをえない。調子が良くなってくるといきなり本題に入ったり読書に入れる。授業はだいたい助走の部分に当たっている気がする。われわれのような職業の場合、お外での作業は本番ではない。
麻生海氏の『の、ような。』を少し読んだが、あるいみ、家族内で気を遣いあう地獄は、性悪ママ友を主人公が説教したりすることによって少々ましになっているようにみえる。主婦が、お外での活動に勤しむには理由があるのだ。
戦後文学にとってお外は、はじめは戦争であり自分そのものであった。しかし、大江や石原になってくると、子どものときにいろんな体験をしているけれども結構忘れている、あるいは作品によって昇華を行いすぎた。で、やたら暴力を描くようになった側面はある。それは不可避的な流れであって、しかしそれが吉本隆明みたいな思春期=戦中派にはゆるせなかった。吉本隆明のわりと知られた大江・石原批判である「もっと深く絶望せよ」をさっきちょっと再読したが、なんかもっと深い怨念が書かれていると勘違いしていた。そうでもない。これだったら、逆に、あまりに「自殺」「殺人」みたいな話題に赴いている大江・石原の方に、何か書かれていない深さがあるんじゃねえかと思ってしまうくらいである。吉本も、この時期はまだ、外部として、マルクスを分かりやすく使う部分があった。
野茂やイチロー以降は、お外を外部と感じない。いまや自意識の力こぶを入れずに大リーグで活躍する大谷がいる。今日、42号=厄年ホームランを打っていた。彼は顔がかわいい?から欺されているけど、でかい図体・ピッチャーやる・悪球打つ・帽子をぶんなげる、つまり完全に「ドカベン」の岩鬼
なのであるが、岩鬼は山田の外部として描かれていたから、あのキャラクターなのであって、いまは単にオオタニサンでいいのである。
外部と内部があった時代は、「影響」というのに特別なニュアンスがあった。つまり与えられた側からいうとなんかありがたいような気がするものであった。しかし、ほんとは与える側からすると水をこぼしたみたいなかんじなのだ。さっき読んだ有名なコミューン組織の本にはKJ法の本が参考文献にあがってて、まあそりゃそういうこともあると思った。この本には、コミュニズムというのは道徳的に「恥」の文化であると書いてあった。学生運動時代の後期には、敵が味方に、隣が遠くに、みたいな混淆がおこって、わけがわからなくなってしまっていたのだ。しかし、まだこれを葛藤として認識していた時代があった。
遠い記憶だと金田正一氏の『かねやんのズバリ勝つ』かなにかに、本妻以外の女性がいると批判されるのは民主主義になったからだみたいなことが書いてあった。フィンガー5の「くたばれジャイアンツ」というのもあった。なにかおかしい。私自身を振り返ってみても、なにか文化資本的に割り切れない感じがいつもあった。私の家には、マルクスも西田も藤村も確かにあったが、同時に中日スポーツがあった。どうかんがえてみも信濃毎日よりちゃんと読んだのである。「中日スポーツ」の全体的に滑っている駄洒落がよかった。――いまだって、学校では新聞よみなさいと指導してるし、新聞の文章をつかったもっともらしい教育法さえあるが、それが朝日読売毎日あたりの悪文を想定しているのがだめだと思うのだ、と庶民文化を愛でることはもう無理だ。
こういう居心地の悪さを克服しようとしてかしらないが、――野球関係の本というのは、昔だったら王選手の伝記とか、どことなく教養小説じみているところがあったのを、野村とか落合とかのそれにおいて、ビジネス書みたいな側面を拡大させて、ある種の修養的な文化に近づいている。一方で、2000年代までは『おしゃれ野球批評』みたいなおふざけ批評の伝統があり、金田正一氏の遊郭行ったなんだの自慢話の本なんかが特に70年代は結構あったはずで、スポーツ新聞にはかならずエロ小説が載っていた。これはいまでもあるのかしら?
最近知ったのは、まだ各地で精霊馬をつくっていること、あるいはみんなわりと精霊馬がスキということである。これはネットでばれた。わたしは、ポストモダンにこだわりすぎているのかも知れない。









