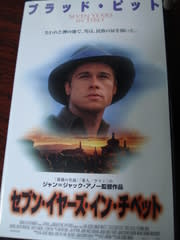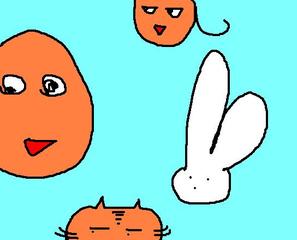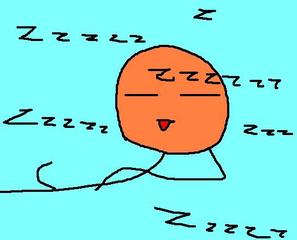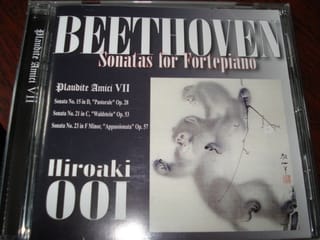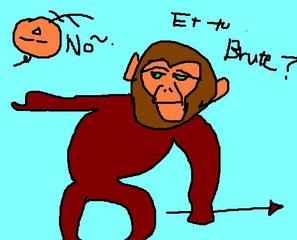あ、間違えた「虚体っ」は埴谷雄高だった。
吉本については、いずれ書こうと思う。ここ数年吉本論ブームだったから、もうみんな追悼は済んでるんじゃないか?わたくしも昨年、柄谷行人「場所と経験」論を書いて吉本についても言及したけど、まだ書き足りない気もするから、書くかも知れない。
匿名批評といえば×田×輝とかを想起するが、彼は文体に強い癖があったので消えます消えますと言いながら全然消えていなかった。むしろ、2ちゃんねらーとかツイッター患者の先祖は吉本氏かもしれない。とにかく、この人は、間違いも気にせずにしゃべりまくり書きまくりの人であって、本当に吉本氏が書いてるのかしゃべっているのか分からなくなってしまうほどである。塾で朝の一〇時から夜の一〇時までほとんど休みなしに授業をやった経験があるが、まさにそのときに「私」が消える。労働とは何か、疎外とは何かを私はその時悟ったね。吉本氏がやったのはそれじゃなかろうか。民衆の原像だかを、普通はイメージで示そうとするのが文学者というものだが、彼は違う。自分が「民衆」だからそのまましゃべっていればよかった。というより、誰でもそうなのだが、彼はそこんとこをきちんと自覚していたのだ。ここまでの自覚はちょいと勉強した人には難しいと考えられていたが、じつはそうでもなかったのである。
ただ、現今のネット世論の方々は、吉本氏をもっと真似て、たどたどしい語り方をしないと目立ってしまうから気を付けた方がよいかもしれない。吉本氏の「あー、えー、あの~、言語はコミュニケ~ションの道具という考えをわたしは否定しましたぁ~。あー」というたどたどしい語りが懐かしいわ。ネットのコミュニケーションはやっぱり独り言の応酬であってコミュニケーションとはいえない。まさにこの状態も、吉本氏は予言していたわけだ。
空想的ユートピアンが歳をとって、せっかく日本の伝統の研究によってあらたな
人民革命の可能性が開かれようとしていたのに、公務員は国歌を歌えとか教頭センセはちゃんと教員が口パクをしてるか監視せよ(あ、あれは自主的にやったのか。教頭は歌いながらご苦労なことだ。)とか、明治政府もびっくりのレベルに議論を落としたい輩が目立ってしまう今日この頃である。小学校の学級会だったら、きまりを守ってない奴を「せんせー、史郎くんがまた掃除の時間に虫いじってました~」などと告発すればよいかもしれん。むろん学級会は怨嗟と嫉妬が勝つ場所なのでそれでもいいかもしれない(よくね~w)が、そんな風に世の中うまくいくのであろうか。かわいそうな末端の教員とか公務員を虐めてもしょうがなかろう。例の知事は、
支配階級エリートの小ずるさをなめてるんじゃないか?明治以来に視野を限ってみても、天皇崇拝をとりあえずの団結のために「かのやうに」導入しなければならないほど、権力に群がる「自称エリート」の足の引っ張り合いと小ずるさはすさまじかったとみなすべし。今日の世界だって、どうせそんなもんだ。下級役人のほころんだ団結を怒ってるうちに、もっと頭のまわるずるい連中に寝首をかかれるぞ。たぶん彼の目指すのは、よく言われるようなファシズム=ハシズムではなく、行動力があり頭の切れる資本家と仲良くする帝国主義的な何かである。だから彼は個人の「自立」すら唱えるのである。彼にとってむしろ日本の社会主義的ファシズムが自分の足を引っぱっていると感じているはずだ。ただ、コンプレックスがある「自称エリート」はむしろそういう帝国主義を嫌うはずである。
吉本氏の考察は、そのずるい連中から精神的に極限まで離れ、例の知事に期待する学級会的精神からも離れたら、何が見えてくるか、という気分で為されたのかも知れない。考えてみれば、いざ氏がいなくなってみると淋しい気もしてくる。アカデミックな世界はどちらかというとさっきの知事みたいな人間が潜在的に多いからである。