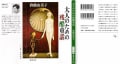このところ病院へ行くことばかりである。3月中と明日4月3日までの34日間で、私の通院と検診7回、親の付き添い7回、妻の付き添い1回、親族の見舞い1回と計16回である。2日に1回は病院通いである。
明日は午前中にいつも受診している科での採血と採尿による検査。結果は1週間後に出来るのを聞きに行く。
明後日以降の私の通院は減る。病院通いの大半は親の通院の付き添いだけとなるはず。
本日の午前中は、自宅で読書タイム。「天気で読み解く名画」(長谷部愛、中公新書ラクレ)の第2章を読み終えた。


天気に関わる指摘は頷けるものもあるし、既知のことの再確認もできる。
「オランダ絵画には雪の風景がよく描かれています。今のオランダではうっすら積もる程度ですが、ブリューゲルの時代は寒い時期に突入した最初ころ。1550年から1849年の間はヨーロッパ全体が非常に寒かったといい、絵画に雪景色が急に増えていった時期になった。日本でも浮世絵に雪のシーンがしばしば描かれており、江戸時代も飢饉が何度か起こるほど、寒い時期だったとされています。ヨーロッパでも日本でも寒さがモチーフをおおいに左右したと言えそうです。」(第1章)
だがしかし安易な把握もある。以下はとてもいただけない箇所、乱暴ないい様である。
「ヨーロッパでは、狩猟民族であることから晴れている時に狩りに出られること、緯度が高く強い日差しが貴重なため、光が何よりも重視されたと思われます。一方で農耕民族である日本や中国では、雨をもたらす雲が恵みの象徴となってたのでしょう。」(第1章 コラム1)
ヨーロッパには農業や牧畜がなく、狩猟民だけが生存し、日本や中国には牧畜も漁撈もないような世界であるような言い回しである。戦後の私の親の世代でよく言われていた。
欧米に占領されていた時期に「鬼畜米英」の延長のような「狩猟民族との体力差で敗北した」という負け惜しみ的な言説がまことしやかに流布していたのを耳にしていた。そんな劣等感の裏返しのような言説に飛びついて何かを言った気分になるのだろうか。あまりにみっともない言説に与しないでほしい。
こういう点を抜きにして「天候論」として楽しみたい内容の本である。