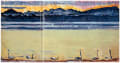本日大晦日。私の部屋の本箱はいまだ最終整理が出来ないが、取りあえず本日の作業は終了。あとは追々(といいつつ何時になるかはまったく不明)と片付けることにする。机の上はきれいになっている。
「大晦日と云えど単なるカレンダーが変わるという以外、時の経過点でしかない」と言ってしまうこともできるが、それでは人生の区切りも、繰り返しにかかる意識の更新もできない。年中行事の内の年末・年始くらいは気分を新たにする意味でも、身の回りの整理、過去の反省や来年の抱負を頭の隅で考えるのも悪くない。
そんな時間をこれから3日間ほどは持つことも大切であろう。
さて本年も一年、私のブログに目をとおしていただきありがとうございます。
親族の不幸が年末にあり、この国の戦後の習いにしたがい、賀状は遠慮しました。「寒中見舞い」という形式で正月明けにはご挨拶状を投函する予定です。
またブログやツイッター上で親しくコメントを交わしてもらっている皆様にはこの場で御礼申し上げて年末のご挨拶と致します。
そして皆様方の来年のご活躍・ご多幸をお祈り申し上げます。
また来年、引き続きこのブログのお目とおし、よろしくお願いいたします。
「大晦日と云えど単なるカレンダーが変わるという以外、時の経過点でしかない」と言ってしまうこともできるが、それでは人生の区切りも、繰り返しにかかる意識の更新もできない。年中行事の内の年末・年始くらいは気分を新たにする意味でも、身の回りの整理、過去の反省や来年の抱負を頭の隅で考えるのも悪くない。
そんな時間をこれから3日間ほどは持つことも大切であろう。
さて本年も一年、私のブログに目をとおしていただきありがとうございます。
親族の不幸が年末にあり、この国の戦後の習いにしたがい、賀状は遠慮しました。「寒中見舞い」という形式で正月明けにはご挨拶状を投函する予定です。
またブログやツイッター上で親しくコメントを交わしてもらっている皆様にはこの場で御礼申し上げて年末のご挨拶と致します。
そして皆様方の来年のご活躍・ご多幸をお祈り申し上げます。
また来年、引き続きこのブログのお目とおし、よろしくお願いいたします。