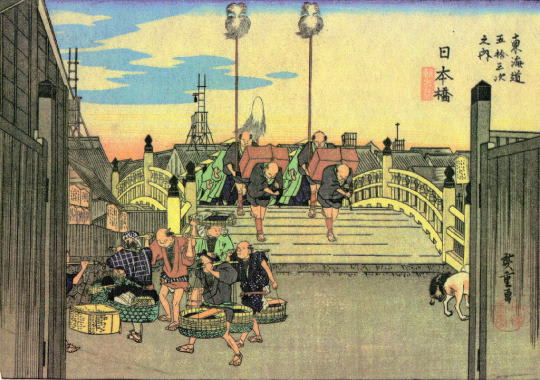この絵は周防灘のシリーズから1982年の作品。洲之内徹の文章(「幸福を描いた絵」所収)では、「どこかの海水浴場らしいが人間はいない。しかし、誰もいない幸福というものもあるだろう」と書かれている。
実際の本文には別のデッサンが掲げられているのだが、私はこの絵にもぴったりの評だと思う。
周防灘の景色のデッサンを元にしているのだが、敢えて海岸、空、雲、島、船という区分けをしなくても、景色という概念を取っ払って、色彩と抽象的な形が舞っていると理解しても楽しいのでは無いだろうか。画家は抽象画について「色や線や使われた材料でそれぞれの美の世界を作り上げたもので、リンゴを描いたとか、女を描いたとかでは全くありません。」「具象と抽象と二つに、はっきり分けることはできません」と述べているとのこと。
楽しい絵についていろいろ記載しても意味は無いと思うので、私が楽しめた絵をランダムに掲げてみることにした。

まずは「大威徳明王」1975年。図録には同じ年の絵としてもう1枚掲載されていたが、当日私が見たのはこの1枚。4色だけが使われているが、その色は不思議とさまざまな陰翳をしめし、塗り方の工夫が面白い。これはこの絵に限らず画家のすべての絵に当てはまる。マチエールの豊かな技法ということらしい。

次が、「鷲」1978年。

そして初期の「綾取り」1957年。この画家らしい表現の出発点のように私は感じた。
4本の手と紐にだけ注目し、身体にまとった青と赤の服がほとんど背景の色として塗りこめられている。綾取りの紐の赤がとても印象的だ。

「かみきり虫」1959年。ビュッフェの影響の強い作品と図録に解説。かみきり虫というが作品自体はとても大きい。死んでいるか、死を迎えつつあるかみきり虫でろう。生物(動物・植物を問わず)に対する画家の視線、志向が明確になってくると思える。

「眠る人」1963年。60年代、70年代はどうもこのように横に人体を描くことが目についた。特に70年代は裸婦が横になっている。この男の姿はそれらのはしりのような絵である。同時に極めて幸福な絵のひとつである。
私もこのように寝ていたい。

「笛吹き」1983年。この絵は、洲之内徹の「人魚を見た人」の表紙のために描かれた作品。本の表紙と図録とそして実際の絵とは、色の具合が微妙に違う。実際の絵は本の表紙の絵に近い。この絵では背景の黄色の右側、フルートを吹く青色の服の背景の上部は茶色に近い。そして髪の毛は赤に近い。顔の輪郭も赤い線である。かなりの早書きのように見える。

「自画像(Mの肖像)」1986年。画家73歳の年の自画像である。自画像というと結構構えた顔で描かれる。ゴッホなど深刻そのものの顔だ。自己の芸術、いや、時代の芸術の抱える苦悩をすべて引き受けようとするような顔がそこにはある。
しかしこの絵はそんな深刻なものはうかがえない。かといって画家がひたすら好々爺として悩んでいなかったわけではない。この人ほどデッサンから実際の作品になるまでの過程が長かった人も珍しいという画家であるらしい。
しかも不思議な色である。不思議な青だが、違和感は少ない。不思議な絵である。そして本人の写真とそっくりというのも不思議だ。

1970年代、画家は裸婦を盛んに描いている。この絵は「月と犬と裸婦」1978年。図録ではアンリ・ルソーの「眠れるジプシー女」に刺激を受けたのではないかと書かれている。
その当否は別として、しかし私はこれらの70年代の裸婦像からはそれほどのエロティシズムは感じない。

1982年以降、画家は千葉の鶴舞のアトリエから五反田まで裸体のモデルを描きに通って6冊に及ぶスケッチブックを残した。
そして70歳になろうとしている画家は、こんなことを書いている。「何十年振りで裸婦をえがいたろうか、あさ黒い痩せた女はまづまづの体をしている。太もものあたりやはり女体の艶がある。‥50年前の画学生にもどった気がした」
洲之内徹の「耳の鳴る音」には画家の言葉として「研究所で一緒に描いている女の子たちはこれを見ると笑いだすんだ」とある。さらな「付き合っている女を裸にしたらこうは描かんだろうなあという気が描きながらする。‥(モデルが)休んでいるときの方が面白い」。
なかなかの言葉である。私には確かに1970年代の裸婦の油絵よりも1980年代の画家が70代を過ぎてからのデッサンの方が生々しく、そしてエロティックに輝いて見えるのが不思議だ。
こんな感想を抱いて、展覧会場と併設の喫茶店を後にした。