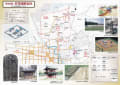本日のお昼にアップした記事「「魯迅の階段教室」&壱弐参横丁」に寄せられた通りがかり人様のコメントに私は気取って次のようにこたえた。
学部の二年間ははっきり言って、魂の抜けた抜け殻、息をしているだけの亡霊のようにフラフラほっつき歩いていました。恥ずかしながら生き続けているようで‥。早く抜け出したくて、気の遠くなるように長い二年間をひたすら耐えていました。
「懐かしい町」を歩く、というのは「自分の恥が埋まっている街」から古い恥を拾い集めて歩くようなものです。これもエネルギーが必要です。
今も付き合ってくれる当時の友人は、教養部の三年間だけでなく、そんな亡霊のような私の二年間と、それだけでなく卒業後も付き合ってくれた仲間です。
「恥」というのは別に酔っぱらってまき散らした恥を表現しているわけではない。自分を見失って、自分の外界との関係をうまく処理できなくなっていた当時の不安定な自分を表現してみた言葉である。昔の自分、と言い換えればいいだけかもしれない。
当時と現在の街を同時に歩くということは、そんな40年前の自分と向き合うことだ。街の風景に埋もれた古い景色の中から自己を見失っていた頃の自分を掘り起こすことである。掘り起こしながら、今の自分を照らし出して見る行為である。
横浜という土地で40年暮らしても、忘れようにも忘れられなかった仙台での20代前半の自分、しかし細部では記憶は大きくズレている。最近は、そのズレを再確認しながら、最近はこのズレの原因にこだわって反芻し続けてばかりいる。当時と現在の自分を結びつけるまでにはならない。先の見えない堂々巡りを繰り返す自分に苛立ってばかりいる。
仙台に暮らし始めた初めの3年間、ひたすら社会と自分の濃密な関係を追い求めたと思う。そして崖っぷちに立っている自分にたじろいで、たたずむことになった2年間。誰にでもある20代の屈曲点とかたずけてしまうのは簡単であっても、そこから抜け出すことの困難は、個人、時代、経験、自己史、周囲の状況等々でバリエーションは無限にある。
そんな出口のない思いをめぐらす街が、私にとっての仙台である。

人気ブログランキングへ
学部の二年間ははっきり言って、魂の抜けた抜け殻、息をしているだけの亡霊のようにフラフラほっつき歩いていました。恥ずかしながら生き続けているようで‥。早く抜け出したくて、気の遠くなるように長い二年間をひたすら耐えていました。
「懐かしい町」を歩く、というのは「自分の恥が埋まっている街」から古い恥を拾い集めて歩くようなものです。これもエネルギーが必要です。
今も付き合ってくれる当時の友人は、教養部の三年間だけでなく、そんな亡霊のような私の二年間と、それだけでなく卒業後も付き合ってくれた仲間です。
「恥」というのは別に酔っぱらってまき散らした恥を表現しているわけではない。自分を見失って、自分の外界との関係をうまく処理できなくなっていた当時の不安定な自分を表現してみた言葉である。昔の自分、と言い換えればいいだけかもしれない。
当時と現在の街を同時に歩くということは、そんな40年前の自分と向き合うことだ。街の風景に埋もれた古い景色の中から自己を見失っていた頃の自分を掘り起こすことである。掘り起こしながら、今の自分を照らし出して見る行為である。
横浜という土地で40年暮らしても、忘れようにも忘れられなかった仙台での20代前半の自分、しかし細部では記憶は大きくズレている。最近は、そのズレを再確認しながら、最近はこのズレの原因にこだわって反芻し続けてばかりいる。当時と現在の自分を結びつけるまでにはならない。先の見えない堂々巡りを繰り返す自分に苛立ってばかりいる。
仙台に暮らし始めた初めの3年間、ひたすら社会と自分の濃密な関係を追い求めたと思う。そして崖っぷちに立っている自分にたじろいで、たたずむことになった2年間。誰にでもある20代の屈曲点とかたずけてしまうのは簡単であっても、そこから抜け出すことの困難は、個人、時代、経験、自己史、周囲の状況等々でバリエーションは無限にある。
そんな出口のない思いをめぐらす街が、私にとっての仙台である。
人気ブログランキングへ