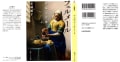雪の句はたくさんある。雪は多くのことを感じさせる。雪は実にさまざまな感覚を吸い寄せる。そして雪は人を感傷的にさせる。雪は人の感覚を鋭敏にさせる。
まだまだあるが歳時記より目についた句を8句ほど。艶めかしいものもある。
★降る雪や玉のごとくにランプ拭く 飯田蛇笏
★雪降れり時間の束の降るごとく 石田波郷
★雪の日暮れはいくたびも読む文のごとし 飯田龍太
★雪はげし抱かれて息のつまりしこと 橋本多佳子
★音なく白く重く冷たく雪降る闇 中村苑子
★窓の雪女体にて湯をあふれしむ 桂 信子
★雪まみれにもなる笑ってくれるなら 櫂未知子
★深雪晴わが影あをき虚空より 深谷雄大
まだまだあるが歳時記より目についた句を8句ほど。艶めかしいものもある。
★降る雪や玉のごとくにランプ拭く 飯田蛇笏
★雪降れり時間の束の降るごとく 石田波郷
★雪の日暮れはいくたびも読む文のごとし 飯田龍太
★雪はげし抱かれて息のつまりしこと 橋本多佳子
★音なく白く重く冷たく雪降る闇 中村苑子
★窓の雪女体にて湯をあふれしむ 桂 信子
★雪まみれにもなる笑ってくれるなら 櫂未知子
★深雪晴わが影あをき虚空より 深谷雄大