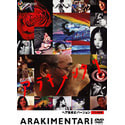★★★★★ 1964年/日本 監督/今村昌平
「ほてる頬」
この時代の今村監督の作品は、モノクロのコントラストが実に美しい。市川崑が「黒を作り出す」巧さだとすると、今村昌平は「白を作り出す」巧さではないでしょうか。いや「白」と言うより「光」の使い方と言った方が正しいか。
春川ますみ演じる主人公貞子は、いつも毛糸の帽子に野暮ったいスカートを履き、体も太っているし、はっきり言って美人ではない。そんな彼女が幾度となく強盗犯に陵辱される。のけぞる彼女の顔、特にぽっちゃりとした頬に光が照らされる。その時の彼女の艶めかしさと言ったらこの上ない。それは、レイプされる女を美しく撮ろうというごまかしの映像では決してなく、言われなき陵辱に為す術もない女の顔に迫れば迫るほど、恐ろしいような美しさが際だってくるのだ。
このようにどこに光を当てるかで、見せたいもの、強調したいものを瞬時に観る側に悟らせる。これは、モノクロ映画ならではのテクニックだろう。光の存在は、特に室内の撮影で効果を発揮している。安普請の日本家屋、無理矢理連れて行かれる連れ込み宿、強盗犯が勤めるストリップ小屋。どこにいても光の存在が際だつ。不幸を絵に描いたような貞子と言う女の物語の泥臭さと「白」の強調がもたらす映像の美しさが見事に溶け合っている。先に書いた「にっぽん昆虫記」も同様だ。
夫、姑、社会、制度。あらゆる呪縛にただただ耐える女、貞子。夫からぶたれようが、姑からいじめられようが、愛人から馬鹿にされようが、「わたしはなにもできない女」という思い込みは、骨まで染みている。あげくの果てに強盗犯にレイプされ、付きまとわれ、いいことなんかなんもないと世の中を嘆く。貞子という女はとことん無力で、自分を卑下して生きている。その様は、現代人にはとてつもなく愚鈍に見えるが、しかし、女という生き物の一つの側面であることには間違いない。一方、貞子を囲むふたりの男。妻をいびることしか頭にない夫(西村晃夫)と死期を前に強引に女に迫る男(露口茂)は非常に身勝手だし、器が小さい。が、しかし、その狭量さもまた、男という生き物の確かな側面なのだろう。人間の醜さやずるさを切り口にして、「生」を鮮やかに描く。これぞ、今村昌平の真骨頂。
自ら自分を変えようという積極的な意思はかけらもなく、ただ男の好き放題に呑み込まれるだけの貞子だが、それゆえ、多くの修羅場を切り抜け、ほんの少しの強さを身につける。夫には絶対服従だった貞子が、夜中にザッザッと編み機を動かす。「うるさい」と言われても動かす。「子どもの学費がいりますから」と初めて口答えする。そのほんの少しの第一歩は貞子をこれからどう変えていくのか、彼女の後ろ姿に思いを馳せる、秀逸なラストシーンだ。
「ほてる頬」
この時代の今村監督の作品は、モノクロのコントラストが実に美しい。市川崑が「黒を作り出す」巧さだとすると、今村昌平は「白を作り出す」巧さではないでしょうか。いや「白」と言うより「光」の使い方と言った方が正しいか。
春川ますみ演じる主人公貞子は、いつも毛糸の帽子に野暮ったいスカートを履き、体も太っているし、はっきり言って美人ではない。そんな彼女が幾度となく強盗犯に陵辱される。のけぞる彼女の顔、特にぽっちゃりとした頬に光が照らされる。その時の彼女の艶めかしさと言ったらこの上ない。それは、レイプされる女を美しく撮ろうというごまかしの映像では決してなく、言われなき陵辱に為す術もない女の顔に迫れば迫るほど、恐ろしいような美しさが際だってくるのだ。
このようにどこに光を当てるかで、見せたいもの、強調したいものを瞬時に観る側に悟らせる。これは、モノクロ映画ならではのテクニックだろう。光の存在は、特に室内の撮影で効果を発揮している。安普請の日本家屋、無理矢理連れて行かれる連れ込み宿、強盗犯が勤めるストリップ小屋。どこにいても光の存在が際だつ。不幸を絵に描いたような貞子と言う女の物語の泥臭さと「白」の強調がもたらす映像の美しさが見事に溶け合っている。先に書いた「にっぽん昆虫記」も同様だ。
夫、姑、社会、制度。あらゆる呪縛にただただ耐える女、貞子。夫からぶたれようが、姑からいじめられようが、愛人から馬鹿にされようが、「わたしはなにもできない女」という思い込みは、骨まで染みている。あげくの果てに強盗犯にレイプされ、付きまとわれ、いいことなんかなんもないと世の中を嘆く。貞子という女はとことん無力で、自分を卑下して生きている。その様は、現代人にはとてつもなく愚鈍に見えるが、しかし、女という生き物の一つの側面であることには間違いない。一方、貞子を囲むふたりの男。妻をいびることしか頭にない夫(西村晃夫)と死期を前に強引に女に迫る男(露口茂)は非常に身勝手だし、器が小さい。が、しかし、その狭量さもまた、男という生き物の確かな側面なのだろう。人間の醜さやずるさを切り口にして、「生」を鮮やかに描く。これぞ、今村昌平の真骨頂。
自ら自分を変えようという積極的な意思はかけらもなく、ただ男の好き放題に呑み込まれるだけの貞子だが、それゆえ、多くの修羅場を切り抜け、ほんの少しの強さを身につける。夫には絶対服従だった貞子が、夜中にザッザッと編み機を動かす。「うるさい」と言われても動かす。「子どもの学費がいりますから」と初めて口答えする。そのほんの少しの第一歩は貞子をこれからどう変えていくのか、彼女の後ろ姿に思いを馳せる、秀逸なラストシーンだ。