『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』
<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=htsmknm-22&o=9&p=8&l=as1&asins=B00130HI74&fc1=000000&IS2=1<1=_blank&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>
例のI drink your milkshake! I drink it up! だね。ハイ。
すごーい、おもしろかった。すばらしい。コレも原作読みたい。
舞台は19世紀末〜1920年代。石油採掘業者のダニエル(ダニエル・デイ=ルイス)はポール(ポール・ダノ)という青年の情報でリトル・ボストンという小さな街の土地を買い占め油井の掘削を始めるが、ポールの弟で牧師のイーライ(ポール・ダノ/二役)はことごとに彼に信仰を強要し、やがてふたりは対立していく。
このハナシがねえ、もう、どうしても、現代のアメリカのいろんな面を如実!!に象徴してるよーにみえてみえてしょーがなかった。
まず石油。アメリカは世界最大の石油消費大国であり、現在のイラク戦争だけでなく20世紀の中東外交はすべて石油の利権のためだった。石油のためなら平気で人を騙したり殺したりするダニエルの人物像は、そんなアメリカのある一面を象徴しているようにみえる。
そして宗教。70年代に比べ飛躍的にキリスト教原理主義勢力が政治力をもつようになったアメリカ。とくに信心深い人が多いといわれるバイブル・ベルトと、レッド・ステイツ=共和党支持者の多い地域は地図上でぴったり重なっている。なにかといえばまるでゲームのルールのように聖書やら神やら原罪やらを持ち出してくる、主体性があるのかないのかわからないアメリカ人のまたべつの面を象徴しているのが、イーライではないだろうか。
他にも、途中で耳が聞こえなくなってしまう息子H.W.(ディロン・フレイジャー)とダニエルとの関係も何やらすごく象徴的に感じる。何を象徴してるのかはネタバレになるので控えますが。
全編ほとんどがダニエルとイーライふたりの生き方の対比になっていて、みればみるほど語り手がいわんとしてることが過激な皮肉に聞こえてくる。
お金がそんなに大切ですか。信仰ってそんなに大切ですか。ふたりが真剣になればなるほど滑稽で、ふたりともムチャクチャ淋しそうにみえてくる。でも本人たちはあくまで必死である。わかりやすいといえばそれまでだし、一貫性のある生き方をよしとするならそれもアリかもしれないけど、みてる限りは全然幸せそうじゃない。彼らは自分のしたいようにしてるだけなのに、なぜか不幸にみえてしょうがない。
だってダニエルはべつに石油採掘という仕事を愛してるワケじゃない。今たまたまお金になるからやってるだけである。イーライだって口でいうほど絶対的に神を信じてるワケじゃない。どーみても周りにありがたがってもらうために預言者のフリをしてるだけである。
そういう人生がどーすれば楽しくみえるっちゅーねん。ありえへんやろー。
本質ではふたりともよく似てたりもする。相手のいうことを聞かないで、とにかく自分の主張ばっかり大声で暴力的に押しつけるだけ。アメリカ人よ・・・。
158分と長い映画だけど、会場けっこう爆笑の連続でなかなか楽しく観れましたです。
なんかホラーみたいなコワイ音楽もたいへん効果的で気に入りました。ストーリーは重いのに重くなりすぎないテイストにうまくまとめてあったのにもたいへん感心しました。
ポールとイーライ兄弟の関係が最後まで謎だったのがネックといえばネックでしたが(多重人格かと思った)、それ以外には気になるところもなかったし、われわれが普段当り前に消費してる石油の産出事業の歴史も勉強になったし、ホントにいい映画だと思います。
<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=htsmknm-22&o=9&p=8&l=as1&asins=B00130HI74&fc1=000000&IS2=1<1=_blank&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>
例のI drink your milkshake! I drink it up! だね。ハイ。
すごーい、おもしろかった。すばらしい。コレも原作読みたい。
舞台は19世紀末〜1920年代。石油採掘業者のダニエル(ダニエル・デイ=ルイス)はポール(ポール・ダノ)という青年の情報でリトル・ボストンという小さな街の土地を買い占め油井の掘削を始めるが、ポールの弟で牧師のイーライ(ポール・ダノ/二役)はことごとに彼に信仰を強要し、やがてふたりは対立していく。
このハナシがねえ、もう、どうしても、現代のアメリカのいろんな面を如実!!に象徴してるよーにみえてみえてしょーがなかった。
まず石油。アメリカは世界最大の石油消費大国であり、現在のイラク戦争だけでなく20世紀の中東外交はすべて石油の利権のためだった。石油のためなら平気で人を騙したり殺したりするダニエルの人物像は、そんなアメリカのある一面を象徴しているようにみえる。
そして宗教。70年代に比べ飛躍的にキリスト教原理主義勢力が政治力をもつようになったアメリカ。とくに信心深い人が多いといわれるバイブル・ベルトと、レッド・ステイツ=共和党支持者の多い地域は地図上でぴったり重なっている。なにかといえばまるでゲームのルールのように聖書やら神やら原罪やらを持ち出してくる、主体性があるのかないのかわからないアメリカ人のまたべつの面を象徴しているのが、イーライではないだろうか。
他にも、途中で耳が聞こえなくなってしまう息子H.W.(ディロン・フレイジャー)とダニエルとの関係も何やらすごく象徴的に感じる。何を象徴してるのかはネタバレになるので控えますが。
全編ほとんどがダニエルとイーライふたりの生き方の対比になっていて、みればみるほど語り手がいわんとしてることが過激な皮肉に聞こえてくる。
お金がそんなに大切ですか。信仰ってそんなに大切ですか。ふたりが真剣になればなるほど滑稽で、ふたりともムチャクチャ淋しそうにみえてくる。でも本人たちはあくまで必死である。わかりやすいといえばそれまでだし、一貫性のある生き方をよしとするならそれもアリかもしれないけど、みてる限りは全然幸せそうじゃない。彼らは自分のしたいようにしてるだけなのに、なぜか不幸にみえてしょうがない。
だってダニエルはべつに石油採掘という仕事を愛してるワケじゃない。今たまたまお金になるからやってるだけである。イーライだって口でいうほど絶対的に神を信じてるワケじゃない。どーみても周りにありがたがってもらうために預言者のフリをしてるだけである。
そういう人生がどーすれば楽しくみえるっちゅーねん。ありえへんやろー。
本質ではふたりともよく似てたりもする。相手のいうことを聞かないで、とにかく自分の主張ばっかり大声で暴力的に押しつけるだけ。アメリカ人よ・・・。
158分と長い映画だけど、会場けっこう爆笑の連続でなかなか楽しく観れましたです。
なんかホラーみたいなコワイ音楽もたいへん効果的で気に入りました。ストーリーは重いのに重くなりすぎないテイストにうまくまとめてあったのにもたいへん感心しました。
ポールとイーライ兄弟の関係が最後まで謎だったのがネックといえばネックでしたが(多重人格かと思った)、それ以外には気になるところもなかったし、われわれが普段当り前に消費してる石油の産出事業の歴史も勉強になったし、ホントにいい映画だと思います。
















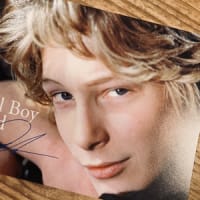



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます