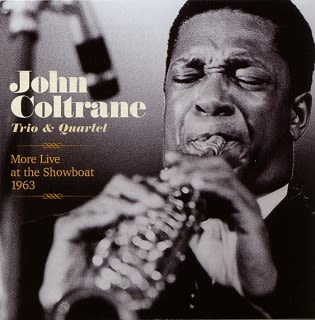■Delaney & Bonnie & Friends On Tour with Eric Clapton (Atco)
まだ8月になっていないのに、この猛暑!?!
全く今年の夏も先が思いやられますが、そんな折に素晴らしいビッグニュースが飛び込んできました。
それは1970年代初頭に大ブームとなっていたスワンプロックの立役者だった夫婦デュオのデラニー&ポニーが作った、その代表作とも言える本日ご紹介のライプ盤が驚きのオフィシャル4枚組CDセットになって登場するという、実に嬉し過ぎる真夏のプレゼント♪♪~♪
先日の連休から出張し、すっかり疲れきって帰ったサイケおやじが、その届いていた注文メールに歓喜悶絶しながら、速攻で返信オーダーを出したのは言うまでもありません。
どうやら発売は月末らしいのですが、そこで待ち切れずに今日は、このアルバムです。
A-1 Things Getting Better
A-2 Poor Elijah - Tribute To Johnson (medley)
A-3 Only You Know And I Know
A-4 I Don't Want To Discuss It
B-1 That' What My Man Is For
B-2 Where There's A Will, There's A Way
B-3 Coming Home
B-4 Little Richard Medley
録音は1969年晩秋~年末に敢行された欧州巡業からイギリスでのライプを収録していますが、そこにはデラニー・ブラムレット(vo,g) とポニー・プラムレット(vo) の主役夫婦以下、エリック・クラプトン(g)、デイブ・メイソン(g)、ボビー・ウィットロック(key)、カール・レイドル(b)、ジム・ゴードン(ds)、ジム・プライス(tp)、ボビー・キーズ(sax)、リタ・クーリッジ(vo) 等々が参加したという裏ジャケットのクレジットだけで、ワクワクさせられますよねぇ~♪
ちなみにこういう編成の豪華ライプが、当時のイギリスや欧州各地で巡業出来た経緯については拙稿「バングラ・デシ・コンサート始末・第5回」前後にも前後にも書きましたが、1969年に新作レコーディングをやっていたデラニー&ボニーと知り合ったジョージ・ハリスン経由でエリック・クラプトンと知己を得たこの夫婦が、ブラインド・フェイスの前座を務めたという流れがありました。
そこで今では有名な伝説になっていますが、当時既に煮詰まり気味だったエリック・クラプトンは前座で大熱演するデラニー&ポニーにショックを受け、ブラインド・フェイスのメンバーとして演奏する自分に嫌気がさしていたというのですが、おそらくはその前座の時と基本的には変わらないと思われるメンバーで楽しめるこのアルバムを聴いていると、さもありなんと納得されます。
しかし告白すれば、このアルバムは我国でも欧米と同じく1970年に発売されていたのですが、サイケおやじはその時から夢中になったわけではありません。それはエリック・クラプトンの参加が明らかにウリになっていたとはいえ、当時の一般的なイメージやサイケおやじの思い込みの中では、エリック・クラプトンはブルース~ニューロックの天才ギタリストであり、未だスワンプロックなんていう言葉が無かった当時、R&Bに分類されていたデラニー&ポニーが白人だった所為で、ほとんど真面目に受け取られなかったのです。
実際、日本では洋楽マスコミの評価もイマイチだったんじゃないでしょうか。
それが翌年末あたりからジワジワとスワンプロックなんていう新発明の用語が使われるようになり、あらためて再発見(?)されたのが、このアルバムだったように思います。サイケおやじが輸入盤のバーゲンでこれを買ったのも、その時期でした。
まあ、狙いはそれでもエリック・クラプトンだったわけですから、ちょいと笑止なんですが、いざ、レコードに針を落としてみれば、重いビートに煽られた熱気溢れる歌と演奏が幸せな観客の拍手歓声とともに繰り広げられる内容は、圧巻!
何気ない煽りの場面からスタートするA面初っ端の「Things Getting Better」から、もうデラニー&ポニーの歌とバンドの演奏は全開モードで、その粘っこいグルーヴは黒人R&Bに近いところから極めて白人ロックに融合した、これは今日でも稀有なスタイルだと思います。間奏で飛び出すエリック・クラプトンのギターも強烈に熱血ですし、カール・レイドルの蠢くベースは鳥肌っ! エキサイトしたポニーの叫び、力強いジム・ゴードンのドラミングも最高です。
また自然体で滲むゴスペルフィーリングが素晴らしい「Poor Elijah - Tribute To Johnson」のメドレーでは左右から絡みまくるギターソロが、おそらくはエリック・クラブンとデイブ・メイソンの仕業でしょうか。
そのデイブ・メイソンの代表曲としてサイケおやじも大好きな「Only You Know And I Know」が、ホーンセクションも入った尚更のスワンプ風味なのも高得点♪♪~♪ 当然なからギターで活躍するのはデイブ・メイソンと書きたいところなんですが、ちょいとエリック・クラプトンに臆しているような気配が残念……。それでも右チャンネルからは何時もながらの三連フレーズを使いまくる作者のギターが憎めませんねぇ~♪ まあ、それよりも、ここはカール・レイドル&ジム・ゴードンのへヴィなリズム、そしてまさにドロドロの泥沼グルーヴを楽しみましょうね♪♪~♪
またAラスの「I Don't Want To Discuss It」が、なんとなくジョージ・ハリスンっぽくなっているのは面白いところで、まあ例の「オール・シングス・マスト・パス」が、このメンツで作られていたことからして、自然の成り行きかもしれませんが、当然ながらグッと黒っぽいのがデラニー&ポニーの真骨頂です。う~ん、エリック・クラプトンのギターがエグイっ! そしてホーンセクションのリフが「寿っ司っ、食いねぇ~~♪」と一緒に歌えたりしますよ。
ですからB面でも粘っこくブルースしてしまう「That' What My Man Is For」が、決してブルースロックになっていないのは時代の証明かもしれません。むしろポニーの歌いっぷりは黒人ジャズボーカルのスタイルに近く、それでいて親しみやすさがあるんですから、これは当時最先端のロックが如何にハイブリットな状態であったのか、今では聴くほどに痛感されます。
そしていよいよのクライマックスは、まさに怒涛のスワンプロック大会!
スタックスサウンド直系の「Where There's A Will, There's A Way」はホーンセクションが咆哮し、ジム・ゴードンのドラミングが強烈無比! それゆえにデラニー&ポニーの歌が火傷寸前ですし、もう、このあたりをライプの生現場で体験したら、発狂するかもしれませんねぇ~♪
あぁ、それなのに、続く「Coming Home」が3本のエレキギターのエグイ絡み、ハードエッジなリズム隊のウネリとホーンセクションやキーボードが作り出す混濁したサウンドによって、それを許しません。もう聴いている自分の魂が何処かへ連れ去られるが如き覚醒と高揚感に包まれるんですよねぇ~♪
その意味でオーラスにR&Rがど真ん中の「Little Richard Medley」をやってくれるのは、本当に世俗に帰った快楽性が満点♪♪~♪ エリック・クラプトンのギターもヤードバーズのライプ盤時代に戻ったような楽しさがありますし、ボビー・キーズも大ハッスルしています。
ということで、今の時期には危険なほど熱いアルバムなんですが、そこに纏わる謎も幾つか残されています。
まず録音データの点から言えば、ジャケットには単にイギリス録音としか記載がなく、B面ラス前のメンバー紹介や挨拶のMCで「ハッピークリスマス」なんていう言葉が出ますから、12月ということは知れるのですが、アルバム全体のミックスにバラツキが散見されることで、幾つかの音源を編集したという疑惑が、これから世に出る前述の4枚組セットでどこまで明かされるのか、楽しみです。
またエリック・クラプトンがこの巡業の折にデラニー・ブラムレットからスライドギターを教わったという説があり、このレコードでは「Coming Home」で聴かれるスライドギターがデラニー・プラムレットと思われますから、そのあたりの謎も解明されるのでしょうか?
しかし、何れにしても、このLPアルバムそのものの素晴らしさが失せることはないでしょう。はっきり言えばアナログ盤特有の団子状の音と音圧が、デラニー&ポニーの暑苦しいまでの魅力と合致しているのです。
それがあえて4枚組CDにされることにより、綺麗にリミックスされるのは余計なお世話だと思いますから、一抹の不安も隠せないのが正直な気持でもあります。
あぁ、またしてもサイケおやじの心配性が出てしまったですねぇ……。
そんなことより、虚心坦懐に楽しむワクワク感を大切にする所存です。
そして、まずはこれを聴きまくります!