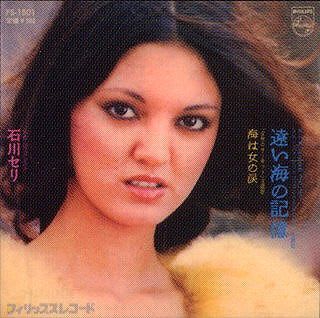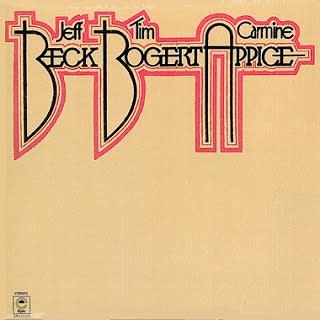■Hey Jude c/w Revolition / The Beatles (Apple / 東芝)
毎年、この時期になると、幾分ホロ苦い気分で思い出す歌があります。
それが本日ご紹介の「Hey Jude」で、言わずと知れたビートルズの超有名曲! そして彼等自らが設立したアップルレコード初のシングル盤として、もちろん世界中でメガヒットを記録し、今日では堂々のスタンダードになっていますが、ジョンとポールの絆がギリギリで切れていないことでも歴史に残るものでしょう。
発売されたのは欧米が1968年8月末、そして我国ではちょいと遅れての9月14日だった事も、鮮明に覚えています。
というのも、この昭和43(1968)年当時のビートルズ人気は、我国においても落ち着いた感じになり、2年前の来日公演をピークとした嵐のようなブームは去っていましたし、肝心のレコードそのものが、なかなか新曲も出ないという状況でした。
そして何よりも例の「サージェント・ペパーズ」や「マジカル・ミステリー・ツアー」の混濁したサイケデリックサウンドが、それまでのミーハー的な人気に終止符を打っていたように思いますが、実際、リアルタイムで洋楽ファンの女の子が夢中になっていたのはウォーカー・ブラザースやモンキーズであり、野郎どもはニューロックやハードロックの世界に耽溺しつつあったのです。
さらにビートルズがこの前に出したシングルヒットの「Lady Madonna」が、今となってはR&Rリバイバルの先駆けと評価もされながらも、リアルタイムでは時代とのズレがあったことは確か……。
ですからサイケおやじも苦しい小遣い状況の中では、ストーンズの「Jumpin' Jack Flash」を買ってしまい、例の事件に繋がるほどだったのです。
そして以降は、優等生への反発からストーンズ命の世界に入るわけですが、さりとてビートルズが嫌いになれるわけもなく、ついに待望の新曲が出るという情報には密かな喜びを抑えきれませんでした。
しかし最初にラジオで聴いた「Hey Jude」には、仰天して???の気分になりましたですねぇ。
実はサイケおやじがそこで接したのは、曲の後半部分、つまりラ~ララ、ラララッラァ~の延々と続くコーラスパートだったのです。
ご存じのとおり、「Hey Jude」はシングル曲にしては7分超の長さがあって、しかも半分以上は、問題の繰り返しコーラスのパートになっていますから、そこだけを3分ほど聴いていれば、当時の常識から、これが歌と演奏の全て!? と思い込まされても不思議はないでしょう。
もちろん時折入ってくるポールのシャウトは確認出来ますが、このコーラスだけのところは本当にビートルズが演じているのか、当時は謎に包まれていたというわけです。
ちなみに今では明らかになっていますが、そのコーラスパートを主に歌っていたのは、集められたオーケストラのメンバーでしたから、あながちの違和感も当然でした。
しかもこの時は、サイケおやじが初体験の「Hey Jude」に対し、ラジオのDJだった糸居五郎が、ウ~ン、サイコ~♪ なぁ~て言ったんですから、完全に取り残された気分に満たされましたですねぇ……。
ところが同じ番組内で続けて流されたB面曲「Revolition」には、溜飲が下がりました!
如何にもジョンらしいヒネリの効いたハードロックで、しかもビートルズならではのポップなフィーリングがパワフルに演じられていたのですから、たまりません。
当然ながら、この時点では、どうして「Hey Jude」がA面扱いなのか理解不能でした。
以上は、今となっての笑い話です。
サイケおやじにしても、直ぐに「Hey Jude」の最高にハートウォームなポップソングの真相に遭遇し、忽ち魅せられたのは言わずもがな、B面収録の「Revolition」も最高だったことから、速攻でこのシングル盤をゲットする覚悟を決めたのです。
しかし待ちに待った9月14日になってもサイケおやじには肝心のお金が無く、それでも母親を騙して何んとか金策出来た数日後、手にしたこのシングル盤のありがたさは決して忘れません。
ところが好事魔多し!
なんとレコードを買っている現場を今や天敵となった優等生のガールフレンドに見つかり、「どうしたのぉ? ビートルズは嫌いなったんじゃないのぉ~♪」と、実に皮肉たっぷりに痛いところを突かれ、グウの音も出ませんでした……。
そして以降、またまたクラス内では反主流的な立場が強まるのですが、そこで優しいポールの歌が心に染みたのは言わずもがなでしょう。
それはジョンとシンシアの不仲によって落ち込むジュリアンを励ますために、ポールが意図的に作った応援歌という内容があるにしろ、どうしたんだい、落ち込んじゃって? と語りかけるように歌うポールは、流石に上手いと思います。
ちなみにサイケおやじが洋楽曲の歌詞を自分なりに調べて訳すようになったのは中学に入ってからですが、ビートルズにしても相当に他愛無いと知った初期、あるいは意味不明の言葉が多い中期の歌に比べ、この「Hey Jude」はシンプルにして暖かく、本当に当時の自分にはジャストミートでした。
ということで、人生には応援歌も必要というのが、本日の結論です。
最後になりましたが、冒頭で述べたように、このシングル盤はアップルレコードからの第一弾という事ながら、東芝からの日本盤には依然として「Odeon」のレーベルが使われている謎について、なんと両社の契約は年末だったという事情があったようです。
このあたりが今となってはマニアックな部分として、「Odeon」と「Apple」の両方のレーベルを集めるのが本筋とされていますが、なんか罪作りですよねぇ……。
そしてサイケおやじとしては、楽曲の方に思い入れが強いシングル盤なのでした。