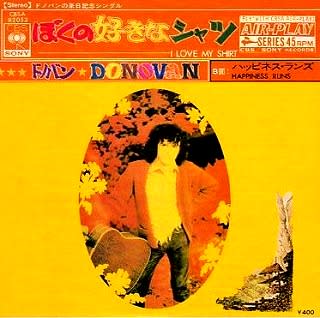■コーラとアメリカ人 / The Byrds (Colubia / CBSソニー)
アメリカの文化に毒されて育ったサイケおやじにしても、コーラを初めて飲んだ時の違和感、あのミョウチキリンな味には、ど~しても馴染めませんでした。
まあ、これは現在でもあまり好きではないんで、本質的にはサイケおやじの体質と相容れないものがあるのかもしれませんが、それにしても子供時代は、こんなん飲んでるアメリカ人って!?!?
そういう気分が大勢を占めていましたですねぇ。
しかし確かにコーラはアメリカを代表する文化のひとつであるらしく、それはアメリカを揶揄する対象になっている事からも明確です。
例えば本日ご紹介のシングル曲「コーラとアメリカ人 / America's Great National Pastime」は、アメリカを代表するロックバンドであったバーズが、その末期の1971年に発表した名盤アルバム「ファーザー・アロング」に収録されていた、中ではちょいと浮いた感じのトラックだったんですが、逆に言えば風変わりなキャッチーさがある所為でしょうか、メンバーの意向よりはレコード会社の思惑優先でカットされたと言われている問題作!?
もちろん原題と異なり、露骨にコーラを用いた邦題は歌詞の内容に由来するものです。
アメリカの偉大なる国民的な文化は
コーラを飲んで 煙草を吸って
野球をやって
とにかくコーラの偉大な味は
プレイヤーも 嫌なやつも
みんなをリフレッシュさせる
等々云々と、かなり皮肉っぽく歌っているのは、明らかに社会風刺という事でしょう。
しかも原詞の中には、はっきりと「Coke」なぁ~んて商標が出ているんですから、いやはやなんとも……。
ちなみに当時のバーズのメンバーはロジャー・マッギン(g,vo)、クラレンス・ホワイト(g,vo)、スキップ・バッテン(b,vo,key)、ジーン・パーソンズ(ds.g,b,key,vo,etc) という、なかなか手強い面々が揃っていましたし、この曲を含むレコーディングセッションはバーズ自らのプロデュースよって完成されたというのですから、ひとつの充実期だったと思います。
それは同時期に残されているライプ音源の勢いが今日でも高い評価を維持している事に加え、率先してカントリーロックという新しい流行を作り出さんとする意気込みは侮れません。
実際、この「コーラとアメリカ人 / America's Great National Pastime」にしても、白人ブルーグラス風の演奏を巧みなロックフィーリングに仕上げ、また前述した皮肉っぽい歌詞をスカッとやってしまうあたりは、なかなか気が利いているんじゃ~ないでしょうか。
ただし、残念ながらヒットはしていませんし、結果的にバーズが解散への道を選んだ、そのきっかけのひとつになったと言われるほど……???
う~ん、なかなか音楽業界も儘なりませんねぇ。
ということで、何時しか馴染んでしまったコーラの味も、それがアメリカでは「文化」になっている事を知ったのは相当後年でしたから、この歌の内容もなかなか理解していたとは言えません。
しかし結果的にバーズが逸早く指向していたカントリーロックが、1970年代のウエストコーストロック、あるいはアメリカンロックそのものの雛型であった事実と同じく、アメリカにおいても最初っから決して馴染んでいたとはど~しても思えないコーラが、アメリカの食文化を代表してしまう事になろうとは!?
ちなみにコーラばかりではなく、似たような炭酸飲料は糖分過多ということで、ダイエット系の同種同類が出たり、地域によってはラージサイズの販売が禁止されたりするんですから、それでも売れるのは何かしらの中毒性があるんでしょう。
もちろん原料は秘密になっているらしいですが、アブナイ薬物と共通する「あれ」が入っているのは、商標からも都市伝説を超越した一般常識!?
ただし、そこまで言うなら、バーズに中毒した方が健全だと思うばかりです。