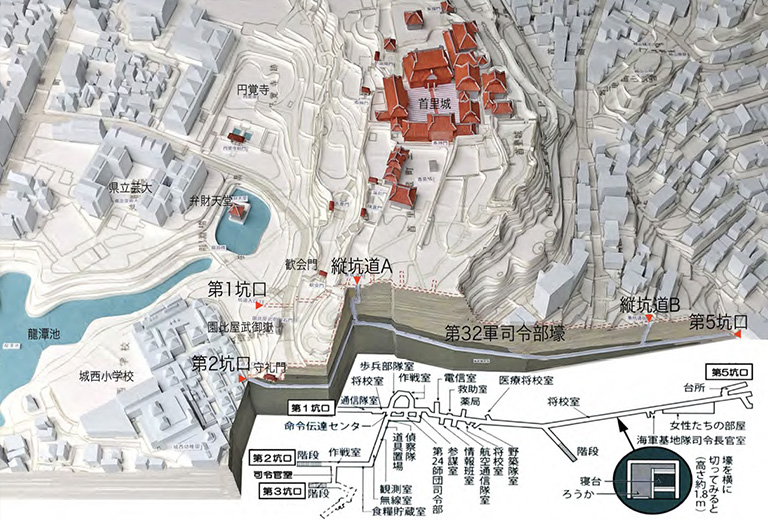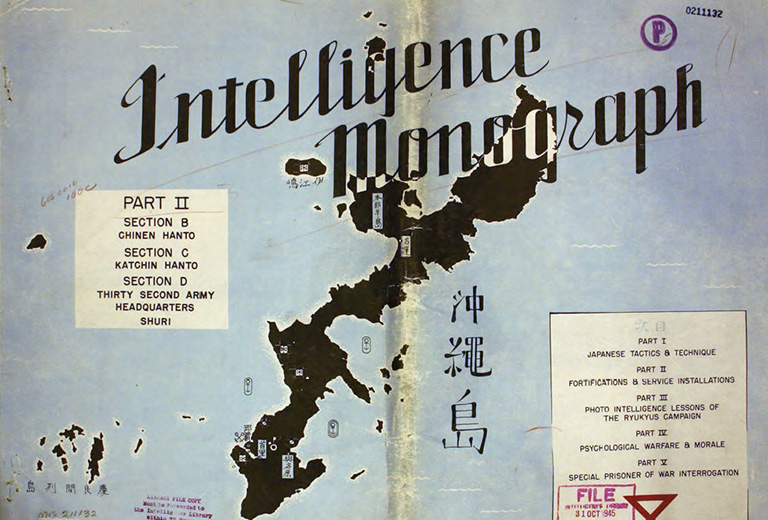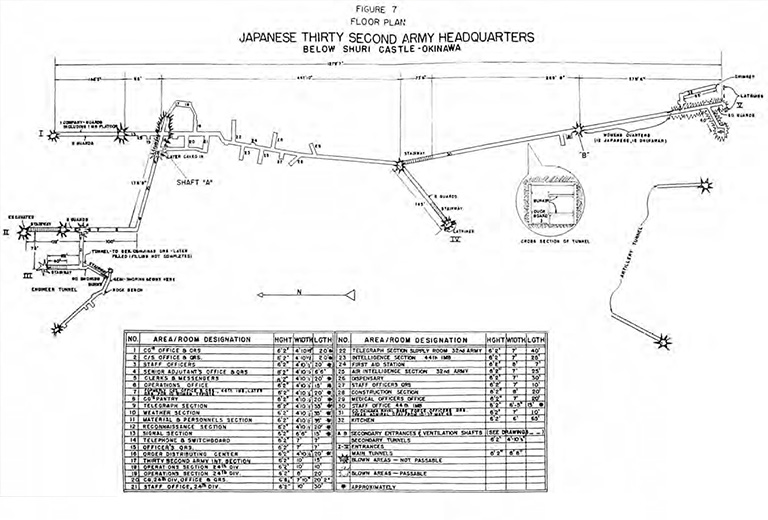【社説・01.01】:沖縄戦終結80年 生きた足跡たどる旅を
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【社説・01.01】:沖縄戦終結80年 生きた足跡たどる旅を
「出てきなさい。もう戦争は終わりました」
米兵の呼びかけに応じて投降した兵隊や民間人の中でも、とりわけ痛ましい印象を与えたのは、老人や女性、子どもの姿だった。
不衛生な壕生活からくる、むせるような体臭。負傷した傷口からは膿(うみ)があふれ、ウジがわいていた。
女性は赤ん坊を背中に、家財道具を頭に乗せ、その上、老人や子どもをかばうように壕から出てきた。
投降した人々は将兵と民間人に分けられ、本島中北部の収容所に収容された。それぞれの「戦後」がここから始まる。
早々と小学校が開校された地域もあれば、依然として交戦状態にある地域もあった。「戦場」と「占領」と「復興」が混在する混沌(こんとん)とした社会が生まれていた。
米軍が設置した孤児院には栄養失調でやせ細った幼い子どもたちが収容されていた。家族を失った孤児にとって戦後は新たな苦難の始まりでもあった。
あの沖縄戦が終わってから今年で80年。1945年以前に生まれた世代は、県人口の1割を切ったと推計される。
沖縄は今、大きな転換期を迎えている。
■ ■
本土決戦に向けた時間稼ぎのための「捨て石」とされた沖縄は、戦後、米軍によって「太平洋の要石」と位置付けられた。
50年6月、朝鮮戦争が起きると、グアムや米本土から米爆撃部隊が沖縄に移動し、B29が嘉手納基地から朝鮮半島に飛び立った。
伊是名島生まれのいれいたかしさんは著書『沖縄人にとっての戦後』(朝日新聞社刊)で書いている。
嘉手納基地を離陸したB29が「島の上空で編隊を整え、北の方へと出撃するのを見上げる日々が続いた」。
やがて、いれいさんは嘉手納基地を次々に離陸し、南へと出撃するB52爆撃機を目にすることになる。B29からB52へ。
沖縄はベトナム戦争の出撃・補給・訓練を担う最も重要な拠点となっていた。
復帰を控えた70年に再刊された『鉄の暴風』(沖縄タイムス社刊)で、著者の牧港篤三さんは「20年後のあとがき」を書いている。
「戦車の放列(野積み)をみると、20年という時間の経過は感じられない」 沖縄では、戦争が過ぎ去った過去の出来事として完了することがない。
生活の場が砲弾の飛び交う戦場となり、戦後は基地と隣り合わせの生活。米軍による事件事故や爆音に接するたびに、沖縄戦の記憶がよみがえる。
惨劇を目撃したり経験したことで心に深い傷「トラウマ」を負い、長い時間がたってから晩発性のストレス症状を訴える人もいる。
基地によって日常生活が脅かされるようなことがない当たり前の暮らしは、いつになったら実現するのだろうか。
■ ■
72年5月15日の復帰は、講和条約によって米国が行使していた施政権を日本政府に返還する代わりに、基地の自由使用を確保するというものだった。
憲法でうたわれた地方自治の原則は、しばしば骨抜きにされ、基地維持が優先されてきた。
今や、反中感情の高まりを反映して沖縄の要塞(ようさい)化を当然視する空気が特に本土で広がっている。
昨秋、実施された日中共同の世論調査によると、日中双方で9割近い人が相手国に対して「良くない」印象を持っていることが分かった。
ネット上では「沖縄ヘイト」と呼ばれる差別的で排他的な投稿が絶えない。
人は安全への脅威に敏感だ。政府が進める日米一体化による抑止力の強化は、安全への脅威を前面に掲げているため国民に受け入れやすい。
県内の政治対立、世代間の分断も深まっている。
だが、対話の努力を欠いた「抑止」論は、緊張を高め、軍拡を招くリスクが高い。
直面するさまざまな隘路(あいろ)に向き合い、一歩でも二歩でも状況を前進させる年でありたい。
歴史を掘り起こし、先人の苦労に学ぼう。そこに泉がある。
人々の尊厳や人権が守られ、自治・自立の気風を世代を超えて共有していくような一年でありたい。
元稿:沖縄タイムス社 朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【社説】 2025年01月01日 04:01:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。












 </picture>
</picture>

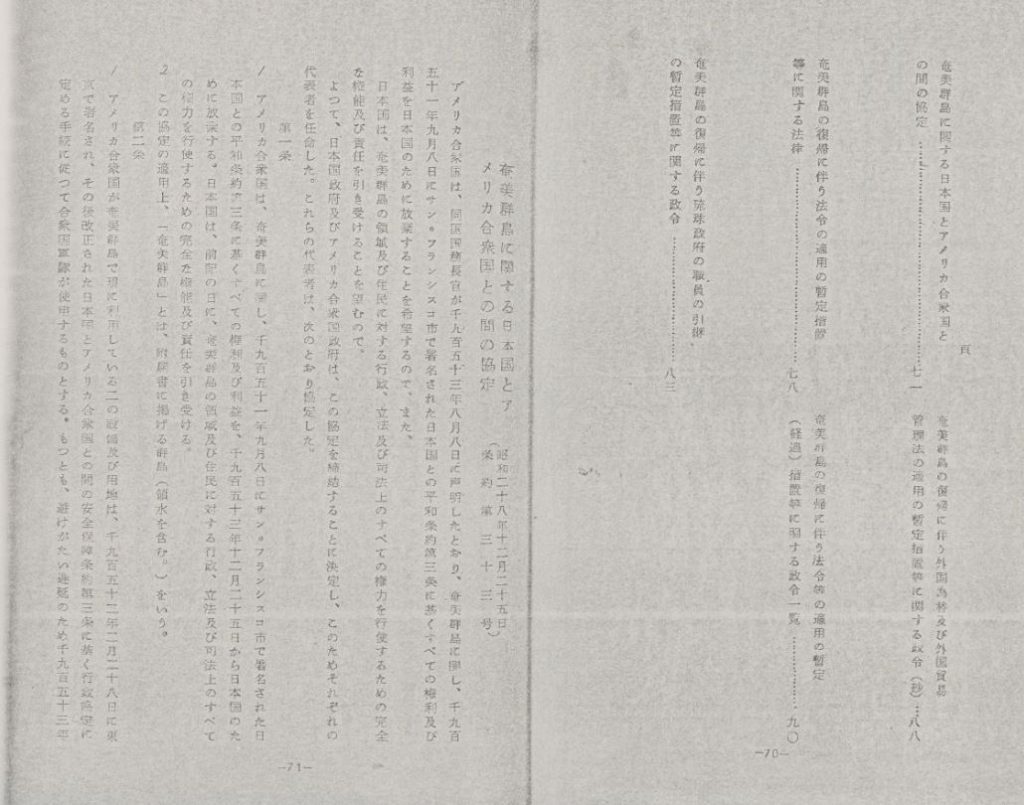

 </picture>
</picture>
 </picture>
</picture>