【経済ニュースの核心】:特殊詐欺対策で注目のATM引き出し額「制限」…“線引き”めぐり警察庁vs金融機関でせめぎ合い
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【経済ニュースの核心】:特殊詐欺対策で注目のATM引き出し額「制限」…“線引き”めぐり警察庁vs金融機関でせめぎ合い
自分の預金がさらに引き出しにくくなるかもしれない。「現在、ATMから現金を引き出せるのは1日当たり50万円までですが、さらにその額が少なくなる可能性が高くなっています」(メガバンク幹部)というのだ。ただし、制限されるのは高齢者のみ。なぜなら高齢者を狙った特殊詐欺が急増していることを受けた、やむを得ない措置だからだ。
振り込め詐欺などの特殊詐欺は急増している。2023年の特殊詐欺被害件数は1万9038件で前年に比べ8.4%も増加した。被害額は前年比22%増の452億円まで膨らんでいる。危機感を強めた政府(警察庁)は、犯罪収益移転防止法施行規則を改正し、高齢者のATMでの振り込みや現金引き出し制限を強化しようとしている。問題はその線引きだ。
 </picture>
</picture>
「警察庁は8月に、全銀協でATMを使用した特殊詐欺対策に関する説明会を開き、65歳以上の顧客のATMでの1日当たりの振込額と引き出し額を、それぞれ20万円以下に制限したいとの考えを示した」(同)という。これに対して、金融機関側は、「65歳以上というのはあまりに年齢が低すぎるし、引き出し額20万円も低すぎる」と反発している。「ATMが利用できない顧客が窓口に流れてくることが予想され、対応ができなくなる事態も想定される」(同)というのだ。
なかでも危惧されるのが偶数月の年金支給日での対応だ。「年金受給については、窓口ではなくできるだけATMの利用へ誘導しているが、20万円を超える2カ月分の年金をまとめて引き出す高齢者は少なくない。そうした顧客が窓口に押し寄せれば、営業店の事務は爆発しかねない」(同)と懸念されている。
メガバンクなど大手行では、こうした顧客は1日に数万件に上る可能性もある。
警察庁では、ATMでの振り込み、引き出し額を20万円以下に制限すれば、特殊詐欺の9割以上は防止できると見込んでいるが、顧客利便性を制限することに金融機関は及び腰だ。「少なくとも制限対象は75歳以上に、振り込み、引き出し制限額は30万円以下に引き上げてほしい」(同)と要望している。
はたしてどこで「線引き」されるのか、注目される。
銀行・証券・保険業界などの金融界を40年近く取材するベテラン記者。政界・官界・民間企業のトライアングルを取材の基盤にしている。神出鬼没が身上で、親密な政治家からは「服部半蔵」と呼ばれている。本人はアカデミックな「マクロ経済」を論じたいのだが、周囲から期待されているのはディープな「裏話」であることに悩んで40年が経過してしまった。アナリスト崩れである。
■関連記事
元稿:日刊ゲンダイDIGITAL 主要ニュース マネー 【トピックスニュース・連載「経済ニュースの核心」】 2024年11月16日 06:00:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。













 </picture>
</picture> </picture>
</picture>
 </picture>
</picture>
 </picture>
</picture> </picture>
</picture>
 </picture>
</picture>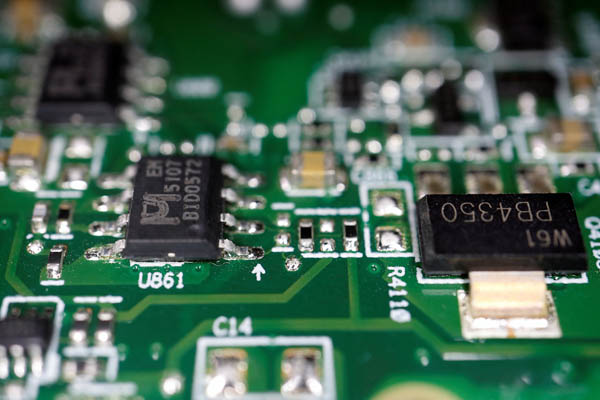 </picture>
</picture>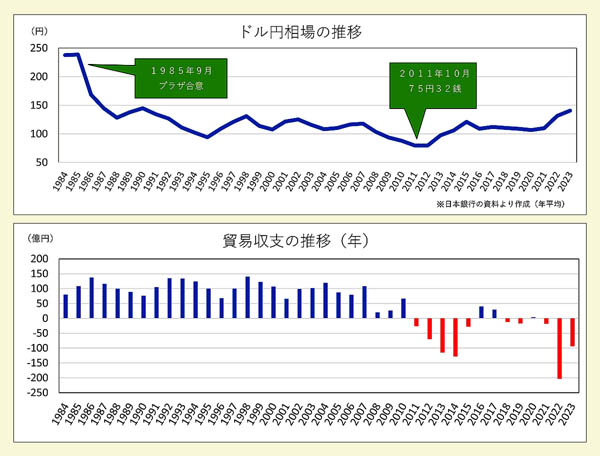 </picture>
</picture> </picture>
</picture> </picture>
</picture> </picture>
</picture>
 </picture>
</picture>



