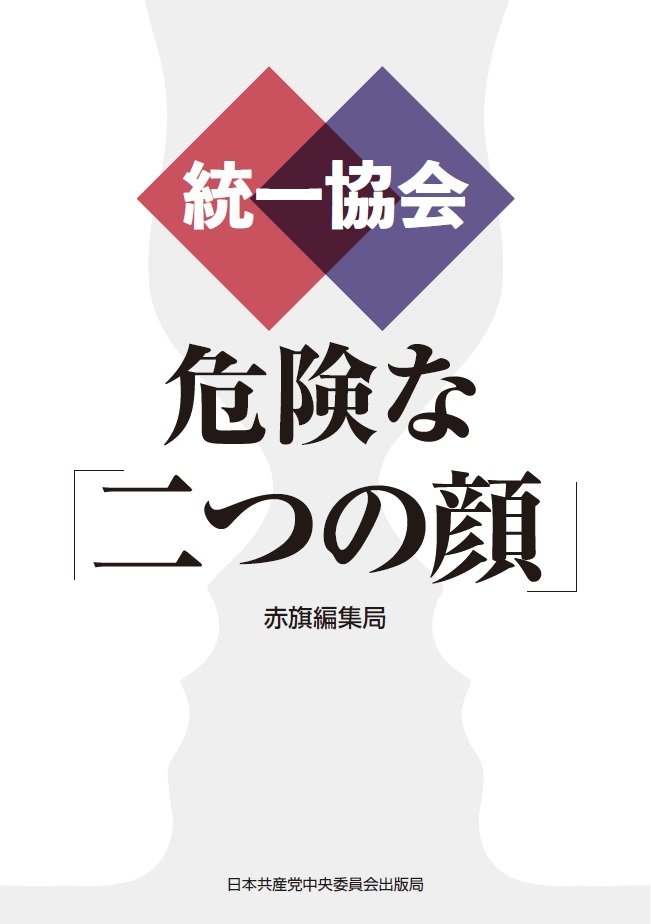【旧統一教会問題】:「脱会には居場所が必要」「オウムの教訓生かされず」 ■鈴木エイト氏×江川紹子氏が語る
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【旧統一教会問題】:「脱会には居場所が必要」「オウムの教訓生かされず」 ■鈴木エイト氏×江川紹子氏が語る
元首相への銃撃事件を機に広く明るみに出た世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の問題。家庭を破綻させるほどの多額の献金、宗教法人の解散命令の是非、適切に養育しない「宗教二世」問題など複数の論点が持ち上がり、政府も対策に動き出した。そこで、オウム真理教事件など長く宗教問題を追ってきた江川紹子氏と今回の旧統一教会問題で圧倒的な取材を見せてきた鈴木エイト氏が、被害者の救済に向けた今後の課題を語り合った。(文:ジャーナリスト・森健、撮影:長谷川美祈/Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部)<button class="sc-kTCxmr ZvCze" data-cl-params="_cl_vmodule:detail;_cl_link:zoom;" data-cl_cl_index="41"></button><button class="sc-kTCxmr ZvCze" data-cl-params="_cl_vmodule:detail;_cl_link:zoom;" data-cl_cl_index="41"></button>
◆「解散命令請求のために質問権」は適度な提言
文化庁は11月22日、解散命令請求を視野に入れ、「質問権」を行使。旧統一教会に対し、教団の管理運営、財産・収支の状況などが確認できる資料の提出を求める書類を送付した。背景にあるのは、10月17日、消費者庁で行われてきた「霊感商法等の悪質商法への対策検討会」が出した報告書だ。同報告書の発表直後、岸田文雄首相は質問権を行使して実態解明を目指すと表明した。<button class="sc-kTCxmr ZvCze" data-cl-params="_cl_vmodule:detail;_cl_link:zoom;" data-cl_cl_index="38"></button><button class="sc-kTCxmr ZvCze" data-cl-params="_cl_vmodule:detail;_cl_link:zoom;" data-cl_cl_index="38"></button>
──消費者庁で行われてきた「霊感商法等の悪質商法への対策検討会」が10月半ばに報告書を出し、解散命令請求にも言及しました。どう評価しますか。
鈴木エイト(以下、エイト) 「解散命令請求をすべき」という提言ではなく、「解散命令請求をするために質問権を行使してください」ととどめたところがよかった。
江川紹子(以下、江川) 報告書の提言として“加減”をよくわかっていたのがいいですね。こういう報告書は強すぎる主張になると逆に実現性が乏しくなる。今回は、ほどよく背中を押した。
──質問権の行使に際しては、所管の文化庁だけではなく、他省庁からも応援が入りました。
 </picture>
</picture>江川紹子(えがわ・しょうこ):ジャーナリスト。1958年、東京都生まれ。早稲田大学政治経済学部卒。神奈川新聞社を経て、独立。1989年オウム真理教の問題をいち早く取材。著書に『「オウム真理教」追跡2200日』ほか多数。1995年、菊池寛賞受賞
エイト 国税庁、金融庁、警察庁、そして法務省から2人ずつ8人。
江川 応援が入ったのは、事実関係で証拠を固める仕事の人たちですよね。そこで証拠を集めて、相手に突きつけて説明させるわけでしょう。ただ、あの団体でお金に関して難しいのは、信者が外国にお金を持っていってしまうところです。
エイト 日本の宗教法人から韓国の宗教法人の財団に送っているお金と、信者個人が韓国の宗教法人に先祖解怨(かいおん)として直接送っているお金、そして日本の信者が韓国の行事へ参加する際に外為法限度額の100万円を運ばせるとされる3種類があります。この韓国への送金ルートは何らかの不法行為に問えるのではないかと司法関係者から聞いたことがあります。金融庁や国税庁が入ってきているので、教団側の危機意識は高まっていると思います。
◆損害回復には韓国への送金止める仕組みが必要
今年7月に起きた安倍晋三元首相の銃撃事件。その後、旧統一教会の問題が明らかになるなか、主に二つの論点に焦点が当たった。一つは献金被害に遭った人をどう救済するかという議論、もう一つは旧統一教会という宗教法人を解散させるべきかという議論。11月17日に時事通信が発表した世論調査では、旧統一教会に「解散命令を請求すべき」は69.4%で、「すべきでない」の6.9%を約10倍上回った。ただし問題は、法人を解散させても、それだけですべて解決とはならないことだ。
──過去に解散命令が出た団体には、地下鉄サリン事件など複数の殺人事件を起こしたオウム真理教や霊視商法詐欺事件で多額の献金を信者から取り立て、有罪が確定していた明覚寺があります。これらの事例を見ても、重要なのは宗教法人の解散だけではなく、その団体から損害賠償などでお金を取り上げ、団体が存続できないようにすることのようです。
 </picture>
</picture>2018年8月、韓国での合同結婚式の席上の韓鶴子総裁(写真:Lee Jae-Won/アフロ)
エイト 私が得ている情報では、教団の本部がある韓国の財団には数百億円ほどの現金資産があるそうです。もともと、これまで日本の旧統一教会は日本の信者から集めたお金を韓国の財団に年間数百億円も送金してきた。損害賠償も大事ですが、その前に韓国への送金を止めるような仕組みをつくらないと、実質的な損害回復はできないと思いますね。
江川 オウムのケースで言えば、解散命令が出されると、法人解散の手続きをする弁護士の「清算人」という人がつきます。その清算人が財産を差し押さえることを最初にしていたのですが、すぐにオウムが破産したので、「破産管財人」という弁護士に引き継いだ。その破産管財人がいろいろなところからお金をかき集めていった。あの時は特例法をつくって、国や自治体の債権よりも被害者救済を優先することになって、被害者に何回かにわたって少しずつお金を配当していきました。
──とすると、もし旧統一教会に解散命令が出されたとしても、清算人がつくところがスタートになるわけですね。
江川 そう。だから、それまでに教団関係者が(資産を)隠してしまう可能性はありますね。不動産は差し押さえできるとしても、現金資産は隠すのではないでしょうか。
エイト そうした資金が散逸しないようにできないんでしょうかね。
江川 難しいです。現段階で旧統一教会の破産宣告を申し立てても通らないでしょうし、また、かりに1000人の原告で多額の損害賠償請求をしたとして、裁判には時間もかかる。時効もありますしね。<button class="sc-kTCxmr ZvCze" data-cl-params="_cl_vmodule:detail;_cl_link:zoom;" data-cl_cl_index="39"></button><button class="sc-kTCxmr ZvCze" data-cl-params="_cl_vmodule:detail;_cl_link:zoom;" data-cl_cl_index="39"></button>
エイト 不法行為に基づく損害賠償請求は20年で消滅時効になりますね。また、もし法人を解散させても、信者として教義を信じている人は損害賠償請求をしないでしょう。そういう(マインドコントロール的な)問題も残ります。
江川 献金をどう扱うかは、憲法で保障されている財産権に関わるので難しい。たとえば法律で上限を決めたりするのは無理だし、家族の取消権も限定的になるでしょう。
エイト 献金をしている人が正常な判断ができなくなった状態なのか、それを誰がどう判断するのか……。正常な判断ができないと見て、法的に代理人を立てる成年後見制度の話もありますが、第三者が絡むのは難しいですね。
江川 だから、お金に関わる部分に限った立法を急ぐべきではないと思うんです。もっと丁寧にやらないといけない。どんな法制度をつくればいいか、(国会に)委員会をつくって、総合的な見地からじっくり議論してもらいたい。むしろ現行法でできることが複数あると思うので、それを進めてもらうほうがいいと思う。
◆被害者の救済へ 現行法の変更なら「いますぐできる」
国会で進む被害者救済の議論で、寄付をめぐる規制と並んで重視されているのが、信者の子(宗教二世)や配偶者の救済だ。厚生労働省は10月初旬、信仰を理由にしても児童虐待にあたる行為はあると全国の自治体に通知を出した。身体的暴力はもちろん、適切な食事を与えない、あるいは子どもの心を傷つける言動。従来こうした問題は信仰が関わる場合、児童相談所や警察で対応されないことが多かった。立法を待たずしての現行法での対応は注目を浴びた。
 </picture>
</picture>旧統一教会をめぐる問題が明るみに出て以降、支持率が低下し続けている岸田首相(写真:アフロ)
江川 厚労省の今回の判断は早かったし、よかった。こういう現行法を使ってできることで一定程度進めるのがいいんです。現行法でできる対策はほかにもあって、たとえば文部科学省では「高等教育の修学支援新制度」というのがある。経済的な理由、あるいは父母等による暴力等の理由で、学業を続けられないという人向けの支援。給付型の奨学金や授業料の減免などがあるんです。この「暴力等」の「等」に、宗教による虐待を入れればいい。
エイト たしか、いま知り合いの社会福祉士がその制度をうまく使って、カルトの二世の子たちを学校に行かせるようにしていたと思います。
江川 そうですね。でも、制度は十分ではなかった。従来は春か秋か、適用できる時期が決められていたからです。でも今年7月に、いつからでも使えるようになったそうです。現行法の変更で救える人たちがいるのなら、全省庁で見直してほしい。いますぐできるのですから。
エイト そうですね。学費、生活保護はもちろん未成年の場合だと児童福祉法もありますね。それなら「二世のシェルターを新たにつくって」という話より早い。<button class="sc-kTCxmr ZvCze" data-cl-params="_cl_vmodule:detail;_cl_link:zoom;" data-cl_cl_index="38"></button><button class="sc-kTCxmr ZvCze" data-cl-params="_cl_vmodule:detail;_cl_link:zoom;" data-cl_cl_index="38"></button>
江川 そうです。以前は18、19歳の子だと児童福祉法を離れて、しかも未成年という空白があり、行き場がない子がいた。でも、今年4月の民法改正で18歳から成人となったので、18歳になれば家を出て、生活保護や社会福祉士などにつなげることができますからね。もちろん、それをやりながら不十分なところは、新たな制度を考えていく。
エイト 子どもの声を聞き、支援をする「子どもアドボケイト(代弁者)」と呼ばれる人たちも出てきていますし、苦しむ二世がそういう支援員の働きで助けられることもあると思います。
◆まずは理念法から…「カルト教育は心のワクチン」
──他の宗教についてはどうでしょうか。 江川 もちろん関係します。例えば「エホバの証人」では、ムチでたたかれるなど体罰をされた事例がたくさん報告されていますが、これは現行法では児童虐待防止法が適用できるケースがある。
エイト ただ、家庭や信仰のコミュニティの中で行われているとその虐待が見えないし、子どもも声を上げられない。そういう子に気づいてあげられるようにできるかが課題です。
江川 例えば、エホバだと信仰上、七夕などの催しや運動会の騎馬戦に参加しないなどの特徴があり、先生も気づきやすい。そういう子は特に注意して、虐待がないかどうか見てほしい。家庭でのムチの体罰は、子どもが「それが当たり前」として育つので、本人もおかしいことだと気づかない場合がある。
 </picture>
</picture>脱会者にとって社会での居場所が不可欠だとともに語った鈴木エイト氏と江川紹子氏
──そうした宗教を規制するために、フランスの「反セクト法」のような法をつくったほうがいいという声もあります。同法は、身体や精神の不法侵害、無知や脆弱な状態につけ込む不法侵害(マインドコントロール)などで有罪判決を複数得ると解散となる条件が掲げられました。こうした規制についてはどうでしょうか。
エイト 私は日本版反セクト法があったほうがきっちり縛れるかなと思いますね。フランスでも一つ一つ事例を積み上げて、「この団体はこういうことをしている」と団体を縛っていった。解散までいった団体はないようですが。
江川 私は、まずは罰則を伴わない、いわば理念法から始めたらいいんじゃないかと思うんです。例えば、ヘイトスピーチ対策法も理念法で直接の罰則はない。ただ、理念法であっても法律があると、それに基づいた啓発活動、社会活動が生まれる。必要であれば、この理念に基づいて、川崎市のように自治体が条例をつくることもある。そういう啓発活動ができれば、歪んだ教えとか、問題行為につながる教えを信じてしまうような人を減らせるんじゃないかと思います。 <button class="sc-kTCxmr ZvCze" data-cl-params="_cl_vmodule:detail;_cl_link:zoom;" data-cl_cl_index="38"></button><button class="sc-kTCxmr ZvCze" data-cl-params="_cl_vmodule:detail;_cl_link:zoom;" data-cl_cl_index="38"></button>
エイト たしかに理念法すらなく、何も法規制がなかったことで、旧統一教会は「一世代」分放置され、被害を受ける人が増えてしまったわけですよね。
江川 「カルト教育は心のワクチン」と私は言っているんですが、そういう体験をした人の話を聞いたら、自分がそういう考えの人に接したときに理解できると思うんです。
エイト カルト教育をすることで、現役信者の子への偏見もなくなる方向にもっていかないといけないですね。いま旧統一教会の二世はひどくいたたまれない感じですから、かわいそうなんです。
◆教義の世界よりリアルを体感できる恋愛の力
──そうした信仰の人たちを排除すると、もっと悪い方向に進んでしまうのでは。社会としては、どう接するべきでしょうか。
江川 オウムのときには省庁連絡会議ができて、それに付随した研究会ができたんです。警察庁、厚生省(現厚生労働省)、法務省、それと心理関係の専門家などが参加した。その総括報告書があるのですが、その中に脱会者のケアの話は随分たくさん書かれているんです。カルト研究センター(仮称)を設けるという提言も書かれていたし、カルトの問題は宗教の問題ではなく、人権問題、犯罪問題、消費者経済問題でもあると書かれている。
エイト ちゃんとしたことが書いてあるんですね。でも、その後、その総括報告書は生かされなかった?
江川 そうなの。予防啓発活動を積極的に行うことでカルト会員に対する抵抗力をつけるとか、心理相談、社会復帰施設ではカウンセリングが重要だとか、情報集約のネットワークを構築するとか、すごく重要なことが書いてあるんです。でも、いまは国立公文書館に眠っている。
エイト これをたたき台にすれば、旧統一教会問題の対策にも使えますよね。そもそも国の報告書がこうした団体を「カルト」と記載していることも重要です。旧統一教会はカルトという言葉はヘイトスピーチだといま言葉狩りをしようとしているんですが、はるか前に「カルト」という言葉が国の機関で打ち出されていた。<button class="sc-kTCxmr ZvCze" data-cl-params="_cl_vmodule:detail;_cl_link:zoom;" data-cl_cl_index="38"></button><button class="sc-kTCxmr ZvCze" data-cl-params="_cl_vmodule:detail;_cl_link:zoom;" data-cl_cl_index="38"></button>
──信仰を持つ人たちが脱会しようとするとき、社会はどう受け止めるべきでしょうか。
エイト 脱会は「居場所」の問題なんですよね。教団の輪の中から出ようとしても、社会の中に居場所がないとまた戻ってしまう。脱会しようという人が駆け込める受け皿が必要だと思います。
江川 教団の価値観と現実社会の価値観。その人にとって、どっちがリアルに感じられるかがポイントだと思う。そこですごいのが恋愛の力です。教団の価値観に強力に染まっていた子が、あるとき外部の世界で好きな子ができると、急に教団をやめたりする。
──ある人を心から信じて、信じられる。そのことで教団の価値観から解放されると。
江川 好きな人ではなく、友人であることもあります。マニュアル化はできないですが、心が揺さぶられて、教義の世界よりリアルな感覚を体験する効果は大きいように思います。
エイト わかります。この間話したエホバを脱会した二世の子は、「社会に出て全然うまくいかなかった、けれどバイト先のコンビニの店長が何を言っても信用してくれた」と。その人に救われたということを言っていました。この人なら自分を信用してくれるという感覚を持つことができれば、現実社会に拠り所ができていくんだと思います。
江川 だからこそ、一般の人にカルトの人を受け入れるための啓発活動が必要なんです。差別や非難ではなく、受け入れる。そうすることで、こちらの価値観も伝えていける。
エイト そうなると、さっきの理念法のようなものが、やはり必要ですね。7月の事件はカルト団体の二世が起こしたというより、国がカルト問題を放置してきたがゆえに起きてしまったとも言えます。
江川 地下鉄サリン事件と安倍元首相の銃撃事件と、日本はカルト絡みで2度も世界を驚かすような事件を引き起こすことになってしまった。銃撃事件はもちろん教団の人間がやったわけではなく、あくまでその背景での問題でしたが、2度もです。カルトに対してどう向き合うか、オウム事件の教訓が生かされなかったからですよね。いま旧統一教会の問題に対処せず、カルトの問題を放置したら、また数十年後に後悔するようなことが起きるでしょう。
エイト 旧統一教会だけを対象にしたものではなく、どんな団体にも対応できるような包括的な理念法ができれば、いま団体にいる人も将来的にちゃんとケアできることになる。その理念をしっかり打ち立てられるかが問われていますね。
------- 森健(もり・けん) ジャーナリスト。1968年東京都生まれ。早稲田大学卒業後、総合誌の専属記者などを経て独立。『「つなみ」の子どもたち』で2012年に第43回大宅壮一ノンフィクション賞受賞。『小倉昌男 祈りと経営』で2015年に第22回小学館ノンフィクション大賞、2017年に第48回大宅壮一ノンフィクション賞、ビジネス書大賞2017審査員特別賞受賞。
元稿:Yahoo NEWS オリジナル 主要ニュース 社会 【話題・特集・「旧統一教会を巡る数々の問題」】 2022年12月04日 18:05:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。










 </picture>
</picture> </picture>
</picture>