【本土復帰50年】:沖縄の「今」が始まった1972年5月15日 “沖縄の一番長い日”ドキュメント【WEB限定】
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【本土復帰50年】:沖縄の「今」が始まった1972年5月15日 “沖縄の一番長い日”ドキュメント【WEB限定】
1972年5月15日、沖縄は日本に復帰した。戦後27年続いた米軍統治が終わり、新しい歴史を開いた。復帰運動の先頭に立ち、激動の時代を引っ張った、屋良朝苗知事は新沖縄県発足式典で、「鉄石のような厚い壁を乗り越え、険しい山をよじ登り、イバラの障害を踏み分けてついに」と悲願をかみしめた。以降、沖縄は国の振興策などによって道路や港など社会基盤の整備が進み、県民の暮らしは豊かになった。が、拒み続けた基地は今もなお居座り、穏やかな日々を脅かす。
ドルから円へ、マイルからキロへ、その日を境に人々の生活は大きく変わった。あれほど盛り上がった復帰運動だったのに、当日の県民の反応はお祝いと抗議に割れ、混乱した。沖縄の「今」が始まった一日を振り返る。(敬称略、肩書は当時)
◆1972年5月14日午後10時半すぎ 復帰前夜 事故米兵 身柄で騒然
復帰前夜、沖縄はどしゃぶりの雨だった。
「世替わり」まで1時間ちょっとと迫った14日午後10時半すぎ、米兵が運転する乗用車が那覇市松山の大典寺前で衝突事故を起こした。ぶつけられた車に同乗していた男性が路上に放り出され病院に運ばれた。
間もなく、MP(憲兵)カー3台が赤いライトを点滅させ到着。やじ馬や報道陣ら100人近くが集まり、現場は騒然とした。
「まだ返還前だ」と加害者を連れ去ろうとするMPに、群衆から「あと2時間したら逮捕されるところだ」、罵声が飛んだ。
そのころ琉球政府の屋良朝苗主席は、ランパート高等弁務官夫妻の送別晩餐会の席にいた。高等弁務官はディナーが終わるとすぐに嘉手納基地へ向かった。
見送りのため後を追った屋良主席は、嘉手納基地でその時を迎えた。「あと1分」「あと10秒」。腕時計の針をじっと見詰めた。復帰の瞬間、車はクラクション、船は汽笛を鳴らすことになっていたが、飛行機の爆音がそれをかき消した。
午前0時すぎ、最後の統治責任者で沖縄君臨の象徴だった高等弁務官は見送りの人たち一人一人と握手をし、特別機で沖縄を離れた。
同じころ、宮里松正副主席は、日本武道館で開催される復帰記念式典に出席するため、東京へ向かう飛行機の中だった。集中豪雨のため出発が大幅に遅れ、羽田に着いたころには日付が変わっていた。
「もうこんなものはいらない」と興奮気味にパスポートを提示した宮里に、入国管理官は「結構です。長い間ご苦労さまでした」と道を開けた。
◆15日午前0時 夜明けの沖縄県議会 条例・予算 スピード可決
午前0時を期して屋良は主席から知事選挙までの間の「みなす知事」となった。そして1号線から国道58号へと名前が変わった道路を南に走った。休む間もなく「県庁」へと生まれ変わった行政府ビルで、議案の決裁に追われた。初仕事は「みなす県議会招集告示」の署名。
「県議会」となった立法院ビルでは早朝6時すぎ、第1回議会が招集された。県政のスタートに必要な条例、暫定予算などを可決。与野党の議論もこの日ばかりは「休戦」となり、60件の条例可決に要した時間はたったの30分だった。
市町村でも同じように条例・規則の改正や見直しが行われた。ドルで編成された予算を円に換算し、市税や水道料、窓口の手数料など、市民と関わるすべての条例・規則を改正する手続きだ。那覇市は午前2時に市議会を開会。平良良松市長は、窓口が開くまでに間に合わせなければと夜通し書類に印鑑を押した。
北中城村石平の米軍司令部屋上には、早朝、星条旗とともに日章旗が掲げられた。一方、浦添市の米民政府はゲートが閉ざされ中央ポールから星条旗が外された。変わらなかったのは、米軍機が離着陸を繰り返す嘉手納の爆音。
復帰に伴い配備された自衛隊の基地開設式も各基地で開かれた。那覇空軍基地では午前7時半、ポールに日の丸と星条旗が掲げられ、両国国歌がスピーカーから流れた。
夜明け前に配られた沖縄タイムスの1面の見出しは「新生沖縄、自治へ第一歩」。特集面には日本国憲法全文が掲載された。
◆15日午前10時半 記念式典 厳戒敷く那覇会場
本土政府主催の沖縄復帰式典は午前10時半、東京の日本武道館と那覇市民会館の2会場をカラーテレビ放送でつなぎ、同時に行われた。那覇会場には屋良知事ら県側の代表、山中貞則総務長官ら本土政府代表、ピートリー在那覇総領事など約1500人が出席した。
屋良は、大事な式典に招待客が皆出席してくれるようにと願い、ステージの上から会場に注意を払っていた。しかし県議の席には保守系議員だけが着席、革新系の姿はない。外には「式典粉砕」のビラが張られ、私服刑事が厳戒態勢を敷いていた。
君が代斉唱や佐藤栄作首相の式辞、戦没者と復帰を待たず亡くなった人たちへの黙とう、天皇陛下の「おことば」までは、東京からテレビ中継された。
その後、沖縄の式典に移り、屋良知事は「復帰の内容は、必ずしも私どもの切なる願望が入れられたとはいえない」と、基地の「核抜き・本土並み」が実現しなかった本土復帰を批判。その上で「主体性を堅持し、沖縄が歴史上、常に利用されてきたことを排除して、県民福祉を確立しよう」と強調した。
一方、保守系の星克県議会議長は「米国施政下という不安定な政情ゆえ、ややもすると抵抗に終始して自主建設の責任を没却するなど、もろもろの積弊を改め、日本国民たる誇りと責任の自覚に立ってまい進しよう」とニュアンスの違いをみせた。
午前11時半、山中長官が音頭をとっての万歳三唱で閉会した。
会場の両サイドと後方は、国内外のテレビカメラが並んだ。記者席にはニューヨーク・タイムズや西ドイツ放送協会、ソ連(現ロシア)プラウダ紙の特派員が「世替わり」を報じるため、ペンを走らせた。
◆15日午前9時 ドル円交換 銀行に列 混乱と不安
日本に戻るから、使うお金も日本円に変わる。それまで使っていた米ドルは、当時のレート、1ドル=305円で円に交換された。
通貨交換を担ったのは71年に設置された日本銀行那覇支店開設準備室。当時の担当者によると、沖縄には通貨の統計がなく、交換する円がどのくらい必要なのか分からず、その見積もりが難題だった。
復帰の日に開店する日本銀行那覇支店の堀内好訓支店次長は、新木文雄支店長の「100%沖縄を向いて仕事をしろ」を思い返し、気を引き締めた。
太平洋戦争時、電探士官だった新木は、鹿児島の特攻基地で、大田実中将の「沖縄県民斯ク戦ヘリ…」の打電を傍受したという人物だった。沖縄との不思議なめぐり合わせが、住民の利益を最優先にという言葉につながった。
日銀那覇支店は、さまざまな想定を重ねてドルの流通量が1億ドルで、為替レート(360円)を当てはめ計算。さらに50%の余裕をもたせ約540億円を準備することになった。
復帰2週間前の5月2日、大量の円を積み込んだ海上自衛隊の輸送艦2隻が那覇港に接岸した。琉球警察の護衛で那覇支店へ運び込まれた。外部には知らされない極秘のミッションだったという。
5月15日午前9時、日銀那覇支店が正式に産声を上げた。同時に、県内189の交換所で一斉に通貨交換が始まった。
琉球銀行本店では午前6時、交換所となる支店へ現金輸送が始まった。午前中は雨のためかさほど混雑はなかったが、午後から一転、客があふれ、長蛇の列ができた。閉店の午後4時をすぎても列は途切れない。「もっと速くできないのか」。いら立つ客の声が響いた。
通貨交換は5月15日から20日まで続いた。交換所は、大勢の人でごった返し、世代わりの節目を象徴した。
庶民にとっての「世替わり」はドルから円への切り替えであり、混乱と不安のスタートでもあった。ドルの価値が低下する中での円への交換は、資産縮小や物価の高騰を伴った。経済不安から、買いだめに走ったり、預金を引き出し物に変える動きも。
交換された総額は米ドルで約1億ドル、円では315億円以上となった。
◆15日午前 特設授業 「変わらぬ現状」立ち上がる生徒
県内の小中高校では復帰を考える特設授業がもたれた。教職員らは、すでに復帰記念のメダルを生徒に配らないことで、反対の意思を示すことを決めていた。
与那城村の宮城小中学校で教壇に立つ安慶名つる子教諭は、いつもの朝と同じように宿舎から学校に向かった。特別な感慨はない。むしろ施政権が返還され何も変わらない現状に怒りがこみ上げてきた。
朝のホームルーム、児童に復帰について話した。「米軍基地は残る。悔しい」「本当の平和憲法のもとに返らなければ」。子どもたちからも「おかしい」「自衛隊には反対」と反応があった。
この日、学校は午前中で授業を終え、先生たちは那覇で開かれる抗議の県民大会に参加した。「先生、頑張ってきて」。児童から激励を受けた安慶名は、前日に手配していた船に乗り込み島を後にした。
そのころ、知念高校で社会科を教えていた平良宗潤教諭も、抗議大会に向けた校内の決起集会に参加していた。
1966年の首里高勤務時に始めた「4・28」「6・23」を考える統一ホームルーム。これが後に、全県的に取り組まれる「特設授業」の原型となった。
校内集会後、バスで那覇に移動。「生徒の政治活動参加は認めない」との国の指導はあったが、希望する生徒と一緒に向かった。
夕方、国際通りをデモ行進。生徒も自主的に加わった。平良ら教員は子どもたちを守るように隊列の外側を固めた。先生も生徒も一つになり抗議のシュプレヒコールを上げた。
◆15日午後3時 1万人抗議集会 雨の中「完全復帰」要求
明暗同居した一日だった。
復帰式典のあった那覇市民会館に隣接する与儀公園では、午後3時から復帰協主催の5・15抗議県民総決起大会が開かれた。労働組合員や学生ら約1万人が結集。降りしきる雨の中、会場は色とりどりの傘で埋め尽くされた。米軍基地存続と自衛隊配備、1ドル=305円での通貨交換など、県民に新たな差別を強いる返還は「沖縄処分」と訴えた。
桃原用行復帰協会長は「米国の施政権返還は県民の闘いの成果。だが米軍の基地機能を存続させた上に自衛隊を配備し、県民意思を無視した」と糾弾。軍事基地撤去と安保廃棄による完全復帰を実現する闘いに向け連帯を呼び掛けた。
式典では喜屋武真栄参院議員、瀬長亀次郎人民党委員長、上原康助社会党県本委員長らが演説。その訴えは暗い雨空に拡散していった。
石川元平沖教組総務部長は「完全復帰を目指す新たな闘いの始まりの日だ」と思いを新たにした。
南風原村職労の神里良光、妻で宜野湾市職労のヨシ子は「復帰自体は喜ばしいが、米軍基地が残った怒りがあった。沖縄の基地がいつかなくなる日が来ると信じて…」。
地面には水がたまり、全ての人が立ったまま、ずぶぬれだった。
午後4時50分、参加者は通りを泥で赤土色に染めながら、与儀公園から県庁前までデモ行進した。拡声器からは「復帰を迎えたが、この空のように県民の心は鉛のように重い」との叫び。
国際通りに立てられた復帰祝賀の日の丸はデモ隊の学生らによって倒された。
■参考文献
屋良朝苗著「激動八年 屋良朝苗回想録」(沖縄タイムス社)、同「屋良朝苗回顧録」(朝日新聞社)、宮里松正著「復帰二十五年の回想」(沖縄タイムス社)、同「復帰秘話 極秘の通貨確認作戦」(復帰秘話刊行会)、平良良松著「平良良松回顧録 革新市政16年」(沖縄タイムス社)、福木詮著「沖縄のあしおと 1968―72年」(岩波書店)、櫻井溥著「沖縄祖国復帰物語」(大蔵省印刷局)、沖縄県祖国復帰闘争史編纂委員会「沖縄県祖国復帰闘争史」(沖縄時事出版)、「戦後沖縄経済史」(琉球銀行)、「琉球銀行35年」(同)、下地宏昌著「1971年10月9日 沖縄県民のドル通貨の確認はこうしてやった」、「海鳴り 15号」(知念高校教職員同人)
元稿:沖縄タイムス社 朝刊 主要ニュース 社会 【話題・本土復帰50年】 2021年05月15日 05:00:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。





















 </picture>
</picture>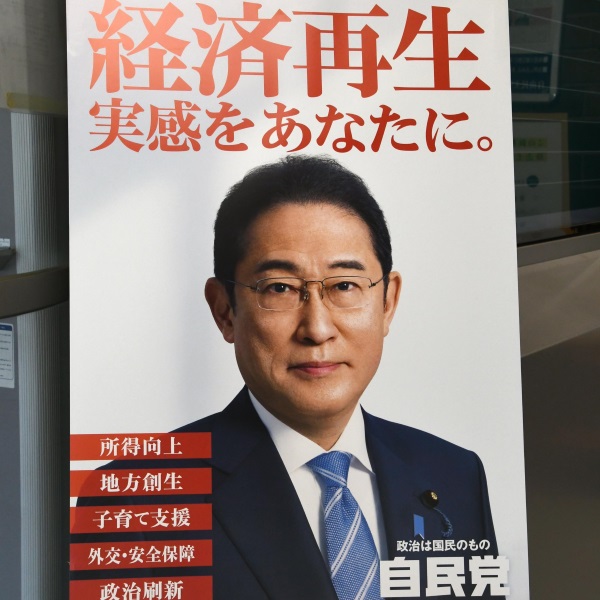 </picture>
</picture> テルアビブ空港乱射事件
テルアビブ空港乱射事件 </picture>
</picture>



