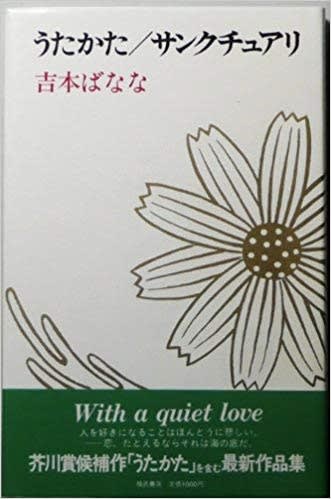
箱根の日帰り温泉を訪ねたら、そこの読書室の本棚にあった一冊。学生時代に読んだ一冊だが、ストーリーは殆ど忘れていた。
2つの短編小説だが、作者のみずみずしい感性を感じる物語だ。現実世界にもみくちゃにされている私のような親父読者には、展開される世界はちょっと別世界すぎるが、学生時代にナイーブな気持ちで物語の世界に投入した若かった自分が思い起こされる。
さりげなく描かれる情景や心情の表現がさりげなく心に刺さる。プロットはさらっと流れるし、表現も難しいものではないが、味わいながら読みたい小説だ。自分が、成長したのか、擦れたのか、わからないが、日々、乾いた企業社会での生活に慣れすぎて、人の気持ちへの感度が鈍っている自分にも気づく。歳を重ねているようで、人間理解や思いやりと言った面では、成長どころか退化しているかもしれないと思ってしまった。
物語そのものへの思いや感想よりも、本作品の読書を通じて、自分自身の振り返りが先に来た一冊となった。















