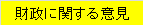大震災と原子炉事故の復興が一向にすすまない。この原因は財源としての増税が確定するまで、一切復興資金をだそうとしない財務省と民主党にある。民主党にたいしては選挙での大敗北によって、財務省にたいしては組織の解体によって、その責任をきっちりとらせなければならない。
2011年11月29日国民を欺く財務省を解体し、予算と税目の決定権を国民の手に取り戻そう。
財務省の操り人形と化した野田ドジョウと民主党は大災害のさなかに必要のない復興増税を強行したばかりでなく、消費税増税、年金支給額の削減と、デフレ促進、景気後退策を強行しようとしている。そもそもバブルの発生、バブル崩壊による景気悪化、その後の回復過程での二度の景気後退の全てに財務省は大いに責任がある。日本が復活するためには、財務省から予算編成権や税目の決定権を取り上げ、予算編成権は内閣総理大臣直轄、税目決定権は内閣府に帰属させ、国民に選ばれた内閣総理大臣が直接コントロールできるよ
うにすべきである。財務省は国税局の徴税権と社会保障の徴収権を合体した歳入省とし、徴収業務だけを取り扱わせることが望ましい。
うにすべきである。財務省は国税局の徴税権と社会保障の徴収権を合体した歳入省とし、徴収業務だけを取り扱わせることが望ましい。