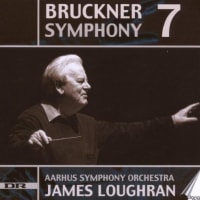大岡昇平(1909‐1988)の「野火」(1952)と「俘虜記」(1949)を読んだわたしは、もう一作読んでみようと思ったが、では、どれにしようかと迷っていたとき、吉田秀和の次のような文章を目にした。
「私は大岡さんの小説では、『俘虜記』『野火』『レイテ戦記』という一連の戦記ものにも大きな尊敬を払っている人間だけれど、それとならぶくらい『花影』を尊重し、大好きで、何度もくり返し読んでいる人間である(ついでにいえば新古典主義的な『武蔵野夫人』より『花影』のほうがずっと好きである)。」(「大岡さんの許しと愛」より)
これを読んで、次は「花影」(1961)にしようと思ったが、それにしても、吉田秀和はなぜそんなに「花影」が好きなのか。上記の引用文の少し後に、次のような文章があるが、
「これも同じく『花影』の大好きな私の家内が、「これは母親に対する愛に源をもっているものかしらね」といいだした。私は途端に、そうかもしれないと思った。」(同)
これを読んでもまだ「花影」が好きな理由ははっきりしない。「母親に対する愛に源をもっている」という指摘が、わたしには唐突な感じがした。だが、それにしても、吉田秀和とバルバラ夫人が「花影」について語り合い、それが好きな理由に大岡昇平の母親に対する愛を見出して頷く。その過程が、何となく微笑ましく、また二人の「花影」に対する想いが伝わってくるように感じた。吉田秀和が「花影」が好きな理由は、わたし自身が「花影」を読み、自分で考えなければならない。それがわかっただけで十分だと思った。
そこで「花影」を読んだわけだが、その感想を一言でいえば、これは追憶の文学だ、というものだった。追憶という言葉にわたしがこめた内容と、吉田秀和とバルバラ夫人が感じたこととが通じ合うかどうかはわからないが。
「花影」の主人公は、戦前、戦後を通じて銀座のバーで女給をしていた「葉子」だ(女給という言葉はいまでは死語かもしれないが、ホステスという言葉では置き換えられない時代的な背景をイメージさせる)。葉子のさまざまな男性関係が描かれる(それを興味本位に読めば、この作品は風俗小説のように読める)。葉子の実の母は、葉子が幼い頃に去り、葉子は「てつ」という継母に育てられた。葉子はてつに馴染めなかった。今ではてつを「母」とは呼ばずに「あなた」と呼んでいる。そんな葉子とてつとの関係がサブストーリーとして描かれる。人形浄瑠璃の心中の道行を思わせる最終章で、てつが印象的に登場する。それは葉子のてつに宛てた手紙の中で。そこにこめられた葉子のてつへの想いと、大岡昇平の葉子への想いが重なり(というのは、葉子のモデルは大岡昇平の愛人だからだ。二人は別れたが、その翌年にその人は自殺した)、その重なり合いに追憶の陰影が生まれるように感じる。
「私は大岡さんの小説では、『俘虜記』『野火』『レイテ戦記』という一連の戦記ものにも大きな尊敬を払っている人間だけれど、それとならぶくらい『花影』を尊重し、大好きで、何度もくり返し読んでいる人間である(ついでにいえば新古典主義的な『武蔵野夫人』より『花影』のほうがずっと好きである)。」(「大岡さんの許しと愛」より)
これを読んで、次は「花影」(1961)にしようと思ったが、それにしても、吉田秀和はなぜそんなに「花影」が好きなのか。上記の引用文の少し後に、次のような文章があるが、
「これも同じく『花影』の大好きな私の家内が、「これは母親に対する愛に源をもっているものかしらね」といいだした。私は途端に、そうかもしれないと思った。」(同)
これを読んでもまだ「花影」が好きな理由ははっきりしない。「母親に対する愛に源をもっている」という指摘が、わたしには唐突な感じがした。だが、それにしても、吉田秀和とバルバラ夫人が「花影」について語り合い、それが好きな理由に大岡昇平の母親に対する愛を見出して頷く。その過程が、何となく微笑ましく、また二人の「花影」に対する想いが伝わってくるように感じた。吉田秀和が「花影」が好きな理由は、わたし自身が「花影」を読み、自分で考えなければならない。それがわかっただけで十分だと思った。
そこで「花影」を読んだわけだが、その感想を一言でいえば、これは追憶の文学だ、というものだった。追憶という言葉にわたしがこめた内容と、吉田秀和とバルバラ夫人が感じたこととが通じ合うかどうかはわからないが。
「花影」の主人公は、戦前、戦後を通じて銀座のバーで女給をしていた「葉子」だ(女給という言葉はいまでは死語かもしれないが、ホステスという言葉では置き換えられない時代的な背景をイメージさせる)。葉子のさまざまな男性関係が描かれる(それを興味本位に読めば、この作品は風俗小説のように読める)。葉子の実の母は、葉子が幼い頃に去り、葉子は「てつ」という継母に育てられた。葉子はてつに馴染めなかった。今ではてつを「母」とは呼ばずに「あなた」と呼んでいる。そんな葉子とてつとの関係がサブストーリーとして描かれる。人形浄瑠璃の心中の道行を思わせる最終章で、てつが印象的に登場する。それは葉子のてつに宛てた手紙の中で。そこにこめられた葉子のてつへの想いと、大岡昇平の葉子への想いが重なり(というのは、葉子のモデルは大岡昇平の愛人だからだ。二人は別れたが、その翌年にその人は自殺した)、その重なり合いに追憶の陰影が生まれるように感じる。