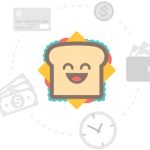【種まき作業スタート】
きょうは朝から好天気。早速、ことしはじめての種蒔き作業だ。ハーブ1種類、トマト3種類。ところで
トマトの種類が急激に増えている。ネット上では八千種もあるとのことだが、30種類程度(タキイ調べ)
でプチトマト(tiny tomato)は16種類、大きなトマトは50種類程度との記事もある。そんなことを考えて
いると、そういえばトマトに品質改良とその市場について俯瞰したことがなかったことに気づく。これに
ついては考えるとして、きょう種蒔きしたのは、イタリトマト、キャンデーチェリー、ピーチトマト。そ
れにしても紛らわし品名が多い。天気が良いだが風がまだまだ冷たいのだが、不思議なことに今年の米国
は暖かく、暖房費が減少した分、消費に回わり消費性向が上向き景気良いということだから「風が吹けば
桶屋が儲かる」ではないが「暖冬になれば景気が良くなる」とのことだから面白い。


化学プラントメーカの日揮が3月7日、植物工場システムの開発と農産物の生産を手掛けるグランパの株式
18%を第三者割当増資により取得したと発表していたが、なろほどと思うところもあるが違和感が沸きだ
んだん大きなってきた。『嵐とAKB48の時代』は昨年度のキャッチコピーだったが、環境リスク本位制時代
の植物工場デザイナー?としてはこれは明らかにしておかなければならないことは、小規模の竜巻のよう
な突然の強風や雹、霙への耐久性に配慮されているかという安全設計のコスト試算への疑問だ。もっとも
そのような心配のない地域、例えば中東砂漠などはむしろ有効かもしれない。
半導体製造会社の技術、事業開発に関わっていた経験から「植物工場」のイメージは「半導体工場」のイ
メージ相似している。つまり、デジタル革命の基本特性がまるまる当てはめたイメージで構想していたわ
けで、今日のインテルの飛躍繁栄は、CPUの集積回路設計にあることは周知のことだろうが、同じように
植物のDNAが植物工場での位置するのだと看破したのはわたし(たち)だけだ。そこでは大規模投資を必要
とするが、一旦投資されば、変動費と販路の管理ということになる。そのことは、人件費の差異ネグレッ
トできるというのがデジタル革命下のデザインの特徴だということで、日本全国を半導体工場を建設すれ
ばその使い終わった工場は「植物工場」に転用可能で、多少の気象変動に十分に耐えうる。このことはす
でに市場戦略がデザインとして完了していたが、ただ半導体は世界を相手に販売できるが、この植物工場
は地産地消という違いがある(ただし、国益と密接な「種子・苗販売」以外は)。いま、世界の覇権の1
つの鍵語としての「世界の工場」がここでは死語となると。そんなことを考えていた。
最近、タツモ社がロール・ツー・ロール方式で球状シリコン太陽電池モジュールの一環製造ラインを開発
されたことを知る。紙上では変換効率は11~14%どいうことだが本当のところは直接聞くのが良いのだが
それは別の機会にしておき、ここではその製造ラインに興味に傾く。2年前の地球温暖化対策技術評価委
員会では20点満点中15.4点の評価をえているが普及次第で(試作量産→量産)、コスト情報が確定してい
くとのことでだったが、建材一体型の需要向けということであれば期待できる(バルクな技術の終焉「燦
々×33」)。
マサチューセッツ工科大学の科学者は、『Physical Review Letters』に、LED電球の出力電力が入力電力
を超えて、効率は230%にも達するのを発見したことを発表した。データから見れば、LEDの電圧が下がる時、
出力電力が直線的に減少するが、ある時期になると、出力電力が入力電力を超えるようになる。実験では、
LEDライトは30pWの効率で約68pWの光効率を発生したというが、エネルギー保存則からみてそれって本当?!
とにわかには信じられない。発熱体としての応用拡張は可能だろうか?それは余にも小さすぎるようだ。
かといって、発光消費電力の減少(省エネ)商品への応用展開が可能だろうか疑問が次々と沸いてくるの
だが、これについては別途考えてみたい(あぁ~、目が疲れる~~~っう)。