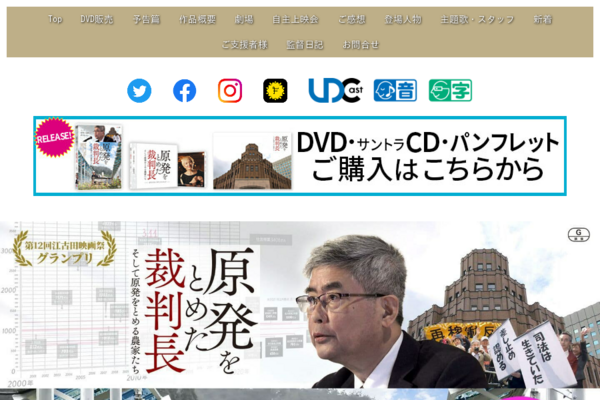終映後の舞台挨拶で、プロデューサーの河合弘之弁護士は、原発の差し止める戦いは今後も訴訟やデモや集会を継続して行なっていく。一方で、原発に代わる自然エネルギーによる発電も進めていくと、わかりやすい主張をしていた。原理原則はその通りでいいと思う。
ヒロインを演じた木村文乃は本作品のために増量したのだろうか。妙な逞しさを感じた。それに笑顔を封印したような演技である。いずれも本作品に相応しかった。
ヤクザや半グレといった不良の中には、堅気に引け目を感じている人がいるかもしれない。非合法の仕事で得たカネでは陽のあたる道を堂々と歩けないところがある。カネはカネだと割り切る者が多いだろうが、堅気と一緒に暮らすことができないことを引け目に感じる者もいると思う。
寺山修司作詞、田中未知作曲の「時には母のない子のように」が流れる。カルメン・マキが歌う、当方としてはとても好きな歌のひとつである。疾走する特急を舞台にしたアクション映画でこの歌が使われたことに、新鮮な驚きがあった。その使われ方はある種のシャレだが、悪い印象ではない。
しかしそんなふうな堅実な投資家みたいな対応をしてしまうと物語にならない。ここは人間の欲望丸出しでストーリーを進めるのが王道だ。その結果がハッピーエンドにならないことは目に見えている。星新一のショートショートにも「笑ゥせぇるすまん」にもハッピーエンドはないのだ。
「彼女のいない部屋」「デリシュ!」それに本作品と、2日間で立て続けに3本のフランス映画を観たが、どの作品も人間性に対する掘り下げがある。鑑賞時間だけ楽しめればいいというハリウッドの娯楽作も悪くはないが、余韻が残るフランス映画は、やっぱりいいものだ。
コメディではあるが、フランス映画らしくエスプリが効いていて、権威や権力を笑い飛ばす。とてもスカッとする作品である。
フランスは哲学の国だが、食欲や性欲を肯定する。性欲の延長であるファッションでは世界の最先端を譲らない。料理にも哲学があり、文化の一端を担っているという誇りを持っている。
玉木宏の怪演が空恐ろしい。身体はゴツいのに話し方が至極穏やかというアンバランスに、底知れぬ薄気味悪さが漂う。いま世間で騒がれている旧統一教会と、洗脳みたいな面で共通していて、教祖的な雰囲気も醸し出している。
本作品に出てくるのは娘の花が考えた洗脳ではなく、玉木宏の演じるセラピスト窪司郎がどうやら独自に開発した魂療法?のようなものである。ホラー映画はどんな想定も可能だ。古い井戸から出てきた貞子がそのままテレビの画面から出てくるのもありで、もしかしたらこんなことが起こり得るかもと想像できるが故の恐ろしさである。
冒頭の荷造りの場面はかなりいい。安全ピンの数で衣類を区別する工夫をしている。視覚がないから、頼りは音と臭いと触感だ。人生の途中で見えなくなった場合は、見えていたときの経験値を活かす。生まれながらの盲目とは違うやり方だ。そう考えると、盲目にも人それぞれの違いがあって、一緒くたにはできないことがわかる。盲は音の感覚が鋭いなどとは、一概に言えないのだ。