学術会議任命拒否政府文書 作成過程読み解く③ 削られた「会議の独立性」
菅義偉首相による日本学術会議の会員候補任命拒否問題で、政府が持ち出した「首相は任命拒否できる」とする法解釈と、それに向けて2018年9月から11月にかけて続けられた内閣府と内閣法制局の協議過程を示す文書。学術会議の、政府からの独立性に配慮した表現が徐々に削られ、弱められていく様子が見て取れます。
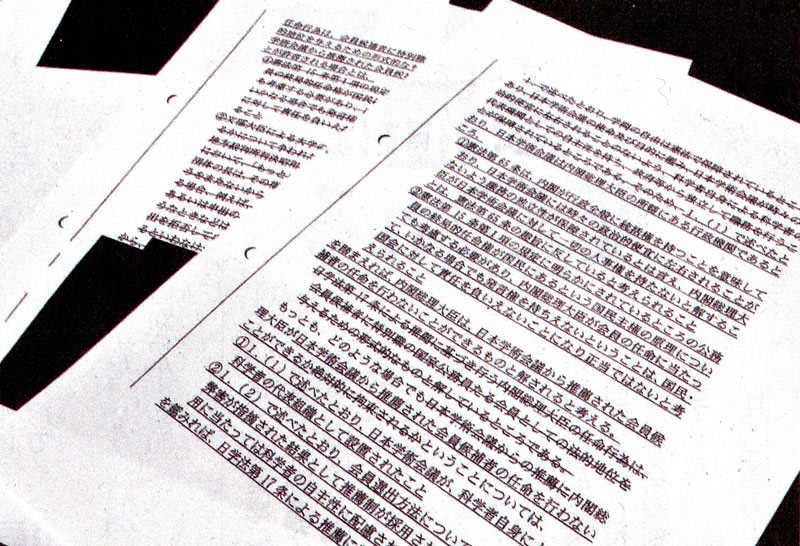
黒線や下線が引かれ、推敲(すいこう)を重ねた様子がみられる協議過程文書。黒塗り部分も
学問の自由消す
例えば、2018年10月9日付の文書。結論部分は「内閣総理大臣は、会議から推薦された者の任命を行わないことができないとまでは解されない」としており、任命拒否を正当化する記述です。
他方、学術会議の性格を説明する部分では次のような表現がありました。
①「学問の自由は憲法で保障されているところであり」②「日本学術会議が時々の政治的便宜に左右されることなく…自主性を持つため」③「職務に関して政府等から独立した立場を保証されている」
10月16日付ではこれらのうち、①が削除されています。
また、②と③に続いて「とは言え」が挿入され、「内閣総理大臣が日本学術会議に対して一切の人事権を持たないと解することは憲法の趣旨に反している」と論旨を逆転させました。
さらに10月22日付では②も削られます。
それでも、その22日付には別の部分に次のような表現が残っています。
「実質的な任命権は日本学術会議にあり、内閣総理大臣の任命権は形式的なものとなることが期待されている」この“実質的任命権は会議、首相は形式的”とする表現も、10月30日付では黒線で消されました。最終段階である11月13日付にもこの部分はなく、より弱まった「内閣総理大臣は…学術会議からの推薦を十分に尊重する必要がある」という記述が残りました。
一方、首相が任命を拒否できるとする部分は、表現ぶりはやや揺れ動いているものの、常に登場します。
首相が「推薦された会員候補者の任命を行わないことができるものと解される」などとしていた時期もありますが、最終的には「推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えない」という表現に落ち着いています。
これも、任命を拒否するという「結論ありき」で協議が進んだことの表れに見えます。
黒塗り部分残る
一連の協議過程文書の多くには、黒塗り部分が残っています。結論の直前部分が隠されているため、結論を導いた論理が分からないものや、結論部分そのものが隠されているものもあります。
内閣府日本学術会議事務局は、黒塗りの理由を「任命権者の考え方につき、誤解を招きうる記述なので」と説明します。任命権者とは首相。当時の首相は安倍晋三氏ですが、事務局は「『特定の首相の考え方』という意味ではない」と説明をぼかします。
協議過程を示す一連の文書の日付は、いずれも安倍前政権期。日付通りに文書が作成されたとすれば、学術会議が推薦した会員の任命拒否は安倍政権で準備が始まり、菅義偉首椙が初めて実施に踏み切ったかたちです。(おわり)(この連載は安川崇が担当しました)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2021年2月3日付掲載
推敲の過程で、“実質的任命権は会議、首相は形式的”とする表現も、10月30日付では黒線で消され、最終的には「推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えない」という表現に。
菅義偉首相による日本学術会議の会員候補任命拒否問題で、政府が持ち出した「首相は任命拒否できる」とする法解釈と、それに向けて2018年9月から11月にかけて続けられた内閣府と内閣法制局の協議過程を示す文書。学術会議の、政府からの独立性に配慮した表現が徐々に削られ、弱められていく様子が見て取れます。
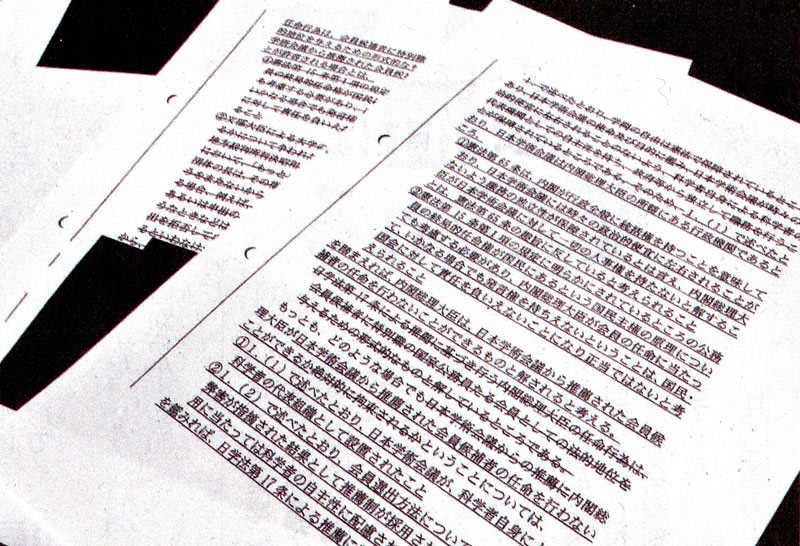
黒線や下線が引かれ、推敲(すいこう)を重ねた様子がみられる協議過程文書。黒塗り部分も
学問の自由消す
例えば、2018年10月9日付の文書。結論部分は「内閣総理大臣は、会議から推薦された者の任命を行わないことができないとまでは解されない」としており、任命拒否を正当化する記述です。
他方、学術会議の性格を説明する部分では次のような表現がありました。
①「学問の自由は憲法で保障されているところであり」②「日本学術会議が時々の政治的便宜に左右されることなく…自主性を持つため」③「職務に関して政府等から独立した立場を保証されている」
10月16日付ではこれらのうち、①が削除されています。
また、②と③に続いて「とは言え」が挿入され、「内閣総理大臣が日本学術会議に対して一切の人事権を持たないと解することは憲法の趣旨に反している」と論旨を逆転させました。
さらに10月22日付では②も削られます。
それでも、その22日付には別の部分に次のような表現が残っています。
「実質的な任命権は日本学術会議にあり、内閣総理大臣の任命権は形式的なものとなることが期待されている」この“実質的任命権は会議、首相は形式的”とする表現も、10月30日付では黒線で消されました。最終段階である11月13日付にもこの部分はなく、より弱まった「内閣総理大臣は…学術会議からの推薦を十分に尊重する必要がある」という記述が残りました。
一方、首相が任命を拒否できるとする部分は、表現ぶりはやや揺れ動いているものの、常に登場します。
首相が「推薦された会員候補者の任命を行わないことができるものと解される」などとしていた時期もありますが、最終的には「推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えない」という表現に落ち着いています。
これも、任命を拒否するという「結論ありき」で協議が進んだことの表れに見えます。
黒塗り部分残る
一連の協議過程文書の多くには、黒塗り部分が残っています。結論の直前部分が隠されているため、結論を導いた論理が分からないものや、結論部分そのものが隠されているものもあります。
内閣府日本学術会議事務局は、黒塗りの理由を「任命権者の考え方につき、誤解を招きうる記述なので」と説明します。任命権者とは首相。当時の首相は安倍晋三氏ですが、事務局は「『特定の首相の考え方』という意味ではない」と説明をぼかします。
協議過程を示す一連の文書の日付は、いずれも安倍前政権期。日付通りに文書が作成されたとすれば、学術会議が推薦した会員の任命拒否は安倍政権で準備が始まり、菅義偉首椙が初めて実施に踏み切ったかたちです。(おわり)(この連載は安川崇が担当しました)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2021年2月3日付掲載
推敲の過程で、“実質的任命権は会議、首相は形式的”とする表現も、10月30日付では黒線で消され、最終的には「推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えない」という表現に。











