真っ赤な大風船をみつけた!
ありゃ!あっちにも!
よくみると、自転車の車輪も一緒!
ここは、茅ヶ崎の高砂緑地の松林。真っ赤な大風船のあとを追った。
ありゃま!茅ヶ崎美術館に連れてこられた!
二階に上がれという。
赤い風船とちゃりんこがいっぱい!
そうか。力五山による、ちがさきチャリンコアートプロジエクトの芸術作品だったんだ

いつも四角い顔ばかりしてないで

たまには、まあるい顔しなさい!って言ってるのカナ。

つい浅田美代子の赤い風船をハミングしてしまった。
真っ赤な大風船をみつけた!
ありゃ!あっちにも!
よくみると、自転車の車輪も一緒!
ここは、茅ヶ崎の高砂緑地の松林。真っ赤な大風船のあとを追った。
ありゃま!茅ヶ崎美術館に連れてこられた!
二階に上がれという。
赤い風船とちゃりんこがいっぱい!
そうか。力五山による、ちがさきチャリンコアートプロジエクトの芸術作品だったんだ

いつも四角い顔ばかりしてないで

たまには、まあるい顔しなさい!って言ってるのカナ。

つい浅田美代子の赤い風船をハミングしてしまった。
それから100年が経過し、大正4年に三越呉服店において、追善法会と光琳遺作展が開催された。このときも紅白梅図屏風と燕子花図屏風が同時に展示された。そのときの展示品が十数点、熱海に再集合した。さあ、100年前の三越呉服店に参りましょう。
第3章 光琳200年忌
槇楓図屏風(東京芸大)重文 宗達”槇楓図”(山種)の摸写であるが、随所に光琳の個性が現れている。
佐野渡図 新古今集の定家 ”駒止めて袖打ちはらふかけもなし佐野のわたりの雪の夕暮”の絵画化。
伊勢物語 武蔵野・河内越図
琴高仙人図 鯉に乗って水中より現れる琴高(きんこう)仙人
雪中大黒天図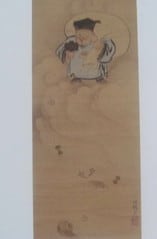
寿老人図
白百合図扇面
山水・寿老人図団扇
松山茶花蒔絵硯箱(個人蔵)
佐野渡蒔絵図硯箱(五島美術館)
そして、4章は光琳を現代に生かす。これがまたすごい。次回にお届けします。
(つづく)
二大国宝の展示室の、壁のないつづきの部屋に光琳100年忌、すなわち200年前に酒井抱一が主宰した遺墨展に出展された作品が並んでいる。文化12年(1815)の展示作品40点余りのうち、何と15点も、ここに集結しているのである。
根岸の自宅の庵で光琳100年忌の法要を行い、近くの寺院で光琳遺墨展が開かれた。そのとき、若き日の鈴木基一ら江戸琳派の面々も集まったことだろう。そして、彼らは、懐かしさの余り、また、この熱海の展覧会にも、天上からやってきているにちがいない。そう思うと、もうそれだけで感動的で、個々の作品の鑑賞なぞは二の次になってしまう。
光琳遺墨展の作品をなるべく、たくさんここに載せ、のちに、時々、覗いて楽しめるようにしておこうと思う。
第2章光琳百年忌
白楽天図屏風(根津美術館) 謡曲”白楽天”に取材。唐の白楽天が漁夫に姿を変えた和歌の神、住吉明神と詩歌の問答をする場面。
紫式部図(MOA)石山寺で源氏物語の着想を得たという伝説をもとに、描く。花頭窓、池に月。
秋野中宮図(MOA)源氏物語21帖の少女(おとめ)に取材。大振りの唐草模様と十二単の中宮。
業平天下り図(五島美術館) 伊勢物語第九段”東下り”から。富士を仰ぐ業平。
波上飛燕図 二羽の燕と波
寒山拾得図 巻物を読む寒山と箒をもってこれを聞く拾得
朱達磨図 南宋時代の達磨像(畠山記念館)を手本に。
船子夾山図 船子(せんす)と夾山(かっさん)の禅問答。
兼好法師図 ひとり灯の下にて文をひろげて、見ぬ世の人を友とする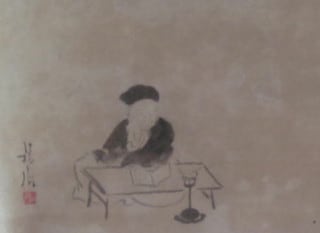
唐子に犬図(宗達写) 迷惑そうな犬の顔
銹絵寿老人図角皿 乾山の焼き物に光琳の銹絵。
絖地秋草模様描絵小袖 菊、桔梗、萩、芒などの秋草模様
(つづく)