 隣接する田村神社が讃岐の一宮で、思いのほか見所があったので一つの記事となり、ようやく一宮寺の山門に出た。しっかりした造りの楼門である。
隣接する田村神社が讃岐の一宮で、思いのほか見所があったので一つの記事となり、ようやく一宮寺の山門に出た。しっかりした造りの楼門である。先の記事にも書いたが、元々は奈良時代に田村神社の別当寺として設けられた寺院である。後に弘法大師が聖観音像を祀り、真言宗の寺院となった。江戸時代になってどういう経緯があったのか松平家から別当寺の役目を解かれたが、その後は一つの独立した寺院として今に至っている。昔とは形が変わったにせよ、八十八所には4つの国とも国分寺や一宮神社の別当寺が札所として残っている。

 境内の真ん中に巨大な楠があり、その奥に本堂がある。江戸時代の建物だという。白衣、笈摺姿の人もちらほらと見える。まずはこちらでお勤めである。
境内の真ん中に巨大な楠があり、その奥に本堂がある。江戸時代の建物だという。白衣、笈摺姿の人もちらほらと見える。まずはこちらでお勤めである。
 本堂から少し奥まったところに大師堂がある。こちらは比較的新しい建物のようで、本堂よりも大きく見える。外陣ではお守りなど扱っていて、賽銭を賽銭箱に入れると寺の人が鐘を一つ鳴らしてくれる。予約が必要だがこちらでは写経体験ができるそうだ。
本堂から少し奥まったところに大師堂がある。こちらは比較的新しい建物のようで、本堂よりも大きく見える。外陣ではお守りなど扱っていて、賽銭を賽銭箱に入れると寺の人が鐘を一つ鳴らしてくれる。予約が必要だがこちらでは写経体験ができるそうだ。


 他には菩薩堂や水掛け不動もあり、コンパクトながらも楠を中心に一通り揃っている感じである。また宝塔があるが、田村神社の祭神を祀ったものだという。
他には菩薩堂や水掛け不動もあり、コンパクトながらも楠を中心に一通り揃っている感じである。また宝塔があるが、田村神社の祭神を祀ったものだという。 その中で目を引くものがいくつかある。まずは薬師如来。「地獄の釜」と呼ばれる石造の祠に祀られている。これは弘法大師が造ったもので、祠に頭を入れると境地を開くことができるとの言い伝えがある。しかし、悪いことをする人が頭を入れると扉が閉まり、地獄の釜が煮えたぎる音がして頭が抜けなくなるとも言われている。
その中で目を引くものがいくつかある。まずは薬師如来。「地獄の釜」と呼ばれる石造の祠に祀られている。これは弘法大師が造ったもので、祠に頭を入れると境地を開くことができるとの言い伝えがある。しかし、悪いことをする人が頭を入れると扉が閉まり、地獄の釜が煮えたぎる音がして頭が抜けなくなるとも言われている。昔、この地で暮らしていたおたねという意地の悪い婆さんが、そんなことはないと頭を祠に入れた。すると扉が閉まり、地獄の釜の轟音がして頭が抜けなくなってしまった。それでこれまでの意地悪を謝り、心を入れ替えると言うと頭が抜け、それからは親切な婆さんになったという話がある。

 また、般若心経が彫られた石板がある。奉納したのは岸信介とある。地元出身の福家俊一という衆議院議員が、今あるのは岸信介先生のおかげだとして一筆してもらい、一宮寺に奉納したとある。・・・という解説の碑は、「じじい放談」、もとい「時事放談」で知られた細川隆元によるもの。弘法大師からいきなり昭和の戦後史まで飛んできた。福家さんも地元の名士として何か残したかったのだろうが、岸信介を持ってくるとはどうなんだろうか。
また、般若心経が彫られた石板がある。奉納したのは岸信介とある。地元出身の福家俊一という衆議院議員が、今あるのは岸信介先生のおかげだとして一筆してもらい、一宮寺に奉納したとある。・・・という解説の碑は、「じじい放談」、もとい「時事放談」で知られた細川隆元によるもの。弘法大師からいきなり昭和の戦後史まで飛んできた。福家さんも地元の名士として何か残したかったのだろうが、岸信介を持ってくるとはどうなんだろうか。
 納経所への通路を挟んだところには「りえとまことの夫婦槇」というレリーフがあり、まだ若い槇の木が2本植えられている。説明文では、結婚式を控えて二人とも夭逝したとある。そして、二人が生きた証として槇の木を植えたとある。平成20年没とあるからちょうど10年前、りえさんとまことさんに何があったのか。また、このレリーフを奉納したのは愛知県小牧市の方とあるが、なぜ一宮寺にあるのだろうか。何らかの経緯があったのだろうがこれだけでは分からない。まあ、そこはあまり掘り下げないほうがいい事情があるのだろう。
納経所への通路を挟んだところには「りえとまことの夫婦槇」というレリーフがあり、まだ若い槇の木が2本植えられている。説明文では、結婚式を控えて二人とも夭逝したとある。そして、二人が生きた証として槇の木を植えたとある。平成20年没とあるからちょうど10年前、りえさんとまことさんに何があったのか。また、このレリーフを奉納したのは愛知県小牧市の方とあるが、なぜ一宮寺にあるのだろうか。何らかの経緯があったのだろうがこれだけでは分からない。まあ、そこはあまり掘り下げないほうがいい事情があるのだろう。こうして見ると、一宮寺はさまざまなものを受け入れるベースがある寺院なのだろう。
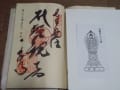
 納経所で朱印をいただき、一宮寺を後にする。駅に戻ると高松築港への折り返し列車が着いたところで、また慌ただしく運転手と車掌が入れ替わる。
納経所で朱印をいただき、一宮寺を後にする。駅に戻ると高松築港への折り返し列車が着いたところで、また慌ただしく運転手と車掌が入れ替わる。時刻は14時半を回ったところだが、次の第84番の屋島寺に行くには時間が厳しい。かと言って帰りのバス、その前の食事にはまだ時間がある。ここは高松市街に戻ることにして、久しぶりに訪ねるあの有名庭園に行くことにしよう・・・。
















