原爆や戦争の悲惨さを描いた漫画「はだしのゲン」が松江市立小中学校の図書室で自由に読めなくなっている問題で、市教育委員会は26日、市教委事務局の手続きに不備があったとして、閲覧制限を撤回することを決めました。
制限の是非には踏み込まなかった点は不満ですが、結果的に子どもたち一人ひとりが自由に読書する権利が守られることになったのは良かったですね。
教育委員会会議に参加した教育委員5人の全員一致の結論で、学校の自主性に任せることになりました。
今回の閲覧制限問題は、戦争の描き方や発達過程にある子どもたちへの配慮などをめぐり様々な議論を呼びましたが、結果的に、「はだしのゲン」の人気が高まり、親子で読む機会が増えることになりそうです。
今回の閲覧制限の真の原因は、これから明らかにしなければいけませんが、私は、3つの問題があると考えています。
一つは、今回の閲覧制限が、前教育長一人の考えで(教育委員会で議論せずに)学校に要請されたことです。
教育長は、地方教育行政組織運営法で以下のように規定されています。
①教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる(第17条)
②教育委員会のすべての会議に出席し、議事について助言する(第17条)
③教育委員会の事務局について事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する(第20条)
このため、通例、教育長は教育委員会の事務局の長となります。
教育長は、教育委員会の指揮監督下にあるのですが、今回の閲覧制限は、この規定に反して行われました。
従って、本来ならば、規定違反で懲戒処分の対象になるのでしょうが、そのような議論は全くされていませんね。
たった一人の考えで(実際には政府、政党、その他の団体からの圧力があったのかもしれませんが)検閲に近い行為がなされてしまうという怖さを感じますね。
二つ目は、今回の教育長からの要請に、大半の学校が従ったことです。
教育委員会が市内49の小・中学校に行ったアンケートの結果が公表されましたが、蔵書がない6校を除く、43校のうち、自由に閲覧できるのは1校で、要請を受けて閲覧できない措置をとったのが41校、以前から閲覧できない措置をとっていたのが1校だったということです。
つまり、要請に反して閲覧制限をしなかった学校(しっかりとした考えを持っていた学校)は、僅かに1校で、残りの大半の学校は教育長の要請に従順に従ったということです。
「はだしのゲン」の教育的な効果を考えもしないで、教育長の要請に簡単に従うという学校関係者の姿勢に何とも言えない気持ちの悪さを感じますね(まるで軍隊です)。
三つ目は、下村文部科学大臣の発言。
下村文部科学大臣は「学校図書館は、子どもの発達段階に応じて教育的に配慮する必要性があると思う。設置者である教育委員会の判断で、学校に対して具体的な指示を行うことは、通常の権限の範囲内であり法令上問題はなく、それぞれの自治体の判断だ」と述べて、一定の理解を示しました。
今回の閲覧制限の手続き(教育長が単独で要請)を認識した上で理解を示したならば、規定に違反しても問題ないということを大臣が自ら認めたことになり、手続きの詳細を認識しないで発言したならば、大臣の職責を果たしているとは言えません。
何れにしても大臣の資格はありませんね。
この問題は、次の国会で野党が追求するでしょうが、真の原因を明らかにして欲しいですね。
どうも自民党の憲法改正案にあるように、国民の権利、自由を制限するような動きが始まっているのではないかと考えてしまいますね。
今回の閲覧制限で良かったことは、市民が健全な判断をして行動を起こしたことです。
政府与党、官僚の思惑に惑わされることなく、自分の頭で考えて判断し、行動する市民で有り続ければ、自民党の国民を管理監督するという思惑も失敗に終わるでしょう。
集団的自衛権の憲法解釈の変更、TPP承認、原発再稼働等の国民の生命、安全に関わる問題が次々に出てきます。
これらの問題にどのように対応していくのか、子供や孫たちにどのような生活を残すのか、私達大人の覚悟が問われています。
ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。
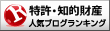
特許・知的財産 ブログランキングへ
制限の是非には踏み込まなかった点は不満ですが、結果的に子どもたち一人ひとりが自由に読書する権利が守られることになったのは良かったですね。
教育委員会会議に参加した教育委員5人の全員一致の結論で、学校の自主性に任せることになりました。
今回の閲覧制限問題は、戦争の描き方や発達過程にある子どもたちへの配慮などをめぐり様々な議論を呼びましたが、結果的に、「はだしのゲン」の人気が高まり、親子で読む機会が増えることになりそうです。
今回の閲覧制限の真の原因は、これから明らかにしなければいけませんが、私は、3つの問題があると考えています。
一つは、今回の閲覧制限が、前教育長一人の考えで(教育委員会で議論せずに)学校に要請されたことです。
教育長は、地方教育行政組織運営法で以下のように規定されています。
①教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる(第17条)
②教育委員会のすべての会議に出席し、議事について助言する(第17条)
③教育委員会の事務局について事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する(第20条)
このため、通例、教育長は教育委員会の事務局の長となります。
教育長は、教育委員会の指揮監督下にあるのですが、今回の閲覧制限は、この規定に反して行われました。
従って、本来ならば、規定違反で懲戒処分の対象になるのでしょうが、そのような議論は全くされていませんね。
たった一人の考えで(実際には政府、政党、その他の団体からの圧力があったのかもしれませんが)検閲に近い行為がなされてしまうという怖さを感じますね。
二つ目は、今回の教育長からの要請に、大半の学校が従ったことです。
教育委員会が市内49の小・中学校に行ったアンケートの結果が公表されましたが、蔵書がない6校を除く、43校のうち、自由に閲覧できるのは1校で、要請を受けて閲覧できない措置をとったのが41校、以前から閲覧できない措置をとっていたのが1校だったということです。
つまり、要請に反して閲覧制限をしなかった学校(しっかりとした考えを持っていた学校)は、僅かに1校で、残りの大半の学校は教育長の要請に従順に従ったということです。
「はだしのゲン」の教育的な効果を考えもしないで、教育長の要請に簡単に従うという学校関係者の姿勢に何とも言えない気持ちの悪さを感じますね(まるで軍隊です)。
三つ目は、下村文部科学大臣の発言。
下村文部科学大臣は「学校図書館は、子どもの発達段階に応じて教育的に配慮する必要性があると思う。設置者である教育委員会の判断で、学校に対して具体的な指示を行うことは、通常の権限の範囲内であり法令上問題はなく、それぞれの自治体の判断だ」と述べて、一定の理解を示しました。
今回の閲覧制限の手続き(教育長が単独で要請)を認識した上で理解を示したならば、規定に違反しても問題ないということを大臣が自ら認めたことになり、手続きの詳細を認識しないで発言したならば、大臣の職責を果たしているとは言えません。
何れにしても大臣の資格はありませんね。
この問題は、次の国会で野党が追求するでしょうが、真の原因を明らかにして欲しいですね。
どうも自民党の憲法改正案にあるように、国民の権利、自由を制限するような動きが始まっているのではないかと考えてしまいますね。
今回の閲覧制限で良かったことは、市民が健全な判断をして行動を起こしたことです。
政府与党、官僚の思惑に惑わされることなく、自分の頭で考えて判断し、行動する市民で有り続ければ、自民党の国民を管理監督するという思惑も失敗に終わるでしょう。
集団的自衛権の憲法解釈の変更、TPP承認、原発再稼働等の国民の生命、安全に関わる問題が次々に出てきます。
これらの問題にどのように対応していくのか、子供や孫たちにどのような生活を残すのか、私達大人の覚悟が問われています。
ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。
特許・知的財産 ブログランキングへ














