今出川通沿い、西陣にある「京都市考古資料館」。「よく前を通るけど、一度も入ったことないね~」と、ミモロだけでなく、おそらく京都に住む人たちも、あまり大人になってからは、訪れたことがないのでは…。


今出川通に面して建つ、堂々とした、ちょっとレトロな建物です。
そもそもこの資料館は、昭和51年に財団法人京都市埋蔵文化財研究所が設立され、数多くの発掘調査、研究などを行い、そこで発掘された貴重な埋蔵物などを展示公開し、埋もれた文化財への関心を喚起し、普及啓発するために、昭和54年に「京都市考古資料館」として開設されたのだそう。
100周年というのは、この資料館の前身である「西陣織物館」が、大正4年(1915)に開館したことを記念するもので、11月29日まで、「特別展示 都へのあこがれーひろがる京文化ー」が開催されています。
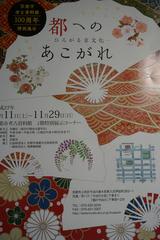
この特別展は、西陣織の歴史をはじめ、戦国時代から政治・経済・文化の中心地として日本各地に発信した京文化などにまつわる展示をしています。(特別展は、撮影できないので、あしからず…)
館内に入りましょう。


「なんかレトロな建物だね~」と、階段を上がりながら、キョロキョロ…。
この建物は、「旧西陣織物館」で、大正4年の竣工。設計は、建築家・本野精吾で、東京帝国大学を明治39年に卒業し、その2年後、建築家・武田五一の招きで、京都工芸学校(現在の京都工芸繊維大学)の教授となり、京都を中心に活躍することに。
装飾を排したシンプルでモダンな外観…
 内部の装飾も抑えられ、モダニズム建築の先駆的な存在といわれています。
内部の装飾も抑えられ、モダニズム建築の先駆的な存在といわれています。現在、京都市指定有形文化財。施工を担当したのは、大林組です。
歳月と共に、さまざまな補修、補強が行われ、今も、堂々とした姿を誇ります。「傾かなくてよかったね~」とミモロ。
さて、2階の常設展示を見学しましょう。
 「わ~土器がいろいろ」
「わ~土器がいろいろ」
壁面の展示スペースには、京都市内で出土した平安時代に使われていたいろいろな焼き物が、半世紀単位で、区分されて展示しています。時代と共に、焼き物の種類も変わってゆくのがわかる展示です。
だれも見学者がいないフロアをミモロは、独占。

「古い土器もいっぱい並んでる~」縄文、弥生など古い時代の京都の歴史が、そこに…。


「京都にも縄文時代があったんだ~」と、平安時代からのイメージが強い京都ですが、平安遷都以前の歴史ももちろん各所にあるのです。
 「埴輪もある…」
「埴輪もある…」縄文時代の竪穴式住居跡も京都市内で発見され、その遺跡から型をとってつくったレプリカが展示されています。

「昔の人の木のお靴…」

平安時代、貴族の人たちが履いていた木製の靴。今は、神職の方などが履いていますが。日本では、一般庶民は、いつしか下駄や草履に…。「外反母趾にならなくてよかったね~」と、ミモロ。アジアでは、サンダルのような履物が発達しますが、親指と人差し指(足で、人はさしませんが…)で挟んで履くスタイルは、日本で最も発展したもの。「なんで?」とミモロ…。履物の歴史でも、その理由は、あまりわかっていないよう…。
京都の地層の断面模型。

歴史と共に、堆積された土が、前の時代を地面の中に埋まらせます。
「遺跡って、みんな深い土の中から出てくるでしょ。つまり時代が過ぎるほど、積もった土の上で暮らしてることになるんでしょ?ねぇ、地球って大きくなっちゃったの?」と、首をかしげるミモロ。おそらく洪水などで、山の土が流れて、平地を埋めてゆくんじゃないの…だから、山は削られているかもしれないけど、地球の大きさって、変わらないんじゃないの?ミモロの疑問には、明確に答えられません。
だれかに聞いてみたいもの…。
1階には、ミモロの疑問に答えが見つかるかどうかは、わかりませんが、考古学に関するさまざまな図書が閲覧できるコーナーもあります。

「ここって、静かに勉強できそう…」
現在「京都市考古資料館」では、琳派400年記念協賛事業として、11月23日まで「出土した仁清・乾山」という企画陳列も開催しています。二人の陶工の足跡を紹介する、京都各所から出土した二人の作品が見られます。
*「京都市考古資料館」の詳しい情報は、ホームページで
 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへブログを見たら、金魚をクリックしてね~ミモロより

















