「ミモロちゃん、きっと興味をもつお話がきける会があるけど、行ってみない?」と、お友達に誘われたミモロ。10月17日の土曜日に、祇園祭の船鉾が立つ、新町通の「京絞り 寺田」で開催された「花習塾 紬の会」に出かけました。
この会は、観世流能楽師 片山伸吾さんが、毎回、さまざまな分野のゲストをお二人迎え、お話しを伺うもの。今年、10周年になる人気の会です。
「はじめまして、ミモロです。今日は、楽しいお話しがうかがえると聞いて、参加させていただきました」とご挨拶。
「ようこそ…きっと楽しいと思いますよ」とナビゲーターの片山さん。

会場には、すでに大勢の参加者が…。
 ミモロは、後ろの方の席から、背伸びしながら、前を見つめます。
ミモロは、後ろの方の席から、背伸びしながら、前を見つめます。第37回となる今回のゲストは、明治16年創業の桂離宮のそばにある「御菓子司 中村軒」の若主人、中村亮太さんと、寺町通にある300年以上の歴史を誇るお茶の「一保堂」の専務の渡辺正一さんです。

共に、長く続く家業を担うお二人です。まずは、誰もが聞きたい質問…
「昔から、家業を継ぐようにいわれたんですか?」と片山さん。
中村さんに伺うと…「いいえ、親から、言われたことはありません。高校を卒業して、なんとなく仕事に就くのも、まだいやだったんで、和菓子の専門学校に行こうかと言ったら、父親に、そんないい加減な気持ちなら、役に立たないから、行くなら、自分で学費を出せ、大学に行くなら、学費を出してやるというので、まずは大学に行くことに。その後、東京の和菓子店で修業をしました。まぁ、直接、家業を継ぐように言われたことはないんです」と中村さん。
 「僕も、親に家業を継げといわれたことはありませんが、一人っ子ですから、周囲が、当然のように跡取り息子だと思っていたんで、僕自身もなんとなく…。」と渡辺さん。「父親に言われたのは、『大学は、どこでもいいから、京都から出ろ』と…。それで東京の大学に行きました」と。大学卒業後、全く今とは関係ないキャラクターグッズ関係のお仕事をなさって、そこに長くいるよりは…ということで、その後、京都に…。老舗の跡取り息子として見る周囲の人の目から、全く、それを知らない別の土地に行くことで、息子さんの世界が広がるだろうと考えた親心かもしれません。
「僕も、親に家業を継げといわれたことはありませんが、一人っ子ですから、周囲が、当然のように跡取り息子だと思っていたんで、僕自身もなんとなく…。」と渡辺さん。「父親に言われたのは、『大学は、どこでもいいから、京都から出ろ』と…。それで東京の大学に行きました」と。大学卒業後、全く今とは関係ないキャラクターグッズ関係のお仕事をなさって、そこに長くいるよりは…ということで、その後、京都に…。老舗の跡取り息子として見る周囲の人の目から、全く、それを知らない別の土地に行くことで、息子さんの世界が広がるだろうと考えた親心かもしれません。また、長く続くお店と言えども、ただ昔からのやり方だけでは、今の世の中のニーズにこたえることはできません。
『中村軒』では、和菓子のほかに、年々バージョンアップされる、春と夏のかき氷が、今、大人気に…。氷に掛ける季節限定のフルーツの蜜など、毎月のように通うファンも大勢。桂離宮のそば、桂川の畔という場所、阪急京都線の「桂駅」から徒歩15分という決して便利な場所ではありませんが、かき氷を求めて、店の前には、列もできるほど。
『一保堂』の渡辺さんは、「最近、多くの方が飲まれる日本茶は、ペットボトルのものなんです。茶葉で一杯、一杯煎れるお茶の美味しさをもっと知ってほしいものです」と。そこで、寺町の店の一角には、喫茶室「嘉木」も作り、さらに東京丸の内にも店舗を構え、国内外の人に日本茶の魅力をアピールしています。
他のところで、聞いたことがありますが、日本茶の緑茶の需要の多くは、ペットボトル飲料で、次に、スイーツなどの原料で、一般家庭での茶葉の需要は減少しているのだそう。
「でも、京都にいると、お茶を飲む機会多いよね~。コーヒーより日本茶のおもてなしのお店ばかりだもの…」とミモロが思っていると…。
「飲食店で、中国茶はメニューに載っていて、みんなお金を払って飲みますが、日本茶は無料という感覚がですよね。これもどうにかしたいところですが…」と本音もチラリ。
さて、ほかにもいろいろお話しが続きましたが、ここでブレイクタイム…「中村軒」の和菓子の実演が始まりました。

作るのは、名物「麦代餅(むぎてもち)」昔から、農家などで、仕事の合間に食べられたお菓子です。
「御菓子づくりチャレンジしたい人いませんか?」と片山さんの声に、ミモロのお友達が手をあげて、前へ。

「あんこ、好きなだけ包んでいいですよ。でも、あまりたくさんいれると、はみだしますから、ほどほどに~」と中村さん。
お餅で餡を包んだ後は、上からきな粉を振り掛けます。
「ミモロちゃん、見て、できたわよ~」と、嬉しそうに、お友達は作った「麦代餅」をミモロの前に…。

「ホント、美味しそうだけど、なんかツチノコみたいな形…太りすぎじゃない…」と、鋭い指摘。「やっぱり餡いれすぎちゃったかな~」とお友達は苦笑します。
その後、参加者全員に、なんと中村さんが作った「麦代餅」と渡辺さんが煎れてくださった抹茶がプレゼントされました。

「わ~感激、つくりたてだよ~」と感激するミモロ。「ほら、やっぱり本物は、スマートな形じゃない?」と。

上から振り掛けたきな粉も香ばしく、素朴な味わいで、また食べたくなる和菓子です。
たっぷりした「麦代餅」は、食べごたえも十分。
「このお茶も美味しいね~」とミモロ。
「抹茶は、茶筅さえあれば、簡単に楽しむことができます。例えば、大き目の器で抹茶を点てて、それをデミタスカップにいれて、楽しんだり…」と渡辺さん。「あ、それいいかも…ミモロもやってみよう…ケーキにも合うかも…」と。りっぱなお茶碗でいれなくても、またお点前を気にしなくても、抹茶の美味しさは、楽しめるのです。
「抹茶は、茶葉の処理もしなくて済みますし、また茶葉自体すべて飲むわけですから、体にもいいんです」と。エスプレッソコーヒー感覚で、楽しむという発想は、素晴らしい…。
「楽しかったね~。おやつも出るなんて知らなかった~。また参加しよう…」とミモロ。
 お菓子とお茶が出たのは、ゲストがその関係者だったから…。毎回でませんよ。「あ、そう…。でも、お話しだけでも十分楽しいよ~」と、また参加するつもりのミモロです。
お菓子とお茶が出たのは、ゲストがその関係者だったから…。毎回でませんよ。「あ、そう…。でも、お話しだけでも十分楽しいよ~」と、また参加するつもりのミモロです。*毎回、多彩なゲストを迎えて行われる「紬の会」。次回は、12月5日。
詳しくはホームページで。
 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへブログを見たら、金魚をクリックしてね~ミモロより



















 その松明の火をじっと氏子の人たちが見つめます。
その松明の火をじっと氏子の人たちが見つめます。
 大きな松明は、藤の根で縛らています。
大きな松明は、藤の根で縛らています。











 すでに境内には、神幸列に参加する人たちが、装束をつけてスタンバイしています。準備は、朝6時ごろから始まるそう。雨天の場合は、翌日に順延されるのは、「葵祭」「祇園祭」と違うところ。神事よりパレードなどイベント性が高いことを示しています。
すでに境内には、神幸列に参加する人たちが、装束をつけてスタンバイしています。準備は、朝6時ごろから始まるそう。雨天の場合は、翌日に順延されるのは、「葵祭」「祇園祭」と違うところ。神事よりパレードなどイベント性が高いことを示しています。

 「今年も見物にきました~」とご挨拶。
「今年も見物にきました~」とご挨拶。
 待ち時間の多い行列参加者。主催から、ゲーム機をもってきてもいいといわれているそう。
待ち時間の多い行列参加者。主催から、ゲーム機をもってきてもいいといわれているそう。





 「通れた~」
「通れた~」

 料理店のご主人たちです。
料理店のご主人たちです。 京都で学生時代を過ごす人には、思い出になるアルバイトです。
京都で学生時代を過ごす人には、思い出になるアルバイトです。





 毎年、ここで会うのに、今年はいらっしゃないと、ミモロが探していた方。市議さんなので、なんでも議会と重なったそうで、今年はお祭りは、パスだとか…。
毎年、ここで会うのに、今年はいらっしゃないと、ミモロが探していた方。市議さんなので、なんでも議会と重なったそうで、今年はお祭りは、パスだとか…。 「始まった~」ミモロは、最前列で見物です。
「始まった~」ミモロは、最前列で見物です。









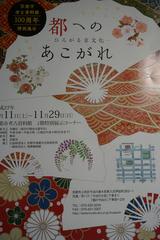


 内部の装飾も抑えられ、モダニズム建築の先駆的な存在といわれています。
内部の装飾も抑えられ、モダニズム建築の先駆的な存在といわれています。 「わ~土器がいろいろ」
「わ~土器がいろいろ」



 「埴輪もある…」
「埴輪もある…」









