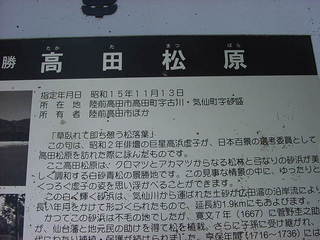5/29(月)に行った一関市花泉町老松の「ぼたん園」の大駐車場に、青紫色とピンクの花をつけた「ワスレナグサ(忘れな草)」がありました。また、芍薬園の方を歩いていたとき野生化したものと思われるものが群生していました。

上の画像は、野生化した「ワスレナグサ」と思われるもの。




ワスレナグサ(勿忘草/忘れな草)ムラサキ科 ワスレナグサ属 Myosotis scorpioides
ヨーロッパ、アジア原産の越年草または多年草。早春、地下茎から芽を出した茎は地を這って広がり、分枝して高さ20~40cmになる。
花は先端がくるりと巻いた花序に、直径6mmほどの小さな花が寄り集まって咲く。平地では4~5月、高原では6~7月に咲く。花色は、鮮やかな青紫に黄色の芯があるものが普通だが、青系のほか、ピンクや白の品種もある。別名:アイミジン(藍微塵)
和名は、英名の「forget-me-not」を訳したもの。恋人のために川岸でこの花を摘み、誤ってドナウ川に落ちた青年が「私を忘れないで」といって水中に消えたというドイツの花物語に由来する。
花壇に植えられているものは、花が大きくて色も濃い園芸品種が多いが、寒冷地では花の色が淡くて見栄えのしないものが、日当たりの良い水辺などに半野生化している。
なお、野生の「キュウリグサ」も俗にワスレナグサと呼ばれるが、別属の草花である。