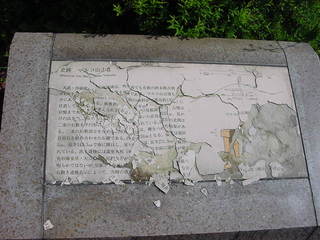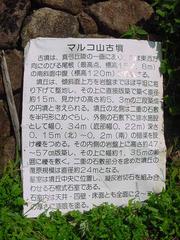5/21(日)、一関市厳美町真湯にある観察林(「巨木の森」)に、「ルイヨウボタン(類葉牡丹)」の花が咲いていました。黄緑色の花なので、ほとんど目立ちません。








ルイヨウボタン(類葉牡丹)メギ科 ルイヨウボタン属 Caulophyllum robustum
落葉樹林の中などに生える多年草で、高さは40~70cmになる。上部に2~3回3出複葉の葉が2個互生するが、葉柄がほとんどないので、3個の葉が輪生しているように見える。小葉は長さ4~8cmで、長楕円形のものや2~3つに切れ込むものがある。
和名は、この葉の形がボタン(牡丹)の葉に似ていることによるという。
花期は4~6月。花は直径8~10mmで、黄緑色の蕚片が6個あり、花弁はごく小さい。分布:北海道、本州、四国、九州