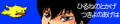犬島精錬所美術館
これを真剣に書こうと思ったら、えらいことになります。
犬島の歴史、精錬所の歴史、アーキテクト三分一博氏、アーティスト柳幸典氏について、そして、作家三島由紀夫氏のこと。
これらが全部集約されたものが「犬島精錬所美術館」です。
すごく思うこと、感じたことたくさんありすぎて、とても自分の筆力では表現仕切れません。
…ので、まずは安易に時系列で体験レポート風に出発します。
館内撮影禁止なので、ぜひこちらもご覧になりながら、お読みください。
YANAGI Yukinori ウェブサイト

まずは精錬所の入り口。
この逆光でショボい画像ですごめんなさいm(_ _)m
前回、冒頭の画像にも登場したこれらのレンガは、精錬の過程でできた「スラグ」からなる「カラミ煉瓦」とのこと。
かつてここに、巨大な精錬所があった…けれど、それが百数年前(しかもたった10年で閉鎖)…というこの時間の隔たりが、あまりピンときません。
数百年か…千年か…まるで、遺跡のようです。いや、遺跡ですよね(^_^;)
敷地全体がアートです。
館内に入ると、スタッフの方がまずこの美術館に携わった建築家とアーティストとのコラボについてご説明くださいました。
それから、この建物の、太陽や植物などの環境を利用した館内空調システムについて。
さて。いよいよアート空間へ、、、
入り口のスクリーンにはには、大きな太陽が燃えている動画。
プロミネンスが見えます。
これ見ただけで、ゾクッとして太陽の燃える音が聴こえてきます。(TAKAMIの空耳)超重低音の耳鳴りとでもいう…?
そして、太陽を背に、まっすぐと、「カラミ煉瓦」の敷き詰められた、狭い真っ暗な直線の道を進んでいきます。
直線は何度も折れ曲がります。
後ろを振り返る度に、いつも、あの入り口の太陽が燃えています。
威圧感のあるギーン…という耳鳴りで、「私はあなたを常に見ている、どこに隠れても…」という感じ。
そのうち、宇宙の星「太陽」ではない、地球の太陽光が見えてきます。
ちょっと耳鳴りが遠のく。ちょっとホッとした…のも束の間、、、、
辿り着いた部屋は、大きな水溜りの上に部屋の建具や家具などを吊るして配置したドームのような空間でした。
この水溜りは、犬島の大きな一枚岩を配置したところにつくられたものと思われます。
揺れもせず、静止して浮かんでいる住人を失った部屋の建具。魂の脱け殻。
ものすごく救いのない逃げ場のない、だけどものすごく美しい空間でした。
画像は明るいですが、実際にはもっとずっと暗く、背筋が凍りそうなテンションの高さでした。
ここからは屋外の展示にも通じていて、そこにも建具が斜めに吊るされていたり、便器が床に転がるように配置されていたり。
ドームの中とは違って、リズムを感じる空間です。
再びドームに戻って、次は鏡の部屋へいざなわれます。
四畳半程度の暗い部屋の対面になっているそれぞれの襖をスタッフの方がゆっくりと開けてくださると、
そこには大きな合わせ鏡が出現。
赤い文字群が簾のようになって映し出され、無限地獄の空間が…
鏡には死者の怨念が映し出されるとかなんとか、コワ~イ解説をしていただいたような気も、、、
このコワイ部屋を後に、やっと屋外へと脱出です。
屋外の作品は、三島由紀夫の『檄』の全文を金メッキの鉄板の文字で天井から吊るしたとても美しい作品でした。
ここで私達はスタッフから始めて「三島由紀夫」の名前を聞きました。
何故ここに『檄』が?
柱だけの枠組みの中に金色にきらきらと垂れ下がっている「檄」は、「金閣寺」を彷彿とさせます。
しかし、それにしても、三島由紀夫の衝撃的な最期ことは、私も子ども心にものすごくショックでした。
その後、中学時代に読んだ彼の小説と接点がみつからず、私の中では、彼は「作家、文学者」であり続けていてほしく、最期のことは心の遠くに投げやっていました。
ここで、突然三島由紀夫と再会するのか…
しかもしかも、予習不十分であとで知ったことですが、「ドーム」などに浮かんでいた建具は、三島由紀夫の住まいの建具や家具だとか。
屋外の作品も、鏡の部屋も、、、
ソレ、先に言ってよ!って感じ。
館内の作品はすべて、「近代化による精錬所の辿った歴史」に「三島由紀夫」を重ね合わせているのであった。
ベネッセとしては、あまりそのような視点で鑑賞してほしくないのか、きっとそうなんだろうな~~~??
思想的に偏った印象になってしまうもんね。
ここを訪れる世代の人で、三島由紀夫の作品を読んだことがある人がどれだけいるか。
さらには「檄」などという過激な文章が存在していることなんか知ってる人は殆どいないと思う。
私、ちょっと…いえ、かなりググってみましたが、
犬島精錬所美術館の記事を書いているブロガーさんで、三島由紀夫氏に言及している方は私のググった範囲では全くといっていいほどいらっしゃいませんでした。
でも私、思うのですが、アーティストとしてはどうなんでしょうか?
「檄」全文を一文字一文字を作って金メッキを施して、それを糸で繋ぎ合わせて吊るすことや、
三島由紀夫の部屋の建具を運んできて吊るすこと、、柱や階段までも…
それと精錬所の歴史を結びつけることこそが、アーティストとしてはこの美術館のテーマじゃないのだろうか??
そんなことは関係なく、恒星としての太陽と、陽射しとしての太陽、建具を用いたアート、
お経のような金色の文字…
これらを、純粋に楽しめばよいのです。
アーティストの作品の受け止めかたは、受け手の自由。
そして、自然エネルギーで空気を循環させるエコなシステムに「へぇ~~っ」と感嘆してね。

そうそう、ここのトイレはびっくりしました。
ドアを開けたら、便器が後ろむきになっているのです、つまりドア側がタンク。
そして、反対側の壁は半透明なタイルで、天井からの採光もありとっても明るく開放感あります。
なんじゃこのデザインは!!( ̄□ ̄;)!! と思ったけど、、、、
館内のエコシステムの図の中にも、トイレの図があって「REUSE」と書かれています。
この分野は、アーキテクト担当か、、、
なるほどね!
そして、この島は負の遺産を抱えながら、これからどこに向かっていくのか、、、
瀬戸芸の島々はどこに向かっていくのか…ひいてはこの地球という、人が唯一住める場所であるところは。
それぞれのアーティストが、そういう共通のテーマを持ちながら、自分の作品と島の自然に連続性を持たせて創作をしているとことに、とても共感します。

このあと、お昼過ぎの船で小豆島まで戻ります。
その前に港のお店でビール飲んだ♪
もうちょっといて、お店のおばんさんたちと語り合いたかったなあ。
でも、また3年後、こんどは少し余裕のある行程で、さらにじっくり訪れたいと思います。