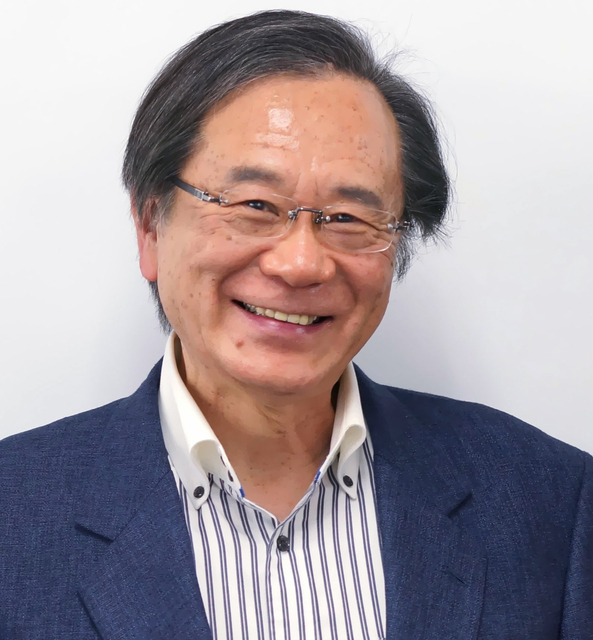武田先生 内田卓志
一休みしたところでインタビュー・質問の続きです。
主観性の知について、語っていただいています。今までは、その認識論的・存在論的な側面についてのお話でしたが、次にその実存論的な側面について伺います。
まず、実存という言葉について伺いたく思います。一般的には実存とは、古代ギリシャからある概念と言われていますが、20世紀の思想的・哲学的成果の一つと考えられています。実存主義とか、実存哲学とか言われます。サルトルやヤスパースは、自らの思想・ 哲学 にその名を与えました。日本でも実存的不安という言葉が流行したのはいつ頃だったでしょうか。評論家の山崎正和氏が、実存(主義)的分析を自らの評論、『不機嫌の時代』で見事に応用したことを想い出します。
それでは武田先生の考える実存について語っていただき、その後、教育と主観性の知における実存の問題、近代と実存の問題、そして、社 会と個人の問題へ話を展開できればと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
内田さん
わたしは大学の哲学徒でもありましたから、実存(現実存在の略)の思想を哲学史の中におく見方も分かりますが、今は、それらはわたしの思索の肥料になってしまい、そのものとしては検討する必要を感じません。
以下に、わたしの実存の定義やそこから得られる帰結についてお話します。
わたしのいう「実存」とは、私は、一回限りの私の生を生きている、という自覚を意味します。ほかの誰でもない、ただ一人のこの「私」が生きる、という明晰な自覚をもった生を実存としての生と呼んでいます。実存の明晰な意識化は、必然に私の生の意味充実を目がけます。
私は世界の中に生きていますが、世界の意味を汲み取るのは、私の意識です。何をどのように見、考えようと、私は私の意識を超えてその外に出ることはできません。私は外なる存在をはっきりと意識できますが、それも「私」の意識であるというパラドクスから逃れられません。この認識論の原理は、実存として生きる以外に人間の生はないことを教えます。
したがって、私にとって意味のないことは認識の対象にはなりえません。他者が意味あるものとして遇する事象も、もし私がそう感じなければ私には存在しないも同然です。これは原事実です。人間の認識は関心がなければ成立しないので、関心が認識の出発点ですが、関心はこの一回限りの生をいきる「私」の関心ですから、実存としての生と重なっています。認識と実存が結び付いてることを知ること は、フィロソフィ(恋知)の原点なのです。
主観と結び付いてしか客観はなく、客観それ自体を問うことが理に反するのは、現代ではすでに「常 識」になっていますが、 主観とは、抽象的な人間の主観ではなく、最後は必ずこの「私」の主観でなければなりません。それを離れれば主観は根付く場所を失い、ただの言葉=概念に陥ります。もしそうなれば、言葉や数字を概念としてだけ扱う精神疾患者(アスペルガーの一種)の意識と同じなってしまいます。 生々しい実感・ピントの定まったクリアーな意識を伴わない主観とは生きた主観ではなく、ただの言葉=概念です。要注意。
人間の主観としての意識が、この世界を世界として定立させ、世界に意味を与えているので、各自の人間存在は、物の存在とは存在のありようが逆です。物はそれ自体で存在しますが、人間とは意識存在で、物やさまざまな事象を意味づけ価値づける主体者です。意識のない人間とは人間ではありません。ここで注意すべきは、前意識や無意識の存在ですが、意識されない意識としての無意識領域も、それが意識=自覚にもたらされた時にだけ現実的な意味をもつことです。検討・吟味(=意識化)されなければ意味をもちませんので、無意識領域を実体化させて物の存在のように見てはダメです。
というわけで、どこまでも「私」が見、感じ、想い、考え、生きるという根源的な事実から目を離さないこと、それを明晰に自覚することが「実存」という意識です。繰り返しますが、実存の明晰な意識化は、必然に私の生の意味充実を目がけます。
この人間の生の原理が自覚された時にはじめて各自の私は協力や共同が可能となり、各自の実存は、 響存(響き合う存在)ともなります。各自の「対立」は、対立があるからこそ豊かな成果をあげます。対立は否定ではありません。必要不可欠な人間の生の要素です。 自己であれ他者であれ、否定したら元も子もなくなります。大事なのは「対立」で、それゆえに各自の実存は輝くのです。この話は、すでに教育論に移行していますね。では、また。
武田康弘