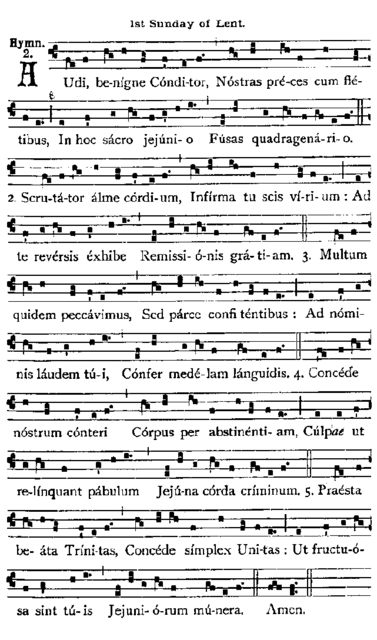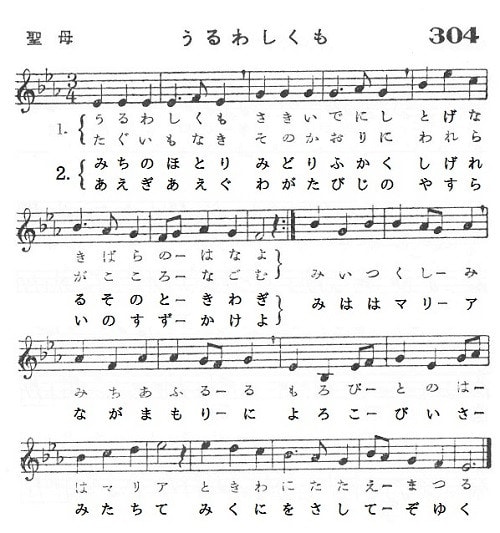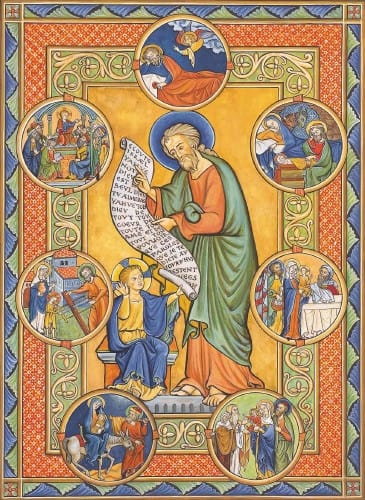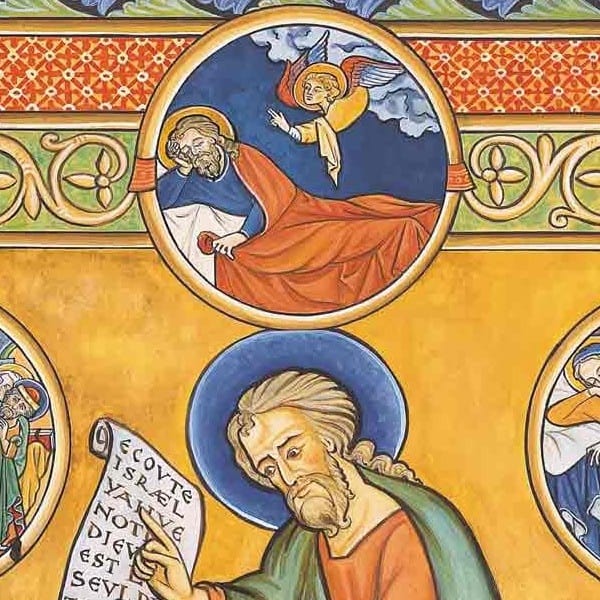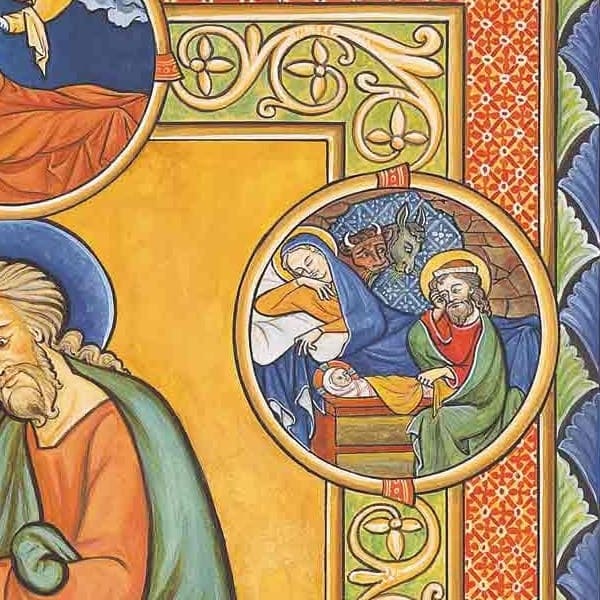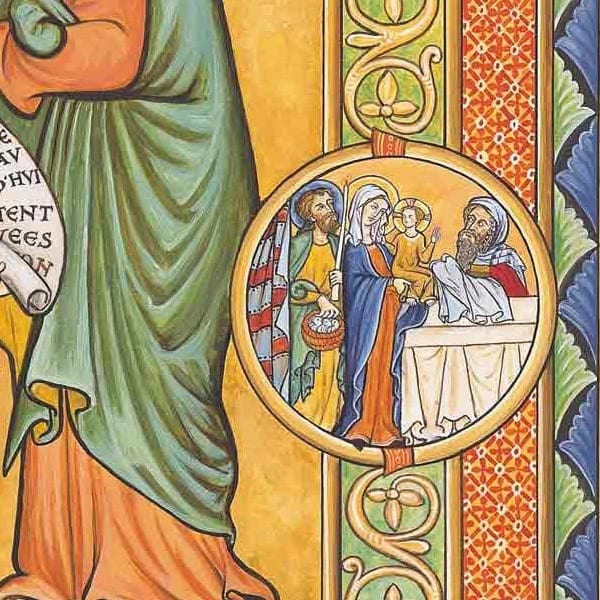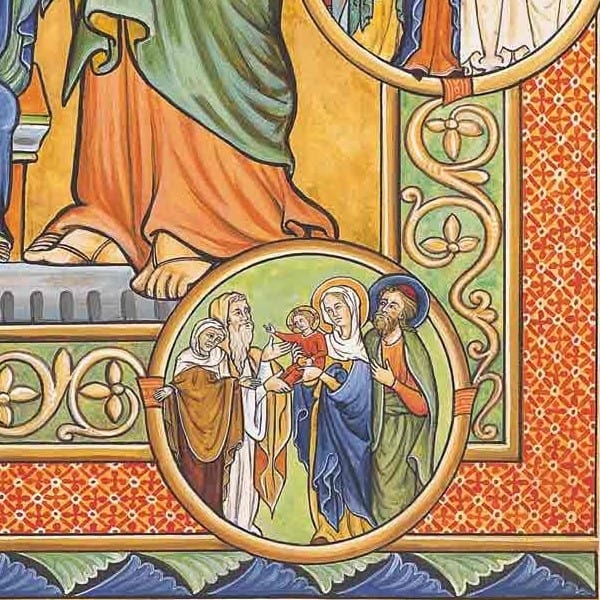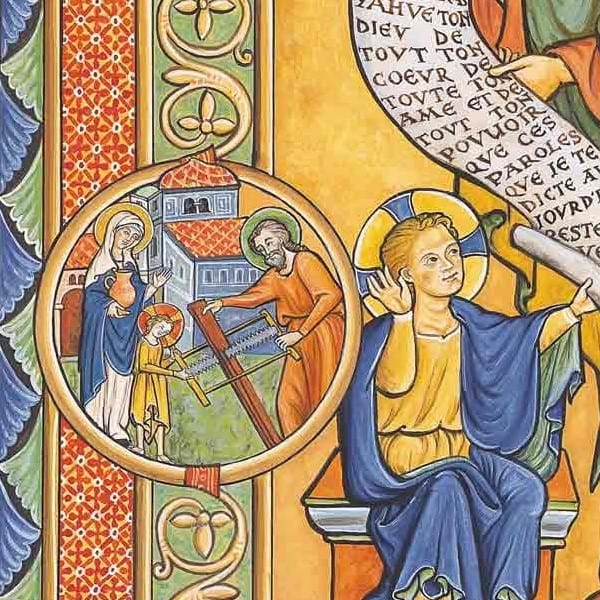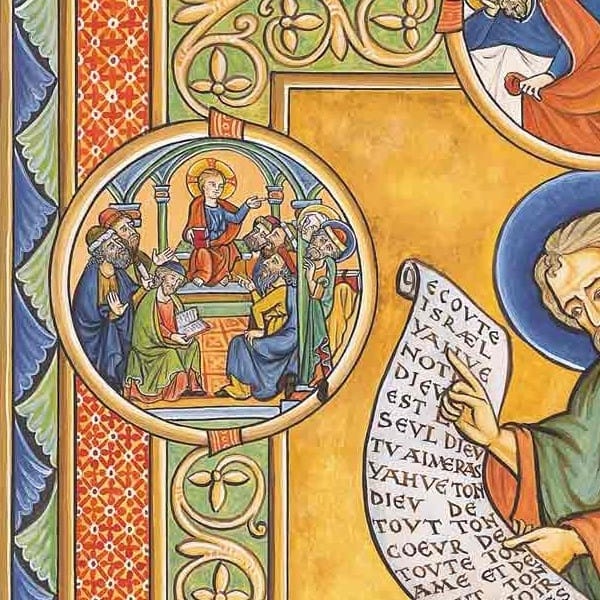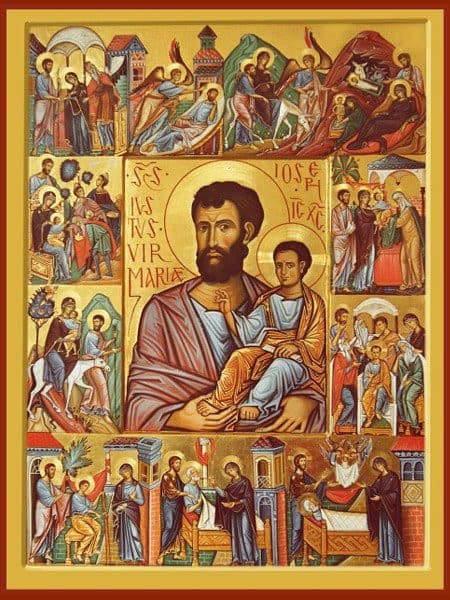アヴェ・マリア・インマクラータ!
愛する兄弟姉妹の皆様、
恒例のドン・ショタール著「使徒職の秘訣」L'Ame de tout apostolat
第三部 内的生活が善徳への進歩を保証してくれなければ活動的生活はむしろ危険である
三、福音の働き手の聖性 ―― その土台は内的生活である
をご紹介します。山下房三郎 訳を参考に、フランス語を参照して手を加えてあります。
天主様の祝福が豊かにありますように!
トマス小野田圭志神父(聖ピオ十世会司祭)

第三部 内的生活が善徳への進歩を保証してくれなければ、活動的生活はむしろ危険である
三、 福音の働き手の聖性 ―― その土台は内的生活である(続き)
(A)内的生活は、使徒的事業につきものの危険にたいして、霊魂を予防してくれる
「人びとの霊魂の世話をゆだねられたときは、そのたずさわる仕事に付随している外的危険のため、あくまでも善良な生活を生きぬくことが、当人にとっていっそうむずかしくなる」(『神学大全』Ⅱa Ⅱae, q. 184, a. 8)
これは、聖トマスの言葉だが、かれのいわゆる“危険”が、どんなものだかについては、すでに前章で、くわしく述べたとおりである。
内的精神をもっていない福音の働き手は、使徒的事業から自然におこってくるいろんな危険を、ちっとも感知しない。かれは強盗や追いはぎの横行するぶっそうな山林を、護身用の武器もなにも持たず、丸腰で通過しようとする旅人に、さもよく似ている。これに反して、まことの使徒は、この山賊どもを、大いに恐れる。恐れるから、毎日、まじめな良心の糾明をして、かれらにたいする警戒を怠らない。良心をまじめに糾明してみれば、自分の弱点がどこにあるかが、すぐ目につく。
「自分は、ひっきりなしに、ある危険にさらされている!」
内的生活のおかげで、こう身にしみてさとっているだけでも、すでに大きな収穫ではないか。そして、危険を自覚している、というこの事実が、道中、不意に賊どもから襲われるという災難を、未然に防止するうえにおいて、どれほど役にたつことだろうか。なぜなら、危険を、事前に見破るということは、すでに半ば危険を脱したことになるからである。
だが、内的生活の利益は、ただこれだけではないのだ。使徒的事業にたずさわっている人にとって、内的生活は、完全で精強な霊的“武具”なのだ。
「兄弟たちよ、悪魔の策略に対抗して立ちうるために、天主の武具で身をかためなさい。……悪しき日にあたって、よく抵抗し、完全に勝ちぬいて、かたく立ちうるために、天主の武具を身につけなさい。すなわち、立って真理のおびを腰にしめ、正義の胸当てを胸につけ、平和の福音のそなえを足にはき、信仰のタテを手に取りなさい。それをもって、悪しき者の放つ矢を消すことができるであろう。また、救いのカブトをかぶり、聖霊の剣、すなわち、天主の言葉を取りなさい」(エフェゾ6・10~17)
これこそは、霊的武具――天主からたまわった武具なのだ。この武具によって、内的使徒は、ただ悪魔の誘惑と策略にむかって抵抗することができるばかりだけでなく、さらに一歩すすんで、おのれのすべての行為を聖化することもできる。
内的生活は、“純潔な意向”を、腰におびさせる。“多くのこと”について、思いわずらわねばならぬ活動的生活の人たちにとって、ただ“唯一の必要事”なる天主にのみ、おのれの思いも、望みも、愛情も、集中させ、定着させておくことは、きわめて大切である。そして、“純潔な意向”こそは、このすぐれた仕事を、みごとにやりとげてくれる。そればかりではない。純潔な意向のおかげで、霊魂は、活動面で、脱線しない。自然の安逸を求めたり、人間的な楽しみにふけったり、世間的な娯楽に、時間を浪費しない。“真理のおびを腰にしめる”とは、このことをいうのである。
内的生活はさらに、使徒の身に、“愛徳”のヨロイをつけてくれる。愛徳のヨロイを身につける人は、剛毅の精神が霊魂にみなぎる。それで、被造物の魅惑にたいして、世間的精神にたいして、悪魔の攻撃にたいして、勇ましく抵抗することができる。“正義の胸当てを胸につける”とは、このことをいうのだ。
内的生活はまた、“用心”と“控え目”という二つの徳を、使徒にあたえる。この二つの徳のおかげで、使徒職にたずさわる人たちは、おのれのすべての行動において、「ハトのように正直」であると同時に、「ヘビのように慎重」でもある。“平和の福音のそなえを足にはく”とは、このことをいうのである。
悪魔と世間は、福音の働き手のあたまに、まちがった教えをたたきこんでやろうと、詭弁をろうしてやまない。かれらを、腐敗した世間の悪習に感染させ、そのエネルギーを消耗させてやろうと、必死になっている。この欺瞞にむかって、内的生活は、“信仰”のタテを取って戦わせる。信仰のタテのかげで、霊魂の目には、天主的理想のともしびが、あかあかと照りかがやく。“信仰のタテを手に取りなさい。それをもって、悪しき者の放つ火の矢を消すことができるであろう”とは、このことをいうのである。
霊魂は、おのれの無力を、心からさとっている。自分の救霊にかんしては、恐れおののいて、万全のそなえと配慮を怠らない。天主のお助けがなければ、自分は絶対に何もできないのだ、と確信している。この確信から、たえまなく祈りが生まれる。嘆願にみちた、しばしばの祈りが。この祈りは、おのれの無能を自覚し、天主のお助けのみに信頼するから、それだけいっそうゆたかな効果に富んでいる。これこそは、つよい青銅のカブトではないだろうか。“傲慢”の強打が、いかに頭上にふりそそいでも、傲慢自体が自滅するばかりだ。“救いのカブトをかぶれ”とは、このことをいうのである。
このように、使徒は、足の爪さきから、頭のてっぺんまで、完全に武装してこそはじめて、なんのおそれもなく、事業に身をゆだねることができるのだ。福音書の黙想によって、かれの奮発心は火と燃える。ご聖体の秘跡によって、かれの霊的エネルギーは増進する。そうなると、使徒職はかれにとって、一つの強力な武器となる。一方においては、かれの霊魂の敵を“撃破”することができると同時に、他方においては、多くの霊魂を“征服”して、これをキリストのものとなすことができる。“聖霊の剣、すなわち、天主の言葉をとりなさい”とは、このことをいうのである。
(B)内的生活は、使徒的活動によって消耗された、心身のエネルギーを回復してくれる
前にも一言したとおり、多忙な仕事の混乱の中にあっても、また、たえまなく世間と交わっていても、すこしも霊魂に害をうけない、りっぱに内的精神を確保している、その考えも、その意向も、いつもタダ天主のなかにだけ集中し固定しておく――ということは、ただ聖人にだけできる仕事である。聖人においては、そのいっさいの外的活動のいとなみが、高度に超自然化され、天主の愛の燃えさかりから出ているので、それはすこしも、心身のエネルギーの減退とはならない。それどころか、かえって、それを機会に、恩寵の増進ともなるのである。
他の人たちにおいては、そうではない。熱心な人たちにおいてさえも。
多少ながいあいだ、外面的な仕事にたずさわれば、末は超自然的生命の衰退におわるようである。
隣人に善をほどこすのは、いいことにはちがいないが、かれらはあまりに、それに没頭しすぎる。他人の惨状に同情し、これを救済するのは殊勝なことだが、この同情も、あまり超自然的動機からは出ておらず、そのうえ、あまりにそのことに気を奪われている。かくてかれらの心は、あまたの不完全のスモッグのために黒ずんだ、純すいでない愛情の炎しか、天主にささげることができないのである。
天主は、霊魂のこの弱さをごらんになっても、怒ってすぐ罰をくだすようなことはなさらない。その恩寵を減らすようなこともなさらない。――もしこの霊魂が、仕事をしているあいだ、よく警戒し、よく祈ろうと、まじめに努力してさえいるなら。また、仕事がおわったら、ご自分のみもとに帰ってきて、休息し、その消耗したエネルギーを回復しようと、常に心がけてさえいるなら。かようにして、霊魂は、活動的生活と内的生活の交錯によってひきおこされる“天主への立ち帰り”を、いつでも、どこでも、くり返していく。そして、この“くり返し”こそは、天父のみ心を、このうえなく、およろこばせするのである。
不完全とたたかう人は、さいわいである。
霊魂は、うむことなく、キリストのみもとに馳せていくことを知るにつれ、不完全そのものもだんだんに減り、それにおちいる回数も、だんだん少なくなっていく。ご自分のもとに馳せてくる霊魂にむかって、イエズスはいつも仰せられるであろう――
「私のもとにおいで。へとへとに疲れきった小鹿のような、あわれな霊魂よ。
巡礼のみちの長く、険しいために、のどは渇き、谷間の水にあえいでいる。
私のもとに来て、生ける水をお飲み。この水のなかにこそ、新たに道をたどるための、新たな力の秘訣を、見いだすだろう。
しばらく、人ごみのさわがしさから遠ざかりなさい。かれらは、あなたの消耗しつくされた力が求めている旅のかてを、あなたにあたえることはできない。
「さあ、あなたは、人をさけて寂しい処へ行って、しばらく休むがよい」(マルコ6・30)
私のところには、静けさがある。平和がある。
まもなくあなたは、最初の若さを、失われた青春をとりもどすだろう。
そればかりではない。あなたはそこに、より少ない苦労をもって、より大きな働きをする秘訣を、手段を見いだすだろう。
エリヤは、旅に疲れて、半死半生だった。暗い気持ちにとざされていた。
だが、あのふしぎなパンを食べるとすぐに、失われた気力を回復したではないか。
そのように、私は、自分の使徒なるあなたにも、――私と共同の救い主として、人類救済のいともうらやましい聖業に協力させるため、私自身が選んだあなたにも、同様の旅のかてをあたえる。
生命そのものなる私の言葉こそは、万物をいのちづける私の恩寵こそは、すなわち、私の血肉こそは、まさしく、このかてなのだ。
これを食べ、これを飲むがいい。そうしたら、あなたは新たな気力を恵まれて、精神を高く、永遠の彼岸にあげることができよう。あなたの心と私の心のあいだに、親しい友情のちぎりを結ぶことができよう。
私のもとにおいで。あなたは旅路に疲れて、しおれている。
幻滅の悲しみに、現実の裏切りに、おしつぶされている。
私は、あなたを、慰めてあげよう。
私の心は、あなたをいつくしむその愛に、燃えさかっている。
私の愛のかまどのなかで、あなたの再起の決心を、きたえあげるがよい。
『すべて重荷をせおって、苦労している者は、私のもとに来なさい。あなたがたを、休ませてあげよう』(マテオ11・28)……」
(この章 続く)
愛する兄弟姉妹の皆様、
恒例のドン・ショタール著「使徒職の秘訣」L'Ame de tout apostolat
第三部 内的生活が善徳への進歩を保証してくれなければ活動的生活はむしろ危険である
三、福音の働き手の聖性 ―― その土台は内的生活である
をご紹介します。山下房三郎 訳を参考に、フランス語を参照して手を加えてあります。
天主様の祝福が豊かにありますように!
トマス小野田圭志神父(聖ピオ十世会司祭)

第三部 内的生活が善徳への進歩を保証してくれなければ、活動的生活はむしろ危険である
三、 福音の働き手の聖性 ―― その土台は内的生活である(続き)
(A)内的生活は、使徒的事業につきものの危険にたいして、霊魂を予防してくれる
「人びとの霊魂の世話をゆだねられたときは、そのたずさわる仕事に付随している外的危険のため、あくまでも善良な生活を生きぬくことが、当人にとっていっそうむずかしくなる」(『神学大全』Ⅱa Ⅱae, q. 184, a. 8)
これは、聖トマスの言葉だが、かれのいわゆる“危険”が、どんなものだかについては、すでに前章で、くわしく述べたとおりである。
内的精神をもっていない福音の働き手は、使徒的事業から自然におこってくるいろんな危険を、ちっとも感知しない。かれは強盗や追いはぎの横行するぶっそうな山林を、護身用の武器もなにも持たず、丸腰で通過しようとする旅人に、さもよく似ている。これに反して、まことの使徒は、この山賊どもを、大いに恐れる。恐れるから、毎日、まじめな良心の糾明をして、かれらにたいする警戒を怠らない。良心をまじめに糾明してみれば、自分の弱点がどこにあるかが、すぐ目につく。
「自分は、ひっきりなしに、ある危険にさらされている!」
内的生活のおかげで、こう身にしみてさとっているだけでも、すでに大きな収穫ではないか。そして、危険を自覚している、というこの事実が、道中、不意に賊どもから襲われるという災難を、未然に防止するうえにおいて、どれほど役にたつことだろうか。なぜなら、危険を、事前に見破るということは、すでに半ば危険を脱したことになるからである。
だが、内的生活の利益は、ただこれだけではないのだ。使徒的事業にたずさわっている人にとって、内的生活は、完全で精強な霊的“武具”なのだ。
「兄弟たちよ、悪魔の策略に対抗して立ちうるために、天主の武具で身をかためなさい。……悪しき日にあたって、よく抵抗し、完全に勝ちぬいて、かたく立ちうるために、天主の武具を身につけなさい。すなわち、立って真理のおびを腰にしめ、正義の胸当てを胸につけ、平和の福音のそなえを足にはき、信仰のタテを手に取りなさい。それをもって、悪しき者の放つ矢を消すことができるであろう。また、救いのカブトをかぶり、聖霊の剣、すなわち、天主の言葉を取りなさい」(エフェゾ6・10~17)
これこそは、霊的武具――天主からたまわった武具なのだ。この武具によって、内的使徒は、ただ悪魔の誘惑と策略にむかって抵抗することができるばかりだけでなく、さらに一歩すすんで、おのれのすべての行為を聖化することもできる。
内的生活は、“純潔な意向”を、腰におびさせる。“多くのこと”について、思いわずらわねばならぬ活動的生活の人たちにとって、ただ“唯一の必要事”なる天主にのみ、おのれの思いも、望みも、愛情も、集中させ、定着させておくことは、きわめて大切である。そして、“純潔な意向”こそは、このすぐれた仕事を、みごとにやりとげてくれる。そればかりではない。純潔な意向のおかげで、霊魂は、活動面で、脱線しない。自然の安逸を求めたり、人間的な楽しみにふけったり、世間的な娯楽に、時間を浪費しない。“真理のおびを腰にしめる”とは、このことをいうのである。
内的生活はさらに、使徒の身に、“愛徳”のヨロイをつけてくれる。愛徳のヨロイを身につける人は、剛毅の精神が霊魂にみなぎる。それで、被造物の魅惑にたいして、世間的精神にたいして、悪魔の攻撃にたいして、勇ましく抵抗することができる。“正義の胸当てを胸につける”とは、このことをいうのだ。
内的生活はまた、“用心”と“控え目”という二つの徳を、使徒にあたえる。この二つの徳のおかげで、使徒職にたずさわる人たちは、おのれのすべての行動において、「ハトのように正直」であると同時に、「ヘビのように慎重」でもある。“平和の福音のそなえを足にはく”とは、このことをいうのである。
悪魔と世間は、福音の働き手のあたまに、まちがった教えをたたきこんでやろうと、詭弁をろうしてやまない。かれらを、腐敗した世間の悪習に感染させ、そのエネルギーを消耗させてやろうと、必死になっている。この欺瞞にむかって、内的生活は、“信仰”のタテを取って戦わせる。信仰のタテのかげで、霊魂の目には、天主的理想のともしびが、あかあかと照りかがやく。“信仰のタテを手に取りなさい。それをもって、悪しき者の放つ火の矢を消すことができるであろう”とは、このことをいうのである。
霊魂は、おのれの無力を、心からさとっている。自分の救霊にかんしては、恐れおののいて、万全のそなえと配慮を怠らない。天主のお助けがなければ、自分は絶対に何もできないのだ、と確信している。この確信から、たえまなく祈りが生まれる。嘆願にみちた、しばしばの祈りが。この祈りは、おのれの無能を自覚し、天主のお助けのみに信頼するから、それだけいっそうゆたかな効果に富んでいる。これこそは、つよい青銅のカブトではないだろうか。“傲慢”の強打が、いかに頭上にふりそそいでも、傲慢自体が自滅するばかりだ。“救いのカブトをかぶれ”とは、このことをいうのである。
このように、使徒は、足の爪さきから、頭のてっぺんまで、完全に武装してこそはじめて、なんのおそれもなく、事業に身をゆだねることができるのだ。福音書の黙想によって、かれの奮発心は火と燃える。ご聖体の秘跡によって、かれの霊的エネルギーは増進する。そうなると、使徒職はかれにとって、一つの強力な武器となる。一方においては、かれの霊魂の敵を“撃破”することができると同時に、他方においては、多くの霊魂を“征服”して、これをキリストのものとなすことができる。“聖霊の剣、すなわち、天主の言葉をとりなさい”とは、このことをいうのである。
(B)内的生活は、使徒的活動によって消耗された、心身のエネルギーを回復してくれる
前にも一言したとおり、多忙な仕事の混乱の中にあっても、また、たえまなく世間と交わっていても、すこしも霊魂に害をうけない、りっぱに内的精神を確保している、その考えも、その意向も、いつもタダ天主のなかにだけ集中し固定しておく――ということは、ただ聖人にだけできる仕事である。聖人においては、そのいっさいの外的活動のいとなみが、高度に超自然化され、天主の愛の燃えさかりから出ているので、それはすこしも、心身のエネルギーの減退とはならない。それどころか、かえって、それを機会に、恩寵の増進ともなるのである。
他の人たちにおいては、そうではない。熱心な人たちにおいてさえも。
多少ながいあいだ、外面的な仕事にたずさわれば、末は超自然的生命の衰退におわるようである。
隣人に善をほどこすのは、いいことにはちがいないが、かれらはあまりに、それに没頭しすぎる。他人の惨状に同情し、これを救済するのは殊勝なことだが、この同情も、あまり超自然的動機からは出ておらず、そのうえ、あまりにそのことに気を奪われている。かくてかれらの心は、あまたの不完全のスモッグのために黒ずんだ、純すいでない愛情の炎しか、天主にささげることができないのである。
天主は、霊魂のこの弱さをごらんになっても、怒ってすぐ罰をくだすようなことはなさらない。その恩寵を減らすようなこともなさらない。――もしこの霊魂が、仕事をしているあいだ、よく警戒し、よく祈ろうと、まじめに努力してさえいるなら。また、仕事がおわったら、ご自分のみもとに帰ってきて、休息し、その消耗したエネルギーを回復しようと、常に心がけてさえいるなら。かようにして、霊魂は、活動的生活と内的生活の交錯によってひきおこされる“天主への立ち帰り”を、いつでも、どこでも、くり返していく。そして、この“くり返し”こそは、天父のみ心を、このうえなく、およろこばせするのである。
不完全とたたかう人は、さいわいである。
霊魂は、うむことなく、キリストのみもとに馳せていくことを知るにつれ、不完全そのものもだんだんに減り、それにおちいる回数も、だんだん少なくなっていく。ご自分のもとに馳せてくる霊魂にむかって、イエズスはいつも仰せられるであろう――
「私のもとにおいで。へとへとに疲れきった小鹿のような、あわれな霊魂よ。
巡礼のみちの長く、険しいために、のどは渇き、谷間の水にあえいでいる。
私のもとに来て、生ける水をお飲み。この水のなかにこそ、新たに道をたどるための、新たな力の秘訣を、見いだすだろう。
しばらく、人ごみのさわがしさから遠ざかりなさい。かれらは、あなたの消耗しつくされた力が求めている旅のかてを、あなたにあたえることはできない。
「さあ、あなたは、人をさけて寂しい処へ行って、しばらく休むがよい」(マルコ6・30)
私のところには、静けさがある。平和がある。
まもなくあなたは、最初の若さを、失われた青春をとりもどすだろう。
そればかりではない。あなたはそこに、より少ない苦労をもって、より大きな働きをする秘訣を、手段を見いだすだろう。
エリヤは、旅に疲れて、半死半生だった。暗い気持ちにとざされていた。
だが、あのふしぎなパンを食べるとすぐに、失われた気力を回復したではないか。
そのように、私は、自分の使徒なるあなたにも、――私と共同の救い主として、人類救済のいともうらやましい聖業に協力させるため、私自身が選んだあなたにも、同様の旅のかてをあたえる。
生命そのものなる私の言葉こそは、万物をいのちづける私の恩寵こそは、すなわち、私の血肉こそは、まさしく、このかてなのだ。
これを食べ、これを飲むがいい。そうしたら、あなたは新たな気力を恵まれて、精神を高く、永遠の彼岸にあげることができよう。あなたの心と私の心のあいだに、親しい友情のちぎりを結ぶことができよう。
私のもとにおいで。あなたは旅路に疲れて、しおれている。
幻滅の悲しみに、現実の裏切りに、おしつぶされている。
私は、あなたを、慰めてあげよう。
私の心は、あなたをいつくしむその愛に、燃えさかっている。
私の愛のかまどのなかで、あなたの再起の決心を、きたえあげるがよい。
『すべて重荷をせおって、苦労している者は、私のもとに来なさい。あなたがたを、休ませてあげよう』(マテオ11・28)……」
(この章 続く)