―真珠湾「奇襲」の負い目―
敗戦国となってしまったからには、あの戦争において「奇襲をした」という“負い目”があることを触れまいとする人々がいる。
三根生久大(大正15年生)は「ワシントンの日本大使館の不手際によって『日米交渉打切り』の通告が開戦後になった」と大使館の不手際による予期せぬ結果としての「奇襲」ということにしてしまう。
入江隆則(昭和10年生)は「ハルノート」という最後通牒が突き付けられたならば、開戦責任はアメリカにあると言う。「米大統領の腹は参戦に定まっている」と分かった以上、日本は捨身の攻撃をせざるを得ない場所に追い込まれた、とも言う。
真珠湾奇襲を「大使館の不手際」の所為にするが、実は「ハルノート」が米国の最後通牒だった、と開き直る人も居る。海軍士官の後官僚となり、後に研究生活に入った伊部英男(大正10年生)のように両論併記の人も居る。
他方、「ハルノートは日付けがないので、最後通牒ではない」という吉田茂の見方を支持し、「大使館の不手際」を厳しく指摘する北岡伸一(昭和23年生)という著名な学者もいる。この方は政府の委員を勤めるなど市井の名もなき学者でありませんが、…。

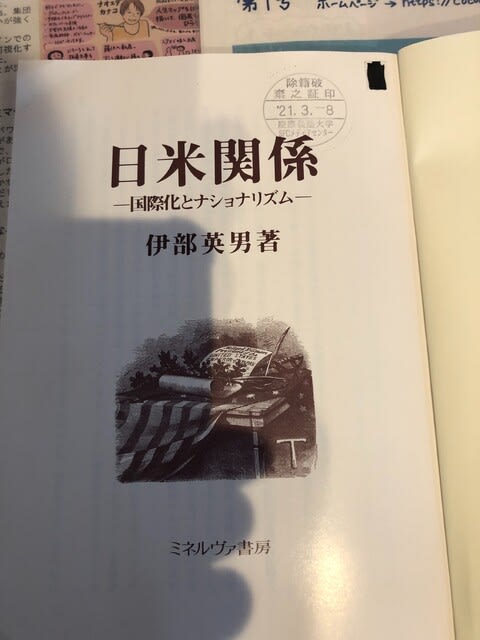
※()内数字は著者の生年を入れました。
【引用文献:三根生久大『日本の敗北』文芸春秋、入江隆則『敗者の戦後』中公叢書、黒野耐『参謀本部と陸軍大学校』講談社現代新書、伊部英男『日米関係-国際化とナショナリズム』ミネルヴァ書房、北岡伸一『政党から軍部へ』中央公論新社】















