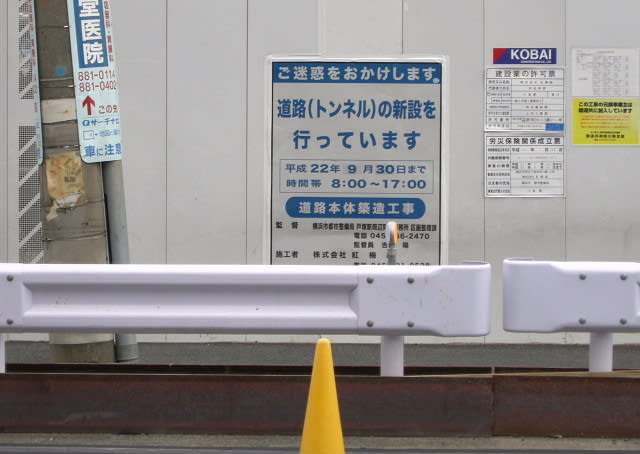東俣野の祠の右手の坂道を上るとそこが東俣野中央公園でした。
子供の遊び場がありましたが、子供も大人も姿が見えませんでした。

段丘の傾斜に作られた公園なので、更に坂道を上ると見晴らしに出ました。
すぐ下にテニスコートがあり、ここは賑わっていました。
はるか向こうには、境川の右岸の段丘が見えます。
かすかに見えるビルは日本大学生物資源科学部の校舎です。

見晴らしの裏手は芝生広場が広がり、その奥に運動場が見えました。

見晴らしから下る立派な階段がありました。
右手遠くに見えるのは以前ドリームランドがあった地域です。

下ってきた階段を振り返りました。

ここには公園の案内図がありました。駐車場も完備していました。
どうやらここが正門のようです。