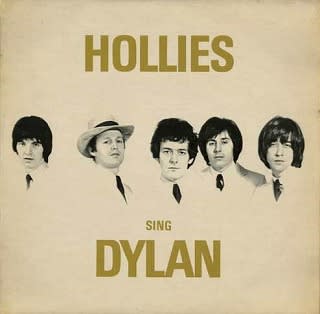■Hold Your Head Up c/w Trgedy / Argent (Epic / CBSソニー)
1970年代キーボードロックの雄だったアージェントが、どうにかブレイクのきっかけとしたヒットが、本日ご紹介のシングル盤A面曲でした。
当時のメンバーはロッド・アージェント(vo,key)、ラス・バラード(vo,g,key)、ジム・ロッドフォード(b,vo)、ロバート・ヘンリット(ds,per) の4人編成で、本国イギリスでは1971年11月に発売され、翌年の春になって、ようやくチャートの上位にランクされたという遅咲きのヒットではありましたが、とにかくアージェントにとっては躍進の第一歩! そして我国でも昭和47(1972)年、ラジオの洋楽番組を中心に小ヒットしています。
で、これまでにも度々述べてきたように、アージェントはゾンビーズ直系の進化形グループとして、如何にも1970年代的なロックジャズとプログレの美しき融合だったわけですが、告白するとサイケおやじがアージェントを最初に聴いたのは、この「Hold Your Head Up」だったのです。
ただしスリー・ドッグ・ナイトのヒット曲「Liar」のオリジナルがアージェントであった事実を既に知っていたことから、身構えていたのは言うまでもありません。そしてこのシングル盤を買い、そこに掲載されていた解説文を読んで、大好きだったゾンビーズがアージェントに進化した経緯を知ったというわけです。
肝心の曲調はミディアムテンポで幾分単調なリズムパータンを用いながら、サビのキメになっている「Hold Your Head Up」というリフレインが覚えやすく、一緒に歌いながら、自然と気分が高揚していくという仕掛けは、ヒット曲の必要十分条件でした。
ちなみにこの曲はアージェントにとって3枚目のアルバムとなった「オール・トゥゲザー・ナウ」からの先行シングルとして、6分超のアルバムバージョンを3分弱に編集した所謂シングルバージョンですが、これには世界各国で様々な仕様が存在していると言われています。参考までに、この日本盤のランニングタイム表記は2分50秒!
しかし正直、アルバムバージョンに接してしまえば、完全に物足りません。
さらに言えば、歌と演奏の第一印象が、同時期に絶頂の人気を謳歌していたエマーソン・レイク&パーマーを狙った事がミエミエでしたから、アージェントの実力を完全に発揮しているアルバムバージョンが素晴らしいに決まっています。
その意味でB面に収録された「悲劇」なんていうストレートな邦題がつけられ「Trgedy」は、絶妙にファンキーなギターイントロからシンコペイトしたベースと重心の低いドラムスが全体をリードする名曲にして名演! アージェントならではのコーラスワークとキーボートの存在感、さらにゾンビーズ直系というキメのメロディ展開も最高という熱いハードロック♪♪~♪
個人的には、こっちの面ばっかり聴いていたのが当時の本音でした。
中間部で炸裂するベースとギターのカッコ良いユニゾンリフからオルガンのアドリブへと続く展開には、本当にゾクゾクさせられますよ。
ちなみに、この曲はイギリス等では「Hold Your Head Up」に続くシングルA面曲として、またまた短く編集されたシングルバージョンが登場し、期待どおりにヒットしていますが、この日本盤に収録されたのはアルバムバージョン! しかも微妙にミックスが異なっていますから要注意です。
もちろん件のシングルバージョンも、あらためて日本発売されたのですから、なんとも罪作りではありますが、そんなこんなもヒット曲と洋楽の楽しみだと思います。
ということで、ここで完全にアージェントの虜となった若き日のサイケおやじは、まずはこの2曲が収録されている前述のサードアルバムを買い、続けて1st「アージェント」と2nd「リング・オブ・ハンズ」の2枚のLPをゲットして、シビレまくったという次第です。
ただし、それでもリアルタイムの我国では、アージェントなんて、本当に「なんて」の評価しか得られず、知る人ぞ知るとい存在に甘んじていたのです。しかしそれが再び、あるきっかけで注目されることになるというお話は、次回へのお楽しみとさせていただきます。