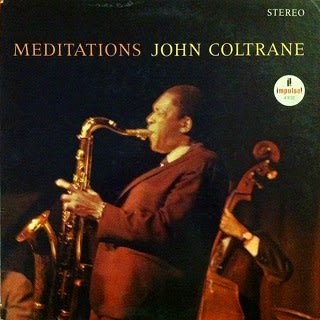■Albert King with Stevie Ray Vaughan In Session (Stax = CD + DVD)
アルバート・キングは、黒人ブルースマンの中では恣意的とも思えるほどにロックやソウルに接近した音楽性で幅広い人気がありましたから、ブルースロックをやっている白人ミュージャンとの共演においても、すんなりマイペースでやっていたという証拠物件のひとつが、本日掲載のCDとDVDのセット物です。
内容は、1983年12月6日に収録されたテレビ放送用のスタジオセッションで、なんとっ!
アルバート・キング(vo,g) のバンドに
スティーヴィー・レイ・ヴォーン(vo,g) が特別参加したという、これはもちろんブルース愛好家よりもロックファンが大喜びの企画でしょう。なにしろその時期は、スティーヴィー・レイ・ヴォーンがメジャーデビューして忽ち注目を集めていたわけで、しかも自らのギタースタイルに大きな影響を受けたのがアルバート・キングと公言していたのですから、願ったり叶ったり!?!
そこで、まずは本篇とも言える映像を収めたDVDからご紹介させていただきます。
Act Ⅰ
01 Introduction
02 悪い星の下に / Born Under a Bad Sign
03 Texas Flood (feat. Stevie Ray Vaughan - vocal)
04 Call It Stormy Monday
05 "Old Times" (talk)
Act Ⅱ
06 Match Box Blues
07 "Pep Talk" (talk)
08 Don't You Lie To Me
09 "Who Is Stevie?" (talk)
10 Pride and Joy (feat. Stevie Ray Vaughan - vocal)
The Finale
11 I'm Gonna Move to the Outskirts of Town
12 Outtro
で、演奏本篇は、これぞっ!
ルーツ・オブ・ブルースロックとも言うべき、アルバート・キングの代名詞でもある大ヒット曲「
悪い星の下に / Born Under a Bad Sign」が演奏されるのは、殊更スティーヴィー・レイ・ヴォーンのファンにとっては安心印ではありますが、やはり御大を前にしてのギタープレイには緊張からでしょうか、慎重に傾き過ぎたような遠慮とプレッシャーが感じられるのは、至極当然だと思います。
そして、そのあたりを懐の深さで受け止めるアルバート・キングが見事なお手本を示すのは、もちろん貫録でもマンネリでもなく、常に真摯なプレイを積み重ねてきたブルース魂のナチュラルな発露に他ならないでしょう。
ちなみに映像をご覧になれば一目瞭然、左利きのアルバート・キングは弦の張り方が右利きそのまんまなので、低音弦が下に、そして高音弦が上に位置する事から、押弦運指は全く独特であり、チョーキングにしても高音弦は押し上げるのではなく、引き下げるという変則奏法!?!
しかもピックは使わず、指弾きなんですから、以下はサイケおやじの独断と偏見による考察ではありますが、エグ味の効いたヴィブラートやダブルノートのチョーキングにおける大袈裟感は、それゆえに可能な必殺技のような気がしますし、当然ながらチューニングもレギュラーではない事が、映像を見ながらコピーするまでもなく、まさに一目瞭然でしょう。
おそらくは低い方から「C(♯)BEG(♯)BF」かと思われますが、これまた確証はございませんので、皆様からの御意見をお伺いしとうございます。
それとアルバート・キングのギタープレイの個性というか、速弾きはやらず、所謂「間」を活かした、それでいて息の長い(?)フレーズを出していくのは、それだけひとつひとつの音の強弱を大切にしている事が明白♪♪~♪
また、マイナースケールの頻繁な使用が逆にソウルやロックを強く感じさせる要因かもしれません。
ですから、スティーヴィー・レイ・ヴォーンが公式デビューアルバムのタイトル曲にしていたスローブルースの「Texas Flood」では、最初っから些かカッコつけ気味のギタープレイに入ってしまう白人の若者を諫めるかの如く、最初はわざとらしくも抑えたところから、グイグイと熱く盛り上げ、しまいには座っていた椅子から立ち上がっての力演を披露するアルバート・キングに感動ですよっ!
また、そうなれば、スティーヴィー・レイ・ヴォーンだって、甘えていられるはずもなく、十八番の手癖も出せるほどリラックスしたところから、いよいよの本領発揮ですから、これには御大もニンマリと上機嫌♪♪~♪
画面の前のサイケおやじも、我知らず惹きつけられてしまいましたですよ♪♪~♪
なにしろ演奏はそのまんまの熱気で、ブルース&ブルースロックの有名曲「Call It Stormy Monday」に雪崩れ込み、グリグリのエレトクリック・ギター・ブルース大会に発展するのですからっ!
長い長い演奏が終わってから、新旧ブルースマンががっちり握手を交わすのも、演出以上の衝動があればこそでしょう。
以上が前半の「Act Ⅰ」ですが、既にここまでの40分弱で、このプログラムの真髄は堪能出来るんですが、続く「Act Ⅱ」は、それゆえに和みも好ましいパートで、軽い雰囲気の「Match Box Blues」では、律儀なスティーヴィー・レイ・ヴォーンに対し、ノリが大きいアルバート・キングが流石と思わせますよ。
それは8ビート主体のファンキーブルース「Don't You Lie To Me」にも引き継がれ、必死の表情も印象的なスティーヴィー・レイ・ヴォーンがブルースに拘れば、アルバート・キングが余裕でブルースロックなギタープレイをやってしまうあたり、いゃ~、ニクイばかりの演出とでも申しましょうか、たまりませんねぇ~~、実に♪♪~♪
こうして演奏は、いよいよ佳境へ突入、スティーヴィー・レイ・ヴォーンが十八番の自作曲「Pride and Joy 」は皆様ご推察のとおり、イケイケのシャッフルビートでノリまくった演奏は、新旧両ギタリストがボケとツッコミを双方やらかす楽しさに溢れていて、こ~ゆ~リラックスした味わいこそが、ブルースロックのひとつの醍醐味かもしれません、と独り納得!
ですから「The Finale」でじっくり&じんわり演奏される「I'm Gonna Move to the Outskirts of Town」こそは、モダンブルースの盃事でしょうか、その神妙にして真摯な儀式の如き作法の伝承には、グッと惹きつけられてしまいます。
それは前向きなスティーヴィー・レイ・ヴォーンを緩急自在に翻弄するアルバート・キングの老獪さでもあり、少しずつビートを強めながら展開される魂の会話は熱くて濃密!
もちろん最終盤で、ブルース&ブルースロックのギグでは定番のアクションもご覧になれますし、演奏終了後の和んだ会話は、このセッションの雰囲気の良さをダイレクトに伝えるものだと思います。
あぁ……、これがエレクトリック・ギター・ブルースの奥儀なんでしょうねぇ~~、サイケおやじは畏敬の念を抑えきれません。
ちなみに演奏の合間に入る「語り」のパートでは、様々な内輪話っぽいところから、業界(?)の大先輩から新人への「アドバイス」と「余計なお世話」のバランスの妙が味わい深く、意味不明な言葉=スラングもあるもんですから、サイケおやじには解せないところもあるんですが、それはそれで面白いんじゃ~ないでしょうか?
書き遅れましたが、このスタジオセッションには観客が入っていませんので、尚更に両者の気持の交流がストレートに伝わってくるあるような気も致します。
以上、とにかく鑑賞する度にシビレるスタジオライブ映像には収まらなかった演奏パートがあったということで、CDには、それも含む以下のトラックが入っています。
01 Call It Stormy Monday
02 "Old Times" (talk)
03 Pride and Joy
04 Ask Me No Questions
05 "Pep Talk" (talk)
06 Blues at Sunrise
07 "Turn It Over" (talk)
08 Overall Junction
09 Match Box Blues
10 "Who Is Stevie?" (talk)
11 Don't Lie to Me
上記の演奏中、DVDで楽しめる楽曲は基本的には同じテイクなんですが、幾分の編集やミックスの違いもあり、曲順が異なるのもそうですが、例えド頭「Call It Stormy Monday」は、映像パートでは「Texas Flood」からの流れの中でアルバート・キングが転調して始めていたところを、ここではそれを巧みに編集してありますが、それを知っていれば些かの物足りなさはあるものの、許せないとは申せません。
それよりも、このCDオンリーのトラックは、やはり気になるウリでありましょう。
それがまずはB.B.キングの「Ask Me No Questions」では楽しいブルースロック仕立てながらも、それゆえにリラックスしたスティーヴィー・レイ・ヴォーン、さらにお気楽なアルバート・キングという連鎖反応的なプレイは、こ~ゆ~セッションならではの結果オーライかもしれませんが、続く「Blues at Sunrise」はアルバート・キングがステージライブでは十八番にしている独白(?)のスローブルースですから、油断は禁物!?
情感溢れるアルバート・キングのギターは言わずもがな、スティーヴィー・レイ・ヴォーンが本領発揮以上の凄さ全開!
ですから御大も上機嫌なのがサウンドだけからでも伝ってきますよっ!
あぁ~~、最高だあぁぁぁぁぁぁ~~~~♪
この、15分超っ!!
ちなみに、これは映像パートでも同じだったんですが、右チャンネル寄りにアルバート・キング、そして左チャンネル寄りにスティーヴィー・レイ・ヴォーンのギターが定位したミックスなんで、丁々発止のギター合戦、ボーカルに寄り添ったり、ツッコミを入れたりするオカズのフレーズ、さらには伴奏コードの様々な用い方等々がストレスを感じずに判明するのも、このセット物が高得点の証です。
そして、これまたアルバート・キングの十八番たるインストの「Overall Junction」は、ヘヴィなシャッフルビートでノリにノッた演奏ですが、前曲「Blues at Sunrise」が凄過ぎた所為か、美味しいデザート感覚と書けば、こりゃ~、不遜の極みと反省するしかございません。
特にアルバート・キングの手慣れているようで、実は深味満点のギターは、やっぱり強烈ですからっ!
ということで、今週は初っ端から仕事で苦しみましたが、そんなこんなの「気分はぶる~す」なところから立ち直るのにも、サイケおやじは大好物のブルースロックを欲してしまうわけです。
最後になりましたが、このセッションを支えたアルバート・キングの子飼いのリズム隊は流石に手堅く、時にファンキーな、あるいはロッキンソウルなリズムとビートを提供しているあたりも聴き逃せませんというよりも、自然に耳がそっちに惹きつけられる事も度々でしたねぇ~~♪
また、ここまでの拙文ではギタープレイばっかり書いてしまいましたが、アルバート・キングのボーカリストとしての魅力だって決して侮れません。ゴスペル系のシャウトやコブシはそれほど出ませんが、抑揚を大切にした哀愁フィーリングのソウルフルな節回しは、サイケおやじの好むところです。
うむ、ここで繰り広げられた名演&熱演に接しながら、思わず傍らにあった自分のギターに手を伸ばしてしまった己が恥ずかしい……。
虚心坦懐に、端座して鑑賞するべしっ!
と、自分に言い聞かせているのでした。
※追記:DVDは日本製の再生機器で全く問題無く鑑賞出来ます。画質も良好♪