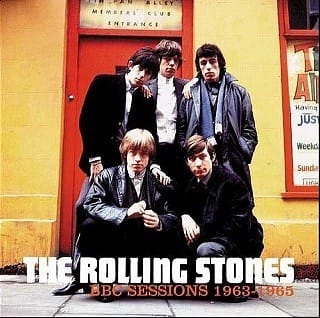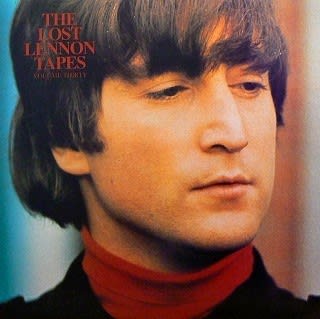■On Air / The Rolling Stones (abkco)

★Disc 1
01 Come On ※:1963年9月23日録音 / 同年10月26日放送
02 (I Can't Get No) Satisfaction ※:1965年8月20日録音 / 同年8月30日放送
03 Roll Over Beethoven ※:1963年9月23日録音 / 同年10月26日放送
04 The Spider And The Fly ■:1965年8月20日録音 / 同年8月30日放送
05 Cops And Robbers ●:1964年3月19日録音 / 同年5月9日放送
06 It's All Over Now ◎:1964年7月17日録音 / 同日放送
07 Route 66 ●:1964年3月19日録音 / 同年5月9日放送
08 Memphis, Tennessee ※:1963年9月23日録音 / 同年10月26日放送
09 Down The Road Apiece ▲:1965年3月1日録音 / 同年3月6日放送
10 The Last Time ▲:1965年3月1日録音 / 同年3月6日放送
11 Cry To Me ※:1965年8月20日録音 / 同年8月30日放送
12 Mercy, Mercy ■:1965年8月20日録音 / 同年8月30日放送
13 Oh! Baby (We Got A Good Thing Goin’) ※:1965年8月20日録音 / 同年8月30日放送
14 Around And Around ▲:1964年7月17日録音 / 同年7月23日放送
15 Hi Heel Sneakers ※:1964年4月13日録音 / 同年4月18日放送
16 Fannie Mae ※:1965年8月20日録音 / 同年8月30日放送
17 You Better Move On ●:1964年3月19日録音 / 同年5月9日放送
18 Mona ●:1964年3月19日録音 / 同年5月9日放送
★Disc 2
01 I Wanna Be Your Man ※:1964年2月3日録音 / 同年2月8日放送
02 Carol ※:1964年4月13日録音 / 同年4月18日放送
03 I'm Moving On ◎:1964年3月19日録音 / 同年4月10日放送
04 If You Need Me ◎:1964年7月17日録音 / 同日放送
05 Walking The Dog ※:1964年2月3日録音 / 同年2月8日放送
06 Confessin' The Blues ◎:1964年7月17日録音 / 同日放送
07 Everybody Needs Somebody To Love ▲:1965年3月1日録音 / 同年3月6日放送
08 Little By Little ◎:1964年3月19日録音 / 同年4月10日放送
09 Ain't That Loving You Baby ◇:1964年10月8日録音 / 同年10月31日放送
10 Beautiful Delilah ※:1964年4月13日録音 / 同年4月18日放送
11 Crackin' Up ▲:1964年7月17日録音 / 同年7月23日放送
12 I Can't Be Satisfied ▲:1964年7月17日録音 / 同年7月23日放送
13 I Just Want To Make Love To You ※:1964年4月13日録音 / 同年4月18日放送
14 2120 South Michigan Avenue ◇:1964年10月8日録音 / 同年10月31日放送
※Saturday Club
●Blues in Rhythm
◎The Joe Loss Pop Show
▲Top Gea
◇Rhythm and Blues
■Yeah Yeah
殊更最近のストーンズは例のアーカイヴ商法がメインなもんですから、サイケおやじも片っ端からお金を吸い上げられていながら、実は多くのブツは未開封&未視聴になっている中にあって、本日ご紹介の2枚組CDは久々に届いたその日にガッツリ聴き込んだという、まさに待望の復刻作!
だってストーンズが最高に上り調子だった1963年から1965年にかけて出演した、イギリスはBBCにおける放送用音源が公式リリースというだけで、血沸き肉躍ってしまうのがストーンズ信者のみならず、ロックファン全ての宿業でしょう、これはっ!
と、思わずノッケから力んでしまいましたが、ご存じのとおり、このBBCからの音源は昔っから夥しいブートのネタ元になっていましたから正直、それほどの新鮮味が無かったのは偽りのない本音ですし、細かい不満も各所に散見されました。
まず簡単に上記した録音&放送日時を考慮すれば、この復刻CDの編集は如何にも中途半端な違和感が拭いきれないのは、昔っからこの音源のブートに親しんできたストーンズ信者だけの感想なんでしょうか……。
なにしろ現在ではブートでも、ストーンズのBBC関連の音源が可能な限り時系列&セッション毎に纏めて聴けるようになっていますからねぇ~~。
ただし、それは当然ながら、演目にダブリがあって、同じ歌と演奏がテイク違いとはいえ、何度も入っているというところを鑑みれば、あくまでもそれはマニアの領域でありますから、シンプルに最良の形で初期のストーンズの生の姿を楽しんでもらいたいという制作者側の狙いも正当なものと思います。
そして実際、虚心坦懐にこれを聴いていけば、音質のバラツキはそれなりにあろうとも、意外にすんなりと受け入れられるものが確かにあるんですねぇ~~♪
しかし、あらためて不満を述べさせていただければ、低音域に関してはベースのモコモコ感があまり解消されていませんし、ドラムスも軽い感じで引っ込み気味というあたりは、やはり1960年代の音源という事を痛切に思うばかりで、だからこその有難味に感謝するべきなのかもしれません。
そこで肝心の歌と演奏については、何と言ってもミック・ジャガーのボーカルの猥雑な味わいが伝統的な黒人音楽が新しい白人音楽であるロックに収斂した素晴らしさ!?
いゃ~、本当に良い味が出まくっているんですねぇ~~♪
またバンド全体の纏まりとノリも、時には危なっかしいところもありながら、ブライアン・ジョーンズ在籍時ならではの突進力が大いに魅力♪♪~♪
中でも「It's All Over Now」のタテノリ感、「Down The Road Apiece」の強烈なロックのグルーヴ、ブラインアン・ジョーンズの素晴らしすぎるスライドに身震いしてしまう「I Can't Be Satisfied」、ふにゃふにゃのブルースフィーリングが心地良い「The Spider And The Fly 」等々、こ~ゆのを聴いていると、やっぱりサイケおやじはストーンズに中毒している事を自覚するばかり♪♪~♪
それとリアルタイムでは公式レコーディングされていなかった演目が入っているところもウリのひとつでしょうか。
特に「Roll Over Beethoven 」はビートルズとは異なったカッコ良さが満点ですよっ!
ということで、本当はまだまだ不満も書き足りないところがあり、また同時に納得して堪能出来る点も多々ございますが、それでもよ~やくストーンズのBBC音源が公式盤として世に出たのは嬉しくも、素晴らしい事ですっ!
そして最後になりましたが、あえて比較用として夥しいブートの中から「BBC SESSIONS 1963-1965 (GOLDPLATE GP-1203CD1/2)」 という2枚組CDをオススメしておきたく思います。もちろん言わずもがなではありますが、音質は公式盤には及びませんが、だからこそ、逆に迫力がある歌と演奏が楽しめるのも確かな事実というのが、ブートの功罪なんでしょうねぇ……。
うむ、やっぱりストーンズは何時だって熱いですっ!